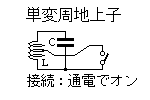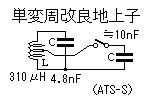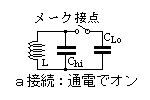ATS,ATC,車内警報装置概説
現物が先にあって後付で定義されることが多いので、各装置毎に微妙な曖昧さを抱えているが、本質は運転安全装置であり鉄道では保安装置と呼ばれるもので、各国毎の考え方や慣行で区分と命名は異なるが、西欧系は列車防護装置ATPとして機能により4つにクラス分けして定義、日本型保安装置については、車内警報装置、ATS、ATCと区分している。それぞれ一言で言えば、- 車内警報装置(車警)とは停止R現示を警報するもの
- 自動列車停止装置:ATSとは制限速度を超える過速度の列車やR現示で安全範囲を越える列車を強制停止させる装置
- 自動列車制御装置:ATCは連続制御で安全な制限速度内に減速する装置である。
 日記目次 |
 総目次 |
|---|---|
 ATS-S車上装置全回路図:Click↑ | |
「(停止信号)車内警報装置」に、5秒の時素で非常制動を掛けるだけのEB装置・デッドマン装置である。ボタン操作・確認扱いによって、信号動作と運転士個人の責任分界とする装置であるが、機能はATSではない。 すなわち「R現示を知らせて、5秒以内に確認ボタンが押されないと非常制動を掛ける」R現示警報にタイマー停止を付けただけのもので、速度照査も位置照査もなく、一瞬ブレーキハンドルを操作している間に確認ボタンさえ押せば最大速度でR現示に突入できる到底ATSとは呼べないものだが、この方式の欠陥ATSが'66/04全国に設置された。制御に当たっての管理値は敢えて言えば「現示管理」である。制動点が決められない。
国鉄型ATSについての各社報道は、88年12月中央総武東中野事故以来2005年4月福知山線尼崎事故まで一貫して、システムに要求される必然動作「確認扱い=確認ボタン押す操作」を、「ATSを切る」と記す誤報を訂正することなく維持して読者の正しい理解を2020年現在まで妨げている。 大新聞の強烈な権威も有り、Wikipedia流のソース至上主義に毒されていると時に誤謬情報が卓越して真実を掴めない厄介なエアーポケット状態になってしまっている。
JR化後の88/12東中野事故89/04北殿事故を承けた運輸省の行政指導があって、B型は全廃してATS-Pに換装し、 S型(130kHz警報地上子)は出発信号と場内信号:絶対信号だけは信号冒進で非常制動が掛かる機能(123kHz地上子)を付加してATS−SNとし、 さらにJR東海以西各社は過速度防御用に車上時素式速度照査機能(108.5kHz地上子×2)を付加したATS-ST/(−Sx)としたが、 最高速度で冒進可能な構造で、冒進前提の防御は変わらず、警報から実際の制動限界までは30秒前後もあって、それを運転者任せ切りで時にブレーキ扱いが遅れて衝突事故を繰り返した。
また、'68年頃から駅進入番線を直進側と勘違いして高速のまま進入して脱線転覆する事故が重なって国鉄はATS−S装置を流用し列車検出コイルと地上タイマーを組み合わせて分岐器過速度警報装置を開発、制限速度55km/h以下の分岐に設置した。
これに対し私鉄ATSは翌年1月の1967/01私鉄ATS通達で常時自動投入、3段階速度照査、赤信号R現示直近照査速度20km/hに規制している。 制御は「速度管理」。国鉄型ATSとの決定的な違いは信号冒進速度が20km/h以下に規制されていることで、衝突エネルギー(=停止制動距離、信号冒進距離)が国鉄型ATSの1/36〜1/42に抑えられることである。
この運輸省通達内容は結果的に前年4月に全国配備の国鉄ATS-S(-A/-B/-C)システムを監督庁が真っ向から批判したものとなっている。 この「私鉄ATS機能通達」を取りまとめたのは国鉄から運輸省への出向者で後の国鉄電気工作局長となった石原某氏とされ、1966年全国整備の国鉄型ATSの欠陥を埋める内容で翌1967年初に発令された。 後に出向解除で電気工作局長に就任しても私鉄ATS通達は省みられず、ブレーキハンドル連動常時投入化などの若干の改良以外は欠陥国鉄型ATSの換装は出来なかったほど国鉄は頑迷固陋の支配下にあった。
私鉄ATS通達は、実施以降故障時誤扱い以外は大事故は起こっていない優れた通達であるが、国鉄分割民営化1987年4月前夜付けで事実上廃止されて民営化JRに国鉄型欠陥ATSはそのまま残された。 その結果88年12月東中野事故、89年4月北殿事故、本線上ATS常時投入違反の97年10月大月事故と繰り返された。 また過速度ATSについては各事業者に任され'05/04/25の尼崎事故後の過速度ATS義務化通達まで放置された。
ATCは、連続速度照査と制限速度以下での自動緩解と、基本的に線路条件制限総てが設定されていて、連続制御の採用でどの位置でも停止命令を伝えられるものを言うが、ATSとの区別は重複領域があり各社の名乗りが絡み、後付で省令として定義された。 だが速度制限については総ては設定されていなかったし、新幹線ATCでは確認扱いを残していて微妙な領域がある2分類である。欧州基準のATPの方が機能区分が多い。
衝突防止に最も優れた管理値は先行列車に対する「位置」であり、その代用特性として閉塞位置を使ったATS−Pに導入され、その優秀な実績でD−ATC/DS−ATCに取り入れられ、また山手貨物と東京トンネルのATC区間がATS−Pに置き換えられた。(詳細はここ:「停止位置基準速度照査方式」はなぜ優れているか! を参照)
ATS−Sxへの25km/h速度照査導入(=赤信号突入速度制限)は比較的安価に実現可能な方法があるが、'87/04国鉄民営化時にアベコベに私鉄ATS通達の方を廃止して存続させ事故を繰り返している。東京大阪近郊新潟仙台などATCやATS-P/-Ps採用の一部区間、全線ATS-PT換装のJR東海を除いてJRは総て欠陥ATS−Sxである。
以下、ATS・ATCの概要について簡単に説明する。
【 車内警報装置 】
1956/10/15 参宮線六軒駅衝突事故を機に重要線区に車内警報装置設置決定。 その機能は、停止現示を警報して、運転士に確認操作=確認ボタン押しを求めるだけ。1941年9月山陽線網干駅急行追突事故を承けて設置途中で米占領軍命令で放棄した鉄道省型多段速度照査式ATSは、技術水準にまだ問題もあった模様で、この時、省みられることはなかった。
[A型車内警報装置]
1300Hz搬送波信号電流を商用周波数信号電流に重畳して連続誘導式とした,車上信号化前提の方式.
東海道山陽など主幹線用に1960〜使用.1970年、ATS−S型に統合し廃止。
[B型車内警報装置]
左右レールに流れる信号電流を車上で検出して,無信号でR現示(赤信号)を警報する.
地上側はR現示時の信号電流の増加を監視し,列車が警報地点まで来ると一瞬(1秒間)信号電流を断って車上にR現示を伝える.前方信号機器からインピーダンスボンド(=信号電流用トランス)を介して左右レールに供給される信号電流を自車の車軸が短絡して閉回路を構成する(1巻きのコイルを構成する)ので,これを「軌道回路」と呼ぶ.A型車警も同じく「軌道回路式」でR現示情報を伝送.
車上のコイルでこの短絡電流を検出し,B型は信号電流ゼロを以てR現示を検出.
送出側は短絡電流値で列車までの距離を知り,列車が規定の位置に来たら信号電流を瞬断(1秒)してR現示を知らせる.
信号電流は常時流れるので突発のR現示にも応答し,東京大阪の国電区間に用いられた.また,都営浅草線−京成−京浜急行の速度照査式ATS=1号型(0.8〜3秒断)の原型である.
B型の難点は車輪踏面とレールの接触抵抗が不安定のため警報位置の調整が難しいこと.特にS型の直下地上子に相当する動作は軌道コイルによる添線式軌道回路で打ち消すなど構成にやや難があって,東中野衝突事故(88/12/05)後の対策として運輸省の行政指導も有り1991〜2頃に関西国電区間も含めて総てATS−Pに換装された.
'50/ 開発.'54/ 京浜東北&山手で,'57/〜中央総武&大阪電車区間で使用開始.'88年東中野事故を機にATS-Pに換装し廃止。
[C型/S型車内警報装置]
地上子との電磁結合で車上の発振周波数(105kHz)を車上子コイルと地上子コイルの電磁結合を介して地上子の共振周波数(130kHz)まで高くして信号現示を伝える,現S型ATSの方式で地上子の共振周波数検知方式名を取って「変周式」と呼ぶ. 近年、JR西日本が「非変周式」と呼ぶFFT方式の共振周波数検出方式を開発、実用化したため、「LC共振地上子方式」と呼ぶ方が自然になった。準幹線用に'61年〜裏日本縦貫線(青森−米原)使用.'63/トランシスタ化してS型となる.機能としては−C=−S.
【 ATS装置 】 | ATS−A,−B,−S型 ATS−A,B,C=S, Sn=SN -ST=SW=SS=SK≒SF: Sx, P, PF, Ps, L, SP |  ATS・ATC |
この国鉄型ATS全般に言えるのは、前述の通り、実質が、停止信号警報に対するEB装置・デッドマン装置、=信号と運転士間の責任分界確認装置であり、停止現示で自動停止させるATSではないこと。
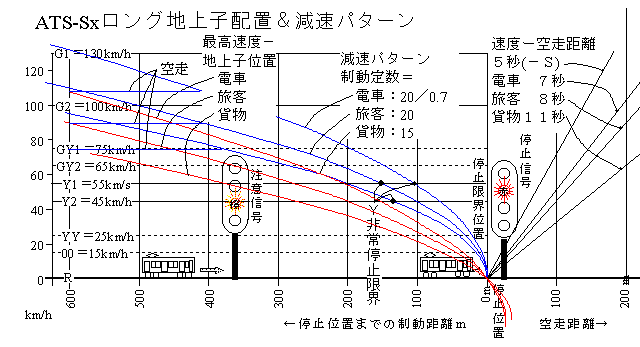
実質EB装置でしか無い国鉄型ATSでの日常的安全確保のため、運転規則では確認扱い後、一旦停止と、再発車後に25km/h以下で停止現示の信号機手前50mまで進んで停まることを定めていた。
ところが、首都圏の過密区間では列車を捌けなくなることから、一旦停止を省略、さらに高速の橙現示制限45km/h〜55km/h制限で停止信号に接近するのが常態化して、東中野事故の半年くらい前には管理側から、運転規則違反の一旦停止省略勧告通達が出されて東中野事故'88/12に到っている。
新宿駅冒進衝突タンク車炎上事故'67/8/8での停止信号冒進抑止対策として場内信号機にも直下地上子を設置し警報を発する様にしたが,閉塞区間の短い過密線区では地上子を隣の閉塞区間に設置する例も多く,ロング地上子との、とっさの判別は困難だから,'88/12東中野追突事故のように実際にはあまり役立たなかったと思われる.(国鉄のマスコミ発表は非常制動で停めるとして世論を誤誘導して東中野事故に繋がった)
ATS−Sn/SN/旧SF (JR東日本,北海道,貨物)
ATS−ST/−Sx:/SW/SS/SK/SF/Sn' (JR東海/S系の総称)

|
速度照査用車上タイマー(速照時素)は旅客電車用標準0.50秒に対して機関車&ディーゼルカーでは1割近く低速の0.55秒とした.貨物会社搭載ATS−SFも後に速照を搭載したが、基本的にこれに合わせ550mSとした.
またJR九州の振り子式電車搭載のATS-SK受信機は時素を0.45秒に設定して10%高速照査としている.(参照写真:06/2/13記)
これらATS−Sからの改良型を総称してATS−Sx型と呼んでいる.
尚、JR東海に乗り入れるJR東の車両にはATS−Pに加え−Snに換えて上位コンパチの−ST速度照査ボードが増設されており、この車上装置を通称−Sn’と呼んでいる.
経過を省いた現ATS-Sx概説をここ[変周式]、([ATS-SS])に述べる.
尚、ATS-Sn/-Sxでは総合試験車による地上子コイルの車上点検に対応して不動作時も共振させ、その周波数を103kHzとした.また車上の常時発振周波数は-Sn/Sは105kHzだが他の-Sxは103kHzとしている
ATS−P (車上で停止予定点からの速度限界を逆算し制動する方式)
西明石ブルトレ富士脱線大破事故'84/10と天王寺駅事故'82/01を承けて,本格的な位置−速度制御を行うH型ATSを開発,'86/年末に西明石,大阪,京都,草津の4駅,F66の16両に装備して,分岐器過速度防止装置:H型ATSとして運用を開始.これが現行ATS−Pのプロトタイプ(原型)であり信号保安関係はJR各社共通コードで互換性を維持している.
ATS-Pの動作は,R現示での停止予定点(=閉塞絶縁点)を想定して,ここを基準点に各地上子からそこまでの距離と勾配を車上に与え,自列車の標準減速性能と刻々の位置から許容速度を逆算,これに接近すると警報を発し,停止速度限界を越えると強制制動を行う.直通ブレーキ系では緩解の速い常用最大制動が掛かり,自動ブレーキでは非常制動が掛かり,10km/h以下に減速するか,地上子から現示アップを受信するまで緩解しないので、降雪・結氷時の高速運転等特殊条件を除き基準点を超えることはない.
R現示での停止予定点距離は信号現示段階(R,YY,Y,YG,G)により最大5種類与える.停止地上子は各信号毎に4基(閉塞信号)〜7基(場内信号、最大8基)設置して距離情報を与えるので,多重系を構成してATS地上設備の故障をカバーし情報が更新されなければ冒進せず外方の停止予定点までに停止する.
地上子設置位置は、最高速度でも停止可能なT600、直下取消再設定のT30〜T25、電車・気動車がY現示速度で停止可能限界のT180、停止までの間に減速途中パターン取消地上子T85設置が基本で、T180までに現示アップされるとブレーキ操作の必要がない。この4基に加えて低減速車のY現示速度停止可能限界としてT280などが条件により追加され実質連続制御化する。場内信号では更にT130、T50、T280が追加され直下地上子はT25で停止信号時に即時停止コマンドを発する。
速度制限の場合は制限開始点までの(放物線)パターンを刻々算出して減速し,制限+余裕速度以下になれば緩解できる.従って無駄な徐行区間や冒進のない適切な制御が行われる.
ATS−PT
JR東海が全線に設置したATS-Pで、保安コードは協議決定により7社共通である。福知山線尼崎事故2005/4/25を経て、JR西特認コードだった「本則『+α』」をJR東も採用、ATS-PTで増設の、路線の最高速度、無閉塞運転区間長も7社共通コードと合意された。
ATS−PF
貨物仕様ATS-P:車上装置.原理的には旅客用Pとの違いは無いが,ATS-Pのコードに貨物用速度制限の割当がなく、貨物の様々な種別に全く対応出来ないため合成音声で旅客の制限速度を読み上げる機能があるとか,一般貨物ではブレーキを強める方向の操作しかできないことから等加速度前提の旅客用ATS-Pとは制動曲線が合わないなどでパラメター設定だけでは解決出来ず、機能としても貨物用のATS-Pが必要である。先頭の取消地上子の最適位置が電車よりかなり手前なので、現示アップ後も減速を要求されやすい等の相違が出るが,詳細は不明.
ATS−Ps
ATS−Sxの上位互換で,多変周型ATSとしてATS−Pと同様のパターン型速度照査機能を持つ.地上子位置と間隔で勾配補正や速度制限を行う.
制動パターンは2段階で、−ST過走防止装置が高速時を放置しY現示速度以下しか防御しないのに対し,最高速度から防御して危険なエラーをフォローしている.地上子非動作の103kHzで取り消しとなる廉価版で,亜幹線用として新潟近郊,仙台近郊に設置された.
ATC−L/(ATC-1F型) <ATC-L>
'88/03/13 運転開始青函トンネル(津軽海峡線)の,高湿度で霧の発生しやすいトンネル区間向きの車上信号式ATSとして開発,装置としては新幹線ATCの構造に準じたもので,自動ブレーキ搭載の機関車ED79に対して予告信号を現示,次閉塞に突入する前に手動操作で減速を完了させるATSが採用された.減速未完了のまま次閉塞に突入すると常用制動で停止する.直通ブレーキの電車はATCとして運行している.車上信号式ATSは認めないという運輸省令でクレームが付けられて現在ATC−L型と呼ばれているが、機関車が自動ブレーキであり込め不足を起こす状態でのATCはあり得ず機能としては国鉄JR命名の通りATSである.交流運転電流のノイズに強い電源同期式SSBで1搬送波2信号波組合せ方式を採用.周波数割当は新幹線ATC-1Dの副信号波から2波を組み合わせて速度信号にしているが、そのコードに新幹線との共通性は見られない.コードが違えば全く別物だし、元々盛岡以北はDS-ATCでこれとも一致しない.だから在来線初の交流電化区間のATCとしては新幹線で実績の厚い方式として採用されたのだろうが、「新幹線との共用」を言うなら、相互に閉塞長まで変えての時間差「排他的共用」しか考えられない.だから「青函ATCは新幹線ATCとは互換性がない」が正しい.自動ブレーキではATCで自動緩解するとブレーキエアの込め不足を起こし,安定した自動回復が困難なので,汎用には手動のATSしか使えないしブレーキ操作の制限を生ずるから装置としてはATCでもコード仕様は明らかにATSだ.
#次区間予告現示が特徴:110,Y110,45,R45,0,R0,02E
ATS−SP
鉄道総研が試作提唱したATS−Sxの上位互換で,不採用のママ廃棄されたもの.ロング地上子でATS−Pと同様のパターン型速度照査を行い,軌道電流の転極でパターン解除をする構成だが,信号電流は絶縁破壊のフェイル・セーフのため閉塞区間毎に極性を変えて居り,閉塞区間外設置の地上子で作られたパターンは閉塞区間が変わると消去される可能性があるため、輸送量の多い短小閉塞区間がある線区に使えず嫌われたり,車載の位置情報のメンテなどに問題があったようで,一部で話題にはなったが結局採用されなかったが、−Sx地上子をマーカーとする車上データベース方式は後日制御式振り子システムに採用され、その実績からD−ATC/DS−ATCに採用された.
ATS−X
鉄道総研が試作したATS-Sロング地上子内にトランスポンダを組込んでケーブルを兼用する地上子を使って現示毎の停止点までの距離を車上に伝え、現示アップ情報を軌道回路から伝えようとするものである。車両側からみての互換性はない。 ATS-Pと比較して流用するロングケーブル分のコストダウンは図れるが、パターン取り消し法(停止位置距離更新法)を地上子から軌道回路に換えて果たしてどれ程の削減効果があるか、JR東西P区間への相互乗り入れでP,X双方の受信機を積んでも採用する利点があるかどうかを考えると、独立設置ならほぼ同格としても、先に普及してJR各社共通コードとなっている現ATS-Pを無視してまでの採用は何処も二の足を踏むのではないか。 現ATS-Pの供用20周年低原価再設計プロジェクトの方が現実的で、鉄道総研開発品はSTに続きまたもお蔵入りの憂き目をみるのではないだろうか。全く独立の鉄道に導入するのは可だから、台湾、韓国の大都市近郊など日本型過密ダイヤの鉄道に導入するには適している。06/06/25追記項
ATS用語メモ
06/07/01追記
<ATS_Words>
3位式自動信号結線例 See→[用語説明補足] |
【 ATC 】
ATC(自動列車制御)とは,営団日比谷線(1961年)と新幹線('64年)でATC(Automatic Train Control)という名乗りで運行が始まって,その定義が後追いになっているので(法定を除き)絶対的なものは存在しない様だが,共通要件としては,しかしながら,3項目は,現在,在来線の臨時速度制限がシステムには設定されず,また新幹線も東京近郊の中間的速度制限が運転者任せだから,設備運用の問題ではあるが厳密にはATCの要件を満たしていない.新幹線30km/h現示も自動緩解ではなく確認扱いが必要だから,一律定義ではない.ATSとして開業した津軽海峡線青函トンネルを「車上信号のATSは省令上認められない」とかいって「ATC」を名乗らせたのはナンセンス。込め不足問題を抱える自動ブレーキ車にATC設置こそ誤解の基で却って困る。ハードとしてはATCのそれを取り入れながら、自動ブレーキ車である機関車列車に付きものの「込め不足」の懸念からATSを名乗った当初のJR側の判断の方が運輸省の言い分(省令:法定)より妥当である。
以下、断片的だがATC地上装置の解説として,記しておく.国鉄のATC車上装置は固有名称の他1〜6型と番号が付けられ線区に跨って運行するものもありうるし、改造部は同一型名に飲み込むので、入り組む部分が出来、設置車両基準ではスッキリするが、具体的な動作の絡む構造解説には適していない。
営団日比谷線・東西線:<WS-ATC>
「AF−FS」:搬送波がAFで、その変調方式がFS.
「AF」:Audio Frequencyとは,可聴周波数だが,鉄道信号の場合商用電源周波数(50/60Hz)以外の周波数を指している.ATC信号の搬送波にAFを用いる.
「FS」:Frequency Shiftとは,必ずしも明確な概念ではないようだが,(副)搬送波を変調するに際して,デジタルの0/1に対応して(副)搬送波の極性を反転させる変調方式を FSと呼んでいる例が多い.初の火星探査機マリナー4号の画像変調方式だった.副搬送波15周期で1ビットを送信.初の火星表面写真だったが写真1枚の送信に数時間を要した.
「FS」というのはデジタル信号1ビットの伝え方の問題の様で、敢えて分類すれば、±90°の位相変調といったところ.これがなぜ「FS」と呼ばれるのか釈然としないのだ.
搬送波を変調する方式としては
振幅変調(AM,DSB,SSB),周波数変調(FM),位相変調(PM)がある.
変調波に(1/周波数)の重み付けをして位相変調すると、周波数変調に等価になるので安定した周波数が簡易に必要な場合に利用された.狭帯域FMは側波の位相がAMとは90度違うだけで周波数成分は同じである.
PWM,PAM,PFM,PCMはパルス波を搬送波として信号を載せる方式で、更にそれでマイクロ波を搬送波として変調し通信に使ったもの.
☆PCM:パルス符号変調はA-D(アナログ−デジタル)変換結果を1ビットづつ順次伝送するもの.
☆PWM:パルス幅変調はパルス幅で信号波を送る方式.VVVFで多く用いられたDC−AC変換の基本技術.
 |
 |
|---|
☆PAM:パルス振幅変調はパルス振幅で信号波を送る方式.
☆AF−AM:搬送波がAF:商用交流電源以外の周波数で、その変調方式がAM:振幅変調.千代田線・常磐線('69年開業)ATCに採用.振幅変調と云っても実態は、搬送波を信号波周波数でon-offしている状態.テキスト「鉄道信号一般」P91に「DSB」とあるが、搬送波も送る純AM=広義のDSBであり、決して抑圧搬送波方式ではない.(波形図参照)
東海道新幹線:JNR-ATCの祖 <JNR-ATC>
(ATC-1A東海道,-1B/-1W山陽,-1D全国共通2搬送波式:2搬送波方式に改造、速度値は線区毎に決められた分は東西を統一できなかったが、基本コードは同じで国鉄JRアナログ式ATCの標準構造になっている)
電源同期SSB1波方式(1A型〜):01,02,03,30,70,110,160,210km/h の速度信号ランクで1964/10営業開始し、後の2周波化改造では基準の制動性能向上で110→120km/h,160→170km/h,210→240km/hと改め、更に各線毎の高速度信号などを加えて電源同期SSB2搬送波2信号方式(1D型〜):01,02,02E,03,30,70,120,170,240km/h,270,285,300km/hなどとなり、現在デジタルATCへの換装工事が進められている。 営団地下鉄日比谷線(1961年〜)に次ぐ日本で2番目のATC.30km/h〜210km/h信号波が軌道回路(左右のレール)に送出されて車上子で検出される.信号波が閉塞区間入口の地上装置で検出されなければ列車在線、検出されば不在線として自動信号系を構成する.
01:先行列車が在線する閉塞の手前に停止させるために、軌道回路から30km/h信号を受けながら制動距離+余裕だけ手前の「P点」と呼ばれる地上子から停止信号を受けた状態.現示アップでクリアされる.P点は各閉塞毎にあるが30km/h現示にのみ有効.
02:先行列車在線閉塞区間突入の無信号状態.故障、停電、誤コードなど.
02E:上記状態で、雑音に依る誤動作を防ぐため軌道回路に送る停止信号.-1D型改造で導入。
03:絶対停止の添線軌道回路からの信号:誤出発・過走防止装置.
1974年の品川信号事故&新大阪誤現示事故を経て速度向上改造と併せ(2搬送波式:-1D型)2信号波組合せ方式&03無変調波を変調波に上位互換で改良している.現在は更に東北新幹線盛岡以北のDS-ATC同様ATS-P照査方式の位置情報から制限速度パターンを生成する方式への換装工事が行われている.従前ATCとの互換性は論議されたが独自の方法となった。
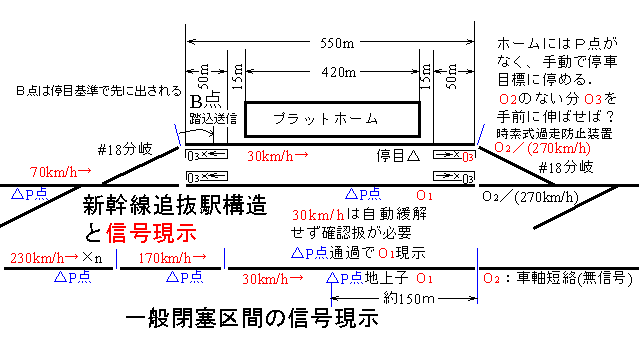
B点:ホームに差し掛かると30km/h現示に落とす点.近年線路容量増加・高速化のため踏み込み送信により閉塞境界より先の停止パターンギリギリに設定し直して時隔を詰めている.
SSB方式:単側波方式. <SSB>
信号波成分だけ送信し,搬送波を送信しないので、単純な振幅変調方式に較べて信号波を6倍以上(会話なら50倍!)の電力で送れるため、現在AM通信の主流になっている.
電源同期方式: 送受信とも電源周波数を基準に搬送波を作成して、信号波を送信する方式.交流電化の場合、運転電流の高調波が極めて強力で信号波をこれと常に分離するためと、SSB方式は受信側で搬送波成分を加えるので、周波数の正確な一致が求められる.そこで共通電源の周波数を基準に採って逓倍し一致を図る方式=電源交流を歪ませて高調波を取り出す方式が採用された.歪み方式は高倍率になるほど効率が悪いので、発振周波数をカウンターなどで分周してそれを基準周波数信号と比較して発振周波数を調整するPLL(=Phase Locked Loop)方式が有利になる.
振幅変調方式 : 伝えたい信号波で振幅変調を行うと、搬送波周波数の両側の信号波周波数だけ上下の周波数に,それぞれの振幅が最大で搬送波の1/2の「側波」と呼ばれる信号波が現れる.情報を伝えるには側波だけあれば良い.(正弦波の積を和に分解すれば簡単に判明)
(直流電化区間ATCに採用∵基準となる交流電源が車上には来ない),

| 装置型名 | 方式 | 電 化 | 設置線区 | 供用 | 廃止 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地上 | 車上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1A | 1 60Hz | 1信号波 1搬送波 | 電源同期SSB | 交流電化区間 | 新幹線 | 東海道 | 64/10/01 | ●1D→ATS-NS
| 1B | 山陽 | 72/03/15
| ●→1W
| 1D | 2信号波 | 2搬送波 東海道 |
| ●→ATC-NS
| 1W | 山陽 |
| 1D | 2 | 50Hz (60) 東北 | 上越 長野 82/06/23 | 82/11/15 97/10/01 Δ→DS-ATC | 全国標準型
| 1F | L | 2信号波 | 1搬送波 在来線
| 青函(新 | 在共用部) 88/03/
| ●在来線コード | のみ→DS-ATC
| − | 3 | 1信号波 | 1搬送波 BSB
| 直流電化
| 東西線 | 69/03/
| ●→CS-ATC
| 1J | 4 | 常磐地下
| 71/04/
| ●→新1J?
| 1C | 5 | 東京隧道 | 72/
| ●→ATS-P
| 1E | 6 | 山手 | 京浜東北 81/
| ●→D-ATC | Δ 埼京赤羽 | 86/ | ●→ATACS
| 1J? | 4? | 2信号波 | 1搬送波 常磐地下 | 00/07/ |
|
●パイロット信号の得られる交流電化では電源同期SSB方式 | 基準のない直流電化でAM/BSB方式(キャリア断続方式)を採用 ●地下鉄東西線は営団の地上設備のため国鉄JRには車上装置3型のみ | ||||||||||||||||||||||
【 デジタルATC 】 D-ATC,DS-ATC,KS-ATC=ATC-NS <D-ATC>
デジタルATC区間
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
デジタルATC方式最大の特徴は,地点基準の制限速度を車上で算出して速度照査を行う「ATS-P方式速度照査」(パターン方式)を採用して無駄な徐行距離を無くし列車間隔を詰められる様にして輸送容量を増やしたことである.これが各線ATC更新改良の動機となっている.
信号の遣り取りに従前の信号周波数ではなくデジタル方式を中心に用いたことで「デジタルATC」と呼ぶが,それは動作の基本原理に関わるものではない.
次いで線路条件データベースを車両側に持って,位置など索引情報から限界速度を得ることで地上側設備の簡略化を図っている.この車上データベース方式は地点機器と1対1の関係ではないので安全装置の構成としては議論を生ずる処である.最初に車上データベース方式を提唱した鉄道総研開発のATS-SPはどこも採用しなかったが,ATS-Sx地上子位置を読みとり車上データベースと照合して振り子を制御する方式の採用実績を経てATC系に採用されることとなった.
パターンは表で持つJR東日本方式と逐次演算の東海方式があるが原理的な差はない.JR東海方式が最大演算時間を読み誤った模様で予期せぬ非常制動が掛かり06/04〜/05に車上ソフトを改修換装している.
(06/05/21追記)
通達 「自動列車停止装置の設置について」
昭和42年鉄運第11号 (1967/01)
自動列車停止装置の構造基準自動列車停止装置の設置基準に該当する区間に設置する自動列車停止装置の構造は、次によらなければならない。
- 場内信号機、出発信号機、閉塞信号機が停止信号を現示している場合、
重複式の信号制御区間の終端、 重複式でない信号制御方式では信号機の防護区域の始端までに列車を停止させるものとする。 - 速度照査機構をそなえ、速度照査地点を照査速度を超えて列車が進行する場合、自動的に制動装置が動作するものとする。
- 照査速度は線区の特性に応じて多段階とし、列車最高速度が100km/h以上の区間は3段階以上、100km/h未満の区間では2段階以上を標準とする。
- 停止信号を現示している信号機に最も近い地点における照査速度は20km/h以下とする。
- 車上設備の機能が正常であることを運転台に表示する。
- 地上設備設置区間を運行する場合は、列車は車上設備を開放して運転できないものとする。
ATS・ATC改訂版(日本鉄道電気技術協会'01/07刊 tel 03-3861-8678)3ページより
通達実施以降、故障時・誤操作を除いては大事故には至っていない。
この運輸省通達は国鉄分割民営化(1987/04)前に廃止されている。そのため欠陥ATSであるATS-B/-Sが存続して、東中野駅追突(88/12)など防げたはずの衝突事故を起こしている。
[地上設備別ATC分類]
[新幹線ATC] (総て交流電化区間)
[在来線ATC] (津軽海峡線のみ交流電化区間.他は直流区間)
ATS-P同様の停止位置基準速度照査パターンを算出するATCに換装
| 型名 | 設置路線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 車上 装置 | 地上 設備 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1A | 東海道新幹線(初代1964/10/01〜) | 1B | 山陽新幹線(初代72/03/15〜) | 1D | 東海道山陽新幹線:2周波改良全国標準型 | 1W | 山陽新幹線 |
| 1D | 東北上越新幹線(初代82/06/23〜/11/15〜)新幹線全国標準型、長野97/10/01開業〜
| 1J | 常磐線(千代田線乗入れ1971/〜) | −− | 地下鉄東西線内WS-ATC乗入れ型(69/03全通) | 1C | 横須賀総武線(東京トンネル内72年開通:地上設備は2004に廃止) | 1E | 山手京浜東北根岸赤羽線(1981〜) | 1F | ATC-L 青函トンネルATC(88/03〜)
| ?? | 常磐線(2000年07月〜) | ?? | DS-ATC用('02/12/01〜) | ?? | D-ATC用('03/12/21〜) | ?? | KS-ATC九州新幹線(04/03/13八代以南開業.ATC-NSとコンパチ) | ?? | ATC-NS東海道新幹線換装(06/03/18)山陽換装中 | | ||||||||||||||||
【 私鉄のATS・ATC 】
○ 東武鉄道ATS=TSP ○ 京王ATS ○ 小田急ATS ○ 都営浅草線/京成電鉄/京浜急行ATS ○ 京浜急行ATS ○ 日比谷線東西線ATC
|
mail to:
| 
| 
| 
| 
|
| Last Upload:
Last Update: 07/03/25 ('7/3/04,'6/6/25,'4/3/09,'3/12/22,'1/11/6♪up56-57等に加筆) | ||||
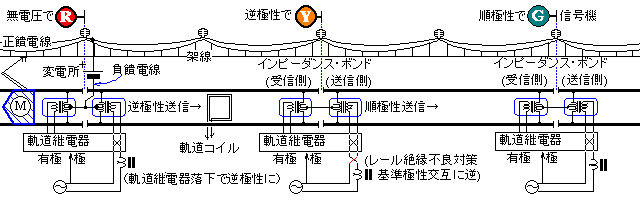 「軌道コイル」は、車軸による短絡電流の有無を検出することで閉塞区間中の軌道コイル位置より先に列車が居るかどうかを検出するもの。新幹線の駅進出判定に列車後方側から用いられて分岐転換時期を早めている。
「軌道コイル」は、車軸による短絡電流の有無を検出することで閉塞区間中の軌道コイル位置より先に列車が居るかどうかを検出するもの。新幹線の駅進出判定に列車後方側から用いられて分岐転換時期を早めている。