(旧版)
|
|---|
新幹線の時素速照式
過走防止装置
「新幹線鹿児島中央駅の過走余裕(停止目標−車止め間)が約30mと不足で、それを補うために時素式速度照査5段による過走防止装置が設置されている」という情報があった.これを「九州新幹線は位置基準限界速度パターン式ATCであるKS-ATC=NS-ATCで防御しているので無用な設備のはず」と思い設置理由に注目していところ,それは事故時にパターンが消去された際のバックアップで,東京駅など従前の東海道新幹線の過走余裕不足駅にも同様の時素速照式過走防止装置を設置していることが判明した.see BBS→過走余裕距離の標準値は,下図に示す03信号ループ長50m,余裕+15mであり,東京駅も#14〜#15番線は過走余裕60mで基準値は満たされているが,同駅#16〜#19番線や鹿児島中央駅は30mの過走余裕しかないため,過走防止装置が設置されている.行き止まり駅での過走余裕距離不足は新幹線東京駅開業当時からあった模様で,鹿児島中央駅に限ったことではなかった.
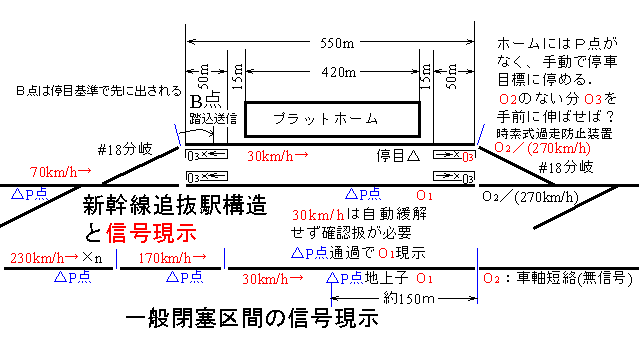
 07/12/22 東京駅#16
| 
|
03コイル長は,信号設置の電車用標準的定数を元にATCの30km/h制限から,非常停止して空走2秒,制動定数20/0.7で停止するのに必要な距離48.167m=30/3.6×2+302/(20/0.7)として定められた様だが,鳥飼電車基地出口でこれを突破して加速し本線ポイントを割り込む事故になったことで以降上図の様に50mに改められたものである.
停止目標から車止めまで30mで約60mに不足するのが東京駅#16〜#19番線と鹿児島中央駅で,残る最小30m分は時素式速照で止めていることになる.
すなわち,非常制動が掛かるのは停目手前30mセンサーに停止可能な速度以上で突入すると03コイルに電流を流して非常停止させる.支障限界から先は常時通電で非常停止で良いが,停止目標のやや先から支障限界までは過走が明らかなので踏み込み送信で停止させるが,停車位置を直すので時素で解除する.都合3種の区間ができる.
センサーは車軸検出器2個を1.25m間隔に配置したものを5m間隔で5組設置.
その先の停止目標先に過走領域踏み込み検出として1基設置.
従って減速照査段としては,突入速度30km/hから15km/hの間を5段階分割で,その先は停止目標を超えて非常制動として,照査分割は等減速度方式ではなく,等制動距離分割≒5mで構成している.制限値を5km/h単位に丸める在来線方式とは違う様だが,規定の分解能は不明.(xkm/h規定か?xms規定か?)
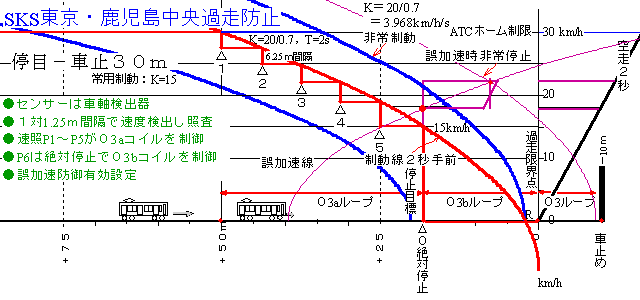
上図は,新幹線の停止目標から車止めまで30mという条件で過走防止装置を設置した例である.
一旦停止後に加速したまま突入されると06/04/21の京王井の頭線吉祥寺駅過走事故のように防御しきれない虞はあるので,K=15(=2.08333km/h/s=0.5787m/s2≒新幹線低速時の最大加速度/常用減速度)での加速でP5を15km/hですり抜けた場合の非常停止曲線を描いてみたが,流石新幹線!車止め直前にちゃんと停まれる!
在来線では,最高速度で冒進可能な重大欠陥のあるATS-Sxを,私鉄ATS通達を廃止させてまで擁護して存続させ,更に「国鉄ATSの安全度は私鉄ATS仕様と変わらない」という虚偽答弁('06/05国交相答弁)で存続を図っているが,新幹線の2重3重の安全装置というのは全く別世界である!経済的負担力が大きいのは確かだが,在来線とは独立の組織として発足させて超高速鉄道に適した安全基準を貫いて経験主義的な在来線の悪影響を断ったのだろう.事故時をバックアップする安全装置まで完備だったとは予想外だった!新幹線は在来線とはまるで格が違う!
|
信号・標識・保安設備について語るスレ6 http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/train/1137513600/750n 750 名前:名無しでGO![sage] 投稿日:2006/05/15(月) 18:31:01 ID:PisVxbL0O >>749 03吹きっぱなしで終端防護してたのは東京駅14、15番線だった。 停止目標から車止めまで60mあった。 東京駅16〜19番線とか鹿児島中央は停止目標から車止めまで30mしかないから速照03だけど、鹿児島中央の資料を見たら速照で面倒見るのって25→15km/hまでなんだね。 停車は運転士の操作が基本で、停止目標を越えると03で非常。 停止限界でループが区切ってあるのは何だろ。 http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/train/1137513600/797n 797 名前:名無しでGO![sage] 投稿日:2006/05/24(水) 01:09:27 ID:LxAZqsJY0 >>788 速照の方法がまったく書かれてないので何とも言えないけど。 速照03は基本的に2対の車軸検知子を使って速度を計測する。 東京や鹿児島中央の現方式は大雑把に描くと下記のような感じ。
http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/train/1137513600/813n-816 813 名前:名無しでGO![sage] 投稿日:2006/05/25(木) 06:52:58 ID:xJq0WKLVO >>807 ちなみに03ループの長さは、詰めてるところでループA:22m、ループB・Cがそれぞれ14mずつくらいね。 816 名前:名無しでGO![sage] 投稿日:2006/05/25(木) 15:59:51 ID:xJq0WKLVO <P2> >>807(パターンATCでも時素式過走防止装置設置の理由) ATCをリセットするとパターンが消える。
|
|
mail to:
|

|

|

| ||
| Last Upload: : Last Update: 2006/05/31 (05/02/04) | |||||
