ATS-P地上子位置の分析
【 概要 】ATS−Pがどのような設定になっているかを、ATSテキストの数値などから整理推定してみます。ポイントは、標準減速パタ−ンの制動指令遅れ時間分手前のパターンとY現示速度と交点に取消地上子を置くことが基本になります。(下図が推定結果)
現ATS−Pの設定を子細に見ますと、通勤電車に特化して効率の良い制御をする様設計・試作されたものを、そのまま、旅客と貨物にも適用した様に思えます。
【 電車のATS-P設定 】制動遅れ0.5秒、Vy=55km/h 車上子取付位置=14m(JR西式)
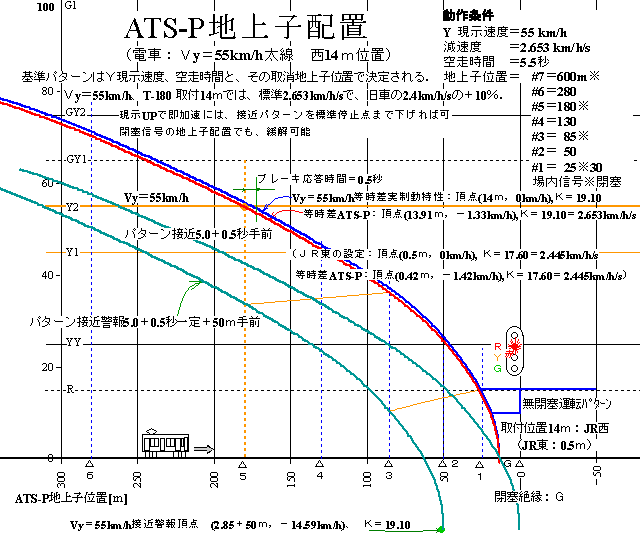
経過を振り返れば'84/10/18の西明石駅でのブルトレ過速脱線大破事故を機に'86年末にATS−Pの原型であるH−ATSが開発完了、60km/h以上の分岐器過速度防止装置として西明石など4駅に配備され、'88/12/01新木場まで開業の京葉線で蘇我までの間、初めて全線ATS−Pとして運用開始しましたが、その直後の12/05に東中野駅追突事故発生!その対応策として「ATS−P換装」前倒しとなりました。
今にして思えば、ATS−P換装が急遽東中野事故の緊急対応とされたため、京葉線電車用設定のままで実運用による最適修正期間を採れないで広範に設置されて、微妙な不具合で現場の不評を買っているのではないかと思いました。例えば、車上子を後方に取り付けたP搭載車は出発時に制動パターンに当たりやすくPモニターが要り、またブレーキ圧の増圧改造が特に必要とか、取消地上子の位置が電車用で、列車や貨物にはマッチしてないとか……。ブレーキ増圧は結果として高速化に効果があるのですが、103系など滑走防止装置のない旧車では滑走し易くなりタイヤ・フラットを嫌うメンテからは不評でしょう。
- [整理&若干の疑問・不明点]
-
パターン接近警報の設定基準不明
制動パターンが安全基準であれば、接近警報パターンは
a).定時間(ex.5秒)手前.(現示アップ即加速不可)
b).定速度(ex.15km/h)低速.(現示アップ即加速困難)
c).独自に運転支援として、50m手前停車の制動指令パターン5秒手前で警報
(R現示出発問題がなくなり、現示アップ即加速可)
- 車上子取付位置補正は
・各車両毎に実値で設定されるのか(0.5m〜14m)?代表値10mで固定か?
・演算は先頭車連結器先端位置に換算。車上子取付位置を補正と思われる.
(テキストには10m固定の表現がある.
本来は先端位置基準が妥当.諸演算が一貫する.作図はJR西位置14m) -
現示アップで即加速可能か?(場内信号用地上子配置で:ATSテキストに明記).
動作余裕5秒一定方式のパターン接近警報(作図緑線上)では、
・T-180地上子先以降、T-50までは緩解可能だが、 地上子を通過するまで加速できない.
(速度に依らない、ATS−Sx速照の設定法.警報余裕時間5秒、応答時間0.5秒一定)
・一定速度低い接近警報方式で余裕を大きく採れば、現示アップで即緩解可能だが、
速度に依って接近警報から制動までの動作時間が変わるし、パターンが下がる.
そんな特性を特別の根拠無く許容するか??
・動作余裕5秒一定方式のパターン接近位置の、標準停止位置50m分手前に警報パターンを設定すると、問題解消。操作の整合性も良好。(大きい減速度が採れない他は)動作に無駄はない。(作図緑線下)
-
基準の取消地上子はT-180と推定.
∵閉塞信号の地上子配置と場内と共通の位置で、電車としては若干強めの妥当な値.
地上子位置、車上子取付位置とY現示速度から算出すると、2.4〜3.0km/h/sを要求され、101系103系の標準減速度=約2.4km/h/sを超えることがあるので、その場合ブレーキ増力措置が必要になるだろう.T-280は場内信号用位置だから閉塞信号と共通の先頭取消地上子ではない。
- 信号(停止)コマンドの場合、
- 車両の最高速度設定がある場合 (こちらが実際と思われる)
「パターン発生」とは、算出限界速度が設定最高速度より低い状態
「パターン消去」とは、算出限界速度が設定最高速度より高い状態
- 最高速度設定がない場合 (強い一説。だが、パターン発生/消去の意味がなくなる)
「パターン発生」とは、警報速度を超過したことを記憶している状態
「パターン消去」とは、現示アップにより
次の地上子から新たな停止位置距離を受け取り、それで
接近警報速度が走行速度より高くなって前項の速度超過記憶が消去されること.
- 車両の最高速度設定がある場合 (こちらが実際と思われる)
-
前区間の地上子が最外方600m地上子等を兼ね、省略される場合も多い.
位置情報送信機能でみれば、停止地上子に、パターン発生、取消、直下の区別はない.
600mは最高速度での非常制動距離.ATS−Pは常用制動が基本だからT-600では停まりきれず、必然的に前(前々)閉塞区間の地上子から停止位置距離を得ている.総て同格! - 信号(閉塞)位置基準で手前に制動指令&接近警報パターンを生成
- 停止信号パターンの場合、制動パターンと警報パターンの速度差が大きくても、最終的な停止点が若干手前になるだけで、悪影響はない.
-
JR西日本の車両がATS−Pモニターを搭載している理由は、パターンに当たりやすいからと推察するが、その原因は、車上子取付位置が約14m位置と後にあって、その分、取消再設定が遅れる.
(西明石など分岐器過速度制限が主のH−ATSから始まり、東は京葉線電車による停止が主の試験データから始まった経過が影響か?)
-
速度制限コマンドでは、警報速度超過が記憶されず
速度制限以下になれば「パターン消去」となる. - 速度制限パターンの実設定値は平均速度に大きく影響する.だから、その制限値は+5km/hに採っている.
- 減速度の若干小さい車両は、Y現示速度を45km/h等に下げれば対応可能.
- 貨物など、ブレーキ応答時間の長い列車は、取消地上子位置が合わず、現示アップ下での減速距離が長い.
ATS−P地上子位置の分析
【 分析手順のポイント 】
- T-180地上子はVyと制動指令パターンの交点に設置(貨物は不明)
- 警報パターンと制動パターンは定時間差として算出手順→
制動定数K=…(4)、 →制動パターン函数…(2)、制動指令パターン…(5)"、
警報パターン函数…(5)"50m手前に移動 - 地上子毎の制動パターン速度、制動指令速度、警報パターン速度を算出
- 現示アップ加速度Aを仮定し
- 制動指令速度Vaiに至る、手前の地上子位置の速度Vxi+1を算出する.
- Vxi+1>Vki+1 が、現示アップ時に即時加速可能の条件.…(10)
【 ATS-Pの設定 】 (以下ATS-Pの基本動作として試算)
- 制動曲線は、閉塞端から車上子取付位置手前が速度0、減速定数K(標準的常用制動)の等加速度運動(放物線)
- T-180地上子の設置位置(180m)は、制動指令速度がY現示速度(55km/h、45km/h)の地点
- ブレーキ応答時間は一定.(仮に電車0.5秒、旅客1.5秒、貨物9.5秒とする)[定時間型]
- パターン接近警報からのブレーキ操作余裕時間を5秒とする(ATS-Sxと同値)
- 停止予定点50mからのパターンに接近警報を行う。実制動パターンは安全確保とし、運転支援とは分けて考える。
- 現示アップ直後、「Y現示速度への加速可能」(テキスト「ATS・ATC」)の確認.(上記措置で達成)
| 項目 | 列車種別 | 備考 | ||||||||||||||||||||||
| 電車 | 旅客 | 貨物 | ||||||||||||||||||||||
| 応答時間 | Td= | 0.5| 1.5 | 4.5
| 秒 |
| 操作余裕 | Ta= | 5
| Y現示速度 | Vy= | 55 | 45 | km/h
| Y現示速度地上子 | T-180位置 Ly= 180 | (180 | m | (貨物 | 不詳 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 装置 | 地 上 子 位置 | Vy=55km/h動作型 T=0.5s+5s(電車) 減速度=2.653km/h/s | Vy=45km/h動作型 T=1.5s+5s(列車) 減速度=1.910km/h/s | 備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 制動 パターン | ATS-P ブレーキ パターン | 警告 パターン | 制動 パターン | ATS-P ブレーキ パターン | 警告 パターン | ||||
| [m] | [km/h] | ||||||||
| 信号#0 | 0 | 0 (15) | 0 (15) | 0 | 0 (15) | 0 (15) | 0 | ||
| P地上子 | #1 | 25 | 14.5 | 13.2 | 6.0 | 12.3 | 9.8 | 5.1 | 直下地上子(非常制動) |
| #2 | 50 | 26.2 | 24.9 | 15.4 | 22.3 | 19.6 | 13.1 | ||
| #3 | 85 | 36.8 | 35.5 | 25.0 | 31.2 | 28.5 | 21.2 | ||
| #4 | 130 | 47.1 | 45.8 | 34.7 | 39.9 | 37.2 | 29.4 | ||
| #5 | ※ 180 | 56.3 | 55.0 | 43.6 | 47.8 | 45.0 | 37.0 | △ Y現示速度での制動指令点 | |
| #6 | 280 | 71.3 | 70.0 | 58.2 | 60.5 | 57.7 | 49.3 | ||
| #H | 600 | 105.8 | 104.5 | 92.2 | 89.8 | 87.0 | 78.2 | 通称パターン発生地上子 | |
○ 現示アップ直後のブレーキ緩解可.加速は無理∵警告速度≒次の地上子の指令速度
【 旅客列車のATS-P設定 】 制動遅れ1.5秒、Vy=45km/h 車上子取付位置=14m(JR西式)

[ 想定減速度の算出 ]
| 制動パターン函数Vb= | sqrt(L*K) | ∴ L=Vb^2/K | ……(2) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ly地点では Ly= | Vy^2/K+Vy/3.6*T | (定時間動作型) | ……(3) | ||||
| K= | Vy^2/(Ly−T*Vy/3.6) | ……(4) | |||||
| (3)式の平方を完成 | V^2/K+V/3.6*T−L=0 | ||||||
| = | V^2+K/3.6*T・V+(K/3.6*T/2)^2 | ||||||
| −(K/3.6*T/2)^2−K・L | |||||||
| = | (V+T*K/7.2)^2−{(T*K/7.2)^2+K・L}=0 | ……(5) | |||||
| ∴放物線頂点(Vp,Lp)= | {−T*K/7.2,−K*(T/7.2)^2} | …(5)’ | |||||
| L=0 のときV= | 0 or | ||||||
| V= = | −2(T*K/7.2) 2Vp | 放物線上3点の 位置が決定 | …(5)” | ||||
| 接近警報と制動の特性曲線は | |||||||
| V= | Vp+sqrt{K*(L−Lp)^2} |
頂点を(0,0)→(Vp,Lp) へ移動 ………(6) | |||||
L=L1でV=0 のオフセットを設定してるから、原点移動&スケール変換を行い、
(4)式&(1)より、K、Vp、Lpを求める。 電車、旅客、貨物それぞれの接近警報、制動、実制動について、下表(7)に示す.
この値は(6)に代入して用いればよい.
| K= | Vy^2/(Ly−L1−T*Vy/3.6) | ……(4)' | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ∴放物線頂点 Vp= | −T*K/7.2 | |||||
| Lp= | L1−K*(T/7.2)^2 | ……(5)” | ||||
| L=L1 のとき | V= | 0 or | ||||
| V= | −2(T*K/7.2) | =2Vp | ||||
【 貨物列車のATS-P設定 】
制動遅れ4.5秒、Vy=45km/h 車上子取付位置=14m(JR西式)

| 減速 | 放物線 | T-180 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 接近警報P | 制動指令P | 基準P | |||||||
| K | km/h/s | Lp m | Vp km/h | Lp m | Vp km/h | Vy km/h | Ly m | ||
| 電車 | 19.10 | 2.653 | 52.85 | −14.59 | 13.91 | −1.33 | 55 | 180 | |
| 旅客 | 13.75 | 1.910 | 52.79 | −12.42 | 13.40 | −2.87 | 45 | ||
| 貨物 | −(選択不能.別パターン設定) | − | − | − | |||||
BGM= 俺たちのシルクロード(反分割民営化・10万人合理化闘争曲:1984年全国 うたごえの祭典参加曲 Data.Ent.Arr哲生2003/07/05)
|
open mail to:
|

|

|

|

| |
| Last Upload: : Last Update=2003/11/15 | |||||