�S�����̎j��ATS�ATC�T��(1)
�s ���ڎ� �t�@�@(04/08/29�lj�)- �S�����̂Ƃ`�s�r���j
- �`�s�r�|�r�S�������O�j
- �`�s�r�|�r�S�������ȍ~�j
- �`�s�r�|�o�^�|�r���J����
- �`�s�b�J����
- �ԗ��̊�{���\�Ɋւ�鎖��
- �m�[�n�E�̕~���Ŗh�����\���̂��鎖��
�� 56/10/15 �d�A����퐧���s�B����� �c�c�c�c�c�c �Q�{���S�� �� 63/11/09 �U����͖@�ݎԂɖ��K�p �c�c�c�c�c�c �ߌ��S�� �� 72/11/06 �g���l���Ў��E�o�D�� �c�c�c�c�c�c �k���g���l���S�� �� 73/02/21 ��~���t���b�g�h�~�D������̉ߑ����� �����E���A���É��ߑ� �� 74/11/12 �W���}�j���A���������A�֎~�������x�Ђ��̗p �V���w�M���댻������ �� 04/06/02 ����~�`�B��i�F�M���d���Ւf�@������ �I�����␅�Y���� - �`�s�r�̊�{���\�Ɋւ�鎖��
- �Ȃ� �h�`�s�r�|�o�����h�Ȃ̂��I
- ATS�EATC:����ł̋@�\�s���́H
�y �S�����̂Ƃ`�s�r���j �z
�@�厖�́��V�X�e�����ǁI���J��Ԃ����D��p�^�[���͍����̂������Ȃ��̂ł����C �`�s�r�E�`�s�b��_����O��Ƃ��āC���̔����o�߂��T������ΊT���ȉ��̂Ƃ����@���S���u(�ۈ����u)�Ƃ����̂́C�I�y���[�^���G���[��`�����Ƃ�O��ɁC�d��ȏ�Q��h����������������̂ł��D ������u�C���������߂ăG���[��`���ȁI�v�Ŏ��̂��h���邩�̎v�z�́C����,���Ă̈��S���u��ے肷����̂ɂȂ�܂��D
�m �`�s�r�|�r�S�������O�j �n
1927�@�Ŏq��ATS:�����n���S1941/09/16�@�R�z���Ԋ�(���ڂ�)�w�}�s�Ǔ�����(85km/h)
�@�@���M�����Ԍ����ɑ��x����(35km/h����45km/h��)�����݂Ɏ���
1941/12/08�@�����m�푈�J��
1942�@�S���Z���J��
1942�@���C���R�z�������{�����A���R�[�h���x�ƍ��@�\�t��ATS�ݒu����,'43.�L�����q�Ԓ��H
1945/�@ATS�ݒu�H�������ԋ߂Ɏ�t���O�̎ԏ㑕�u�����q�����őS�����ڍ��A
1945/08/15�@�����m�푈�s��
1945 ����i�|����(�͂���)��9.8km��(�ԏ㑕�u�S���ɓ���)�������������̌R���߂Ŏ������~
1946/�@��̌R��ATS�ݒu�H�������\���������p���C(��z���d���H���͋���)
1950/ �a�^�ԓ��x�u���d��Ԃɐݒu�ԐM���������x��
1954/ ���l���k���R���ATS-B�g�p�J�n
1956/10/15�@�Q�{���Z���w�E���]���Փˎ����D40�l���S �D�P���o���M���`�i
�@�@�M�������Ƃ������C�斱���͉����M����ʉߐM��(���������)�ʉߌ���(���M������~�X)
�@�@���咣������s�̗p�D��~�������^�u���b�g��O����ƗD��̉\������؋��s�\���ȗL��
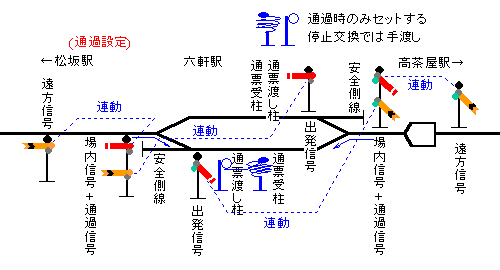
���ꂸ�� �]�����Ό��Ԃ��ՓˁC��S���ɂȂ����D
1957�`�������������d�ԋ�Ԃ�ATS-B�g�p�J�n
1960�`�`�^�ԓ��x�u���C���R�z�Ȃǎ�v�����Ŏg�p�J�n
1960/12/04 �s�c�n���S�P����(����)�{������������펞���x�ƍ���
�@�@�P���^�`�s�r�̗p�ŊJ�ƁC������l�}�s�ɂ����ݏ�����
1961/ �c�c����J���J�Ƃ`�s�b�ݒu
1961�`�����{�c�ѐ�(�X�|�Č�)�b�^�ԓ��x�u�g�p�J�n(ATS-S�̌��^)
1962/05/03 21:37 ����O�͓��w�Q�d�ՓˁD160�l���S�A�d�y��358�l �D
�@�@�������ԐM���`�i�E���Փˁ{��Ԗh��[�u�Y��őΌ��d�Ԃ��Q�d�Փ�
�@�`�s�r�ݒu�ցA�O���Z����&���㔭�������^�]���Ɏ�����Ƃ��ď�����L�����B����ɂ͖����ݒu�B ��Q�̏Փ˂܂�5�`6���������Ƃ���邪�A��Ԗh��@�ɁA�O���Z����͂Ȃ���������A�]�O�ʂ�̔��������������Đ��H���600�������ĐM�ǂ����t�����Ǝ��ԂƂ��Ă͌����������B�����A�{���ł��r�ؐM�����������͂Ȃ������̂ŁA���������M����ԗp�̗�Ԗh��@���W���Ƃ��Ă͒�߂��ĂȂ������l���B
1962/11/29�@�H�z�����ʏՓˎ����A�H��{���|�H���J�ԁB�H��{���o���M���̒��O�]���������A�@�֎m�Ƃ������Ƃ��Ĕ��ԁB�u�A���Ǖ����v�ŐM�����߂݂̂ɒZ���O����H�~�Q��݂��ė�ԕ������m�A�ǂ��s�����A��o�����m���Ȃ�����~���Ȃ������B���\���Ƃ��ẮA��ԏo������̒Z���O����H�ޑO�̃^�C�~���O�ɂq�����ɐ�ւ��A�Ό������f�����ɂȂ��āA�o���f�����Ő��ʏՓ�����B
�@��Ƃ��āA
1963/11/09�@���C�����ߌ������D161�l���S�D����1�^�ݎ����Ȑ��o�����ł̒E��
��('68/�E�����̋Z�p�����ψ���ݒu,�돟���������Ŏ��ԒE�������A3�`4���Ɍ���)
�@��Ԏ��ɐ��H�̗���Ŗ\��n�̂悤�Ȍ������s�b�`���O������ݎԂ������D
1963/11/10�@�R�z��������}���������|�݂��ْǓˁD��ATS-S�ݒu1964�`
1964/ ATS-B�ԏ㑕�u�̃g�����V�X�^��
1964/10�@���C���V�����J�Ɓ������I�����s�b�N�D �`�s�b�|�P�`�^�{�b�s�b
1965/ �`�s�r�|�`�^���C���Ŏg�p�J�n
1965/05/04 ���É��w�Ђ���17��380���ߑ����́D����D
�@�@��͊������m���~�܂����x�v���̐�����C����50%�ɂ����Dsee��'67/07/23
1965/08/21�@�V���������w��o���E�����́F�����w18�Ԑ�����̉Ԃ��A�M�����m���߂�
| �@�@ �@�@ �@�@ �@�@ |
�m <�`�s�r�|�r>�����ȍ~ �n
1966/04/01 ATS-S/ATS-B/ATS-A�@���S�S���ɐݒu�����B�o���M���̂ݒ����n��q�ݒu�B�@�@�ԓ��x�u�ɂT�b�^�C�}�[��퐧����t���������D����ATS�Ƃ͌����
1966/12/15 �����ɐ�������V��w�\����t���Ȑ���2���Ґ����E���A�ɐ����3���Ґ��ɏՓ�7�����S�A20������
1967/01 ���S�`�s�r�@�\�ɂ��Ẳ^�A�ȒʒB(s42�N�S�^11��)
�@�@'68�ݒu����1200km�ȍ~�厖�̂Ȃ��I��{�d�l��
1967/07/23�`/11/�@�H���I�[�o�[�������́B1300�`1000���ߑ��D
�@�@��͊������m���~�܂����x�v���̐��������𑬂₩�Ƀ[���ɂ���Dsee��'65/05/04
1967/08/08�@�V�h�w�\���^���N�ԏՓˉ��㎖�́D�ۂP���Ԓ��������~�߂�D
�@�@�m�F������A�ڂ���Ő�������x��Փˉ���
�@�@����M������20m���x��u�����n��q�v��V���D�u��퐧���v�ƍL��
�@�i�����O�x��Ƌ�ʍ���DATS-B�ł͒����n��q���Ȃ�:�ł������R�C��
�@�@�ڋߌx��́H���x��_�����Ԏ�O�̏ꍇ�́H���R�ς�Njy�ł����j
1968/02/15�@���C�����Č��w�Փˎ��́D����ATS�d������Y��
�@�@�d���������h�~���u�ݒu�i���m�b�`���Q�ȏ�ɂ͂Ȃ�Ȃ��j
�@�@�^�]���u�Ƃ̘A���͓��ւ𗝗R�ɕs�̗p(���֎���ATS�I���̂܂܂Ƃ������z�ɂȂ�Ȃ�����)
1968/06/27�@���C�����V���w�ݕ���ԒE���]���ՓˁD
�@�@�������45km/h������70km/h�ȏ�œ˓�
�@�@�����ߑ��x�x�u�ݒu�D55km/h�����܂ŗL����60km/h���ɂ͖���
1968/07/16�@�����������䒃�m���w�Ǔˎ��́D�d�y��210�l�D�T���p�ԁD
�@�@��������s�d�Ԃ̃h�A�ߕs���S�ŋ}��ԁC�����݉^�]�ŐԐM���`�i�D
�@�@�x�����u�ݒu�m�F�������Q�i�N���A�ɂ��Č����A�b�v��Q�x�ڂ������D
1969/12/06 06:20�Q����}���{�C(�X�����))�k���g���l�����Ńg���l���Д���
�@�@�斱���͒���g���l������Ԃ͊댯�Ɣ��f�A������~�Ƃ����^�]�K���ɋt����
�@�@�g���l����E�o���ď��h�Ƌ��͂��Ė������Ε����ɗ��߂�B
�@�@�͏斱���̓K�Ȕ��f�Ə^������
�@�@���S�͉^�]�K���ᔽ�Ə̂��ď������ĂR�N��̋}�s�������ɎS���̈���������
1971/03/04 �x�m�}�O�����]�������A���؎��̂ŃG�A�[�n�����A�����s�\�ɁD
�@�@�}���z�ʼnߑ��E���]���A����14�{�D�F�p���^�O���t���グ�Ă����
�@�@���d�������L���ɂȂ�y���ȂQ�����̂ōςD
�@�@��̓G�A�[�n��t�ʒu�ύX�D���̃}�j�A���̌������D������ʗ\���u���[�L�V��
1971/10/06�@�R�z�{���}�s�_��R���Ў��̐��ʏ�����o�Όy���|��10�n�q�ԂR���S��
1972/03/28�@�������D���w�Ǔˎ��́D�d�y��758�l mmmmm!!!
�@�@�������M���n��d�C���z�Ɍ��f����M�������m�F�o�����C�M���n��d����
�@�@ATS-B�^�̌x������ɂȂ邱�Ƃ��^�]�m�͒m�炸�C�̏�ƌ�F���i�s��Ǔ�
1972/06/23�@���l���k�����闢�w�Ǔˎ��́D�d�y��158�l
�@�@��������s�d�Ԃ̃h�A�ߕs���S�ŋ}��ԁC�����݉^�]�ŐԐM���`�i�D�Ǔ�!!
�@�@�ݗ���ATC������(�R��,���l���k,����,�ԉH�D�ߖ����������͊����s�\)
1972/11/06�@�k���g���l���}�s�������ɉ��D30�l���S714�l����
�@�@�ԗ��̓�R������D�^�]�K���g���l���E�o�։����D
�@�@�ԗ��̉R���R�Ă̕K�v�_�f�d�ʂ��l������g���l�����ł̒�Ԃ͎��E�s�ז�����
�@�@�R�N�O�̓��}���{�C�Ђł̎�M�̏斱�������͓P�ꂽ
1973/02/21 17:30:40 �V���������d�Ԋ�n�ߑ��{���x��E������
1974/04/21 �����������������|��ɏW�@�Ԃ�2034M���}583�n12���Ґ�(�Q��d��)��300R65km/h������傫�������鑬�x(�����̐���95km/h��)�ő��s�A1,2���ڂ̐擪�P�����E���B78�l�����B�^�]�m�̃~�X
1974/09/12 �V�����i��M���댻�����́F�����g�������ɂ��M���g�������Ɠ�����
�@�@�Ւf�@�ݒu�D�M���g�̂Q���g�g���������M����~�����Ɏ��g�������ĉ��D
1974/11/12 �V�����V���M���댻������
�@�F�O3�̂Q���g���ϒ��g���A�m�[�n�E�̃}�j���A��������
�@�@���S�����ł́u�d������Ƀt�B�[�h�o�b�N����͎g��Ȃ��v�ƒ�߂��Ă�����
�@�@�x�Вi�K�œO�ꂹ���A���䉞����10Hz�����M���O�����O3��210�댻������
1976/07/09 �V���������܍��O�߃g���l�����l���s�����B�h�A�̏���m�b�`����ꂽ�܂܍~�ԏC���A
�@�@�����Ŗ��l�o���IUSO���\�Ł������݁A���������Ńo���ė������ӎ��C�B
1976/10/02 04:42 ��P�P�쎖�́D���ٖ{����x�|�P��Ԃ�60km/h��������J�[
�@�@�u�ŋ�����ɂ��ߑ�110km/h�]�ʼnݎ�41����40���Ƌ@�֎Ԃ��E���]���A
�@�@�A���o�C�g�̑�H�d���Ő����s���Asee��'88/12�A'96/12�A���펖��
1976/11/30 �������w�`�i���́A�Ҕ��ݕ��ɒǓː��O25m�O��~�D�m�F������ߑ�
1979/06/02 �m��w�ŏC�w���s�d�Ԃɑ��Ԓ��̉ݎԂ����ʏՓˁB�˕��Ƀu���[�L���s��ԁA
�@�@�@��Ԋm�F�Ȃ��B���ԏ�o���Ɉ��S�����s�ݒu�B
1982/01/29�@�V�����w�����ߑ��C�w�ɏՓ�
1982/03/15�@���É��u���g���I�ɏՓˁD
�@�@�t���ւ���DD51�����������^�]�Ńu���g���ɍ�������(���ւɂ�ATS�H?)
1984/05/05 11:30 ��}�Z�b�w�R�z�d�ԉԌ�o���Փ˒E�������FATS�f�Ŗ{�����s
1984/10/19 �R�z�������Ήw�u���g���x�m����@�ߑ��x�E����j����:�@�֎m����
1986/12/28 13:25 �R�A���P���S����ԓ]�����́B�a���q�Ԃ݂�тV�����������œS������]���B�ԏ��ƒ����̍H��]�ƈ��v�U�����S�U���d���B�}�~���f��������CTC�ɂ��ė}�~���x���
1987/04/01 �i�q�����C�펞���x�ƍ����߂����SATS�ʒB(s42�N�S�^11��)�p�~
�@�i�����Ƌ@�\�̂Ȃ�(ATS�Ƃ͌Ăт�����)ATS-S���c��)
1988/07/03�@���w���}�`�i�j�A�~�X����
�@�@�������M�������Ƃ��D�����n��𒆐S��ATS-P�ݒu������
1988/12/01�@���t���V�؏�|��D���J�ƁD�h��܂őS��ATS-�o�^�̗p�I
1988/12/05�@������w�Ǔ����́F���҂Q�����C18���p�ԁD�����łR�x�ڂ̎���='64,'80,'88�D
�@�@�������M�������Ƃ��C�m�F�{�^���łx�������x��52km/h�̂܂ܐԐM���˔j�̖͗l
�@�@��P���֓��E�ߋE����s�s�ߍx��Ԃ�ATS-P�^�Ɍ�������v��O�|���A�͈͊g��
�@�@��Q�������n��q���퐧���^�Ƃ���i�\-SN,-ST,-SW,-SK,-SS,-SF�^)
�@�@�s���{�P��-Sx�n�ł̂x�������Ɓ�����25km/h���ƁA�s���{�Q�����lj^�]�ł�15km/h����
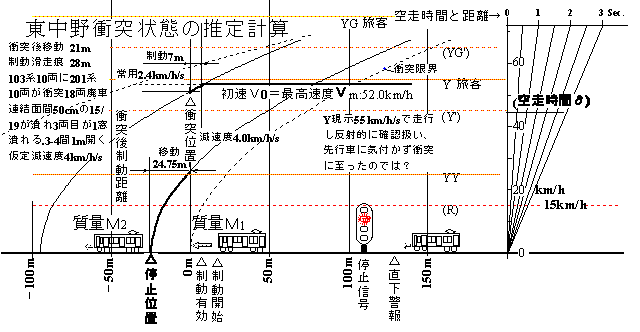
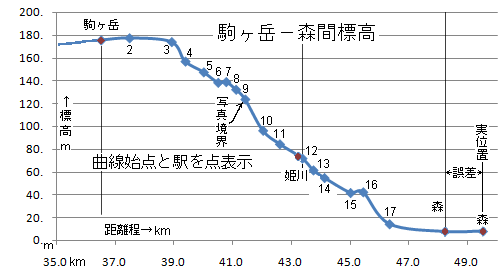 1988/12/13�@�P�쎖���F
���ٖ{���P��w�t�߃R���e�i�[�ݎԒE���]����ԕ������̇U�Asee��'96/12�A'76/10
1988/12/13�@�P�쎖���F
���ٖ{���P��w�t�߃R���e�i�[�ݎԒE���]����ԕ������̇U�Asee��'96/12�A'76/10�@�@���������������^�]�ŁC60km/h�����̉���J�[�u���ߑ�100km/h�Ői��
�@�@�@�R���e�i�[�ݎԂ�21����19�����E���]���C�@�֎Ԃ̂�CTC�ɒ�߂���16km�����܂ő��s
�@�@�^�⁁��ԕ����Ŏ�����퐧�����|����͂��D�@�֎Ԃ͂Ȃ�16km�����ꂽ���H
�@�@���������\�I�ݐ��Q���͌���ɒ�~���Ă邩��C�@�֎m�����ӎ��ɒP�ƃu���[�L
�@�@�𑀍삵�Ĕ�퐧�����ɉ������\���͂���D
1989/04/13�@�ѓc���k�a�w���ʏՓˎ��́D
1991/05/14�@�M�y�����c�����ʏՓ��F���ւ��S���̈�O�����ŕs���͂߂����̈�����
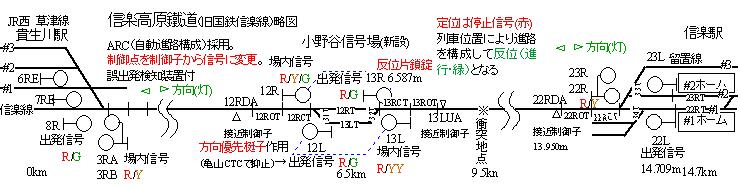
�@�̈ӂ̂q���������o���D���ꎩ���̂��ߏC����ƂŌ�o����N���A
�@JR�����M�y�S���ɖ��f�ŕ����D�枌�q�ݒu�C���f����,�s���Ȍ����ƂȂ��p�nj돈���U��
�@JR�斱���V�����F�����w�E�����D��R�Z�N�^�[���S���ɉߓx�̎d�؉��A�Z�p�̐��s��
 |
�@�@�F�q�������Ȃ�������ɂ�ATC������~�@�\������
�@�@�^�]�m�̒��ӗ݂͂̂ʼn^�s���Ă������A�����֑�
�@�@����ԓ������Ԃ����e����Q���M���܂Ői�ރV
�@�@�X�e�������ŁA��Q���M����~���������Ƃ���
�@�@���`�i���ˁI
�@�@�@����JR���܂߈�����ɋ�����~�͂Ȃ��������A
�@�@�o���M�����u��P���ւȂ狗��������A�{���ݔ���
�@�@����~�\�ŁA�{�����s�̑�Q���M���ɋ�����
�@�@�~��݂��Ȃ��ݒu��̕s���I�Ɓ��ߑ��]�T10��
�@�@�̑�Q���M����ATC��~�Ȃ��ł̓����i�����e
�@�@�ɖ�����������(04/08/16��/11/05�NjL)
1994/02/22 15:20�@�O���S�������]�����́D����5
�@�@�p��2�C�h����,��Ԗ���,�����v,�J�ʌv��
1994/02/22 17:45�@JR�k�C���Ώ������}��������10
�@�@�������]�����́C
�@�@183�nDC�P���]���Q���E�����������C�����v�̏���u�C�h����ݒu
1996/12/04 05:49 ���ٖ{���ʼnݕ���Ԃ��E���]���V�AJR����`�m�R�ԂŁA�D�y�ݕ�
�@�@�^�[�~�i�����~�c�䂫�̉ݕ���Ԃ̂����A�R���e�i�ݎ�20�����ׂĂ��E�������B
�@�@�������x��60km/h�̎��̌����120km/h�߂��ő��s���Ă���(�^�R�O���t)�B
�@�@'97/2��7�� �ۍ╛�x�В��A�n�[�h�ʂ̑���s�Ȃ������B'76/10,'88/12�`�R�x��
�@�@�ߑ��]�����̂���������ɑ��x�ƍ����u��ݒu�A�^�]�m�@�|���فB
�@�@�@�R���̂ɋ��ʂ��čō��n�_��ʉ߂�������z�ɂȂ�������̉���J�[�u��100km/h����
�@�@�ߑ��E���]���B�Ɍ��z�o��͍s�^�]�����狏���肵����}���z�i�����H
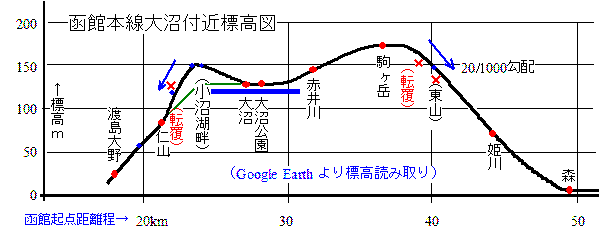
�@�@���lj^�]���ɁC��s��Ԍ����f��������F���ĉ����Փ�
�@�@�������̖��lj^�]�J�n�ɖ��D�����C���x�ƍ��Ȃ��D���ؒ�~�Ή����Ǘv
�@�@JR���Ȃǂ͌�����lj^�]�p�~�C�w�߂̔��f�����ǎw���^�]�ɐ؊��A���C&��&��B���u�B
1997/10/12�@���}�X�[�p�[�������C�匎�w�œ��֓d�ԂƏՓ˂��E���]��
�@�@�������d�Ԃ̐M�������DATS-Sn�̔���~�������Ȃ����������͕s��
�@�@�Č������ł͒n��q�Ŕ���~���{���ɂ͒B���Ȃ��D
�@�@���֎���ATS�d����OFF�Ƃ��āC���̔�����ɒN�������������^���D
�@�@��ATS���u���[�L�n���h���������݂ƘA�������������Ƃ���������̎��́I
�@�i���SATS�ɑ���1967�N�^�A�ȒʒB�F���������ɒ�G�j
1998/08/05pm�@�V�������É��w�ŃI�[�o�[�����I
�@�@������414����80����418����50���B(�����ԍ��͏��F�������ʍs��)
2000/03/08�@����J�����ڍ��w�\���E���Փˎ����F���҂T���������D�֏d�s�ύt���
�@�@�֏d�Ǘ��v�����ہD�K�[�h���[���ݒu��Ȃ��C�c�c��̂ɒ[�Ɋɂ��D
�@�@�Ȑ��o�����̊ɘa�Ȑ��J���g�������ꕔ�Ƒ�Ԓ����̋���(�֏d�䖳�Ǘ�)�ƂŒE���Ɏ���A�����|�C���g�ɗU������đΌ���ԑ��ʂɌ��ˁB�ߌ����̂Ɠ����E�����������ł���A���������ȕ��͂����\����Ă���A����J���ڍ����̒���̉^�A�Ȏ��̒�������w���ł���u�Ȑ��o�����ւ̃K�[�h���[���ݒu�v�͑S�S�����Ǝ҂Ɋ����E�z�ߍς݂ƂȂ��Ď��̂ɂȂ�Ȃ������\��������D
2000/12/17�@�����d�S�z�O�{�����ʏՓˎ��́F�u���[�L���b�h�ܑ�
�@�@�u���[�L���P�n�������Ȃ��C�O��o�����T�[�̃X�g�b�p�[�����������D
�@�@�S���P�s�Ԃ̂Q�n�����C���͎g�p���~�D
2001/04/18�@���C�����x�m�w�`�i����
�@�ߑ��h�~���ƍŊO��80�������삵����~��75���`�i
�@SF��ST���ς݂��������`�i�O��̖h��Ŕ���~��̌�o�����~�߂��Ȃ�����
2002/01/03�@���S�V�H���w�ߑ��E�����́�2002-5
�@�@�~��ɑϐ�u���[�L���g�p�����C�K�v�Ȕz���������ɉ^�]
�@�@�X��l�܂�ɂ�萧���͂��ɒ[�ɗ��������̂Ǝv����
�@�@�C�ۏ��ɗ��ӂ��ϐ�u���[�L�g�p���w�߁D
�@�@�ϐ�u���[�L�g�p��ϐႪ���[�����������ł͂Ȃ����H���B�ꂽ��ɕς���D
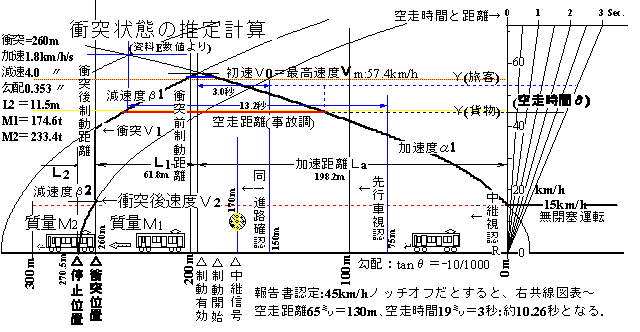
2002/02/22�@���������C�V�Á|�����O���Ǔˎ�����2003-4B
�@�@���lj^�]���ɒ��p�M��������C�������ՓˁD
2002/11/06 �X�[�p�[�͂��Ƌ~�}�����������́�2003-5
2003/10/18 17:10�@���S�V�ߑ����w���ˁF�̒��s�ǎ��̑���~�X�D�����n���h���}�X�R���t����
�@�@���S�^ATS���`�i�O��̖h���ł��邱�Ƃ�ATS�����蔲������{����
| 2004/06/02 07:15 �I�����␅�Y(���l)�掖�� | ||
|
���������̊ۑ��ɏ�グ�E��11�l�����B 07:11��Ԗ����ŗ�Ԃ��ĂԂ����̎��̂ʼn���ؒf����s�ʁB�����̎��͕̂s�������o����ł��M����d�ɂ��ǃ����O�n��q�łq�����`�B�\�B�����s�̗p�B | ||
| 2005/03/02 20:40 �y�����낵���S���h�ѐ��h�щw���� | ||
|
�s���~�܂�w��47D�U��q�����}�앗17���R���Ґ����ō����x�߂��œ˓����đ�j�B�^�]�m���S�A��q11�����Q���d���W���y���A�ԏ��y���B���������������A�ō����x�����ATS-SS�ߑ��h�~���u�s�ݒu�Ŏ��̂�h���Ȃ������BATS-S�n��q�P�s�ݒu�A�P�����~�X�A���邢�͐ݒu��̃G���[�ŁA�U�_�W�̒n��q�ʒu�̂T�`�U�ɖ�肪�������B | ||
| 2005/04/25 09:19 ���m�R��(��ː�)���ߑ��x�]���E�������B | ||
|
207�^�V���Ґ������d�Ԃ�300�q70km/h������108km/h�Ői�����T�����]���E���A���H�e�}���V�����Ɍ��ˁA����107���d�y��547���̑�S���ɁB �@ 3/02�h�ю��̂�4/25��莖�̂��A�ߑ��x�h�~���u�Ƃ��Ă�ATS-ST�^���x�ƍ����u�s�ݒu�����̂�h���Ȃ����������ł���BATS-P�Ɋ������Ă����x�����n��q��ݒu���Ȃ���Ζh���Ȃ��BATS-P���ő��x�������s����Ƃ����������ȑ�b�k�b�����ł���B | ||
| 2005/12/25 19:14 �H�z�����}���Ȃٓ˕��E���]�������D | ||
|
�H�z����Q������S����l�ߕt�߂̒z���𑖍s���̓��}���Ȃ�14��485�n�U���Ґ����˕����đS�ԒE���C�R�����]�����C�擪�Ԃ��_�Ə����̃R���N���[�g�ɏՓ˂��Ē��p�ɐ܂�āC���҂T���C����33���̑�S���ƂȂ����D �@ ���s�̕����ϑ��l�ŗ}�~�����߂颋A�Ґ��䣌^�ł͕����̋}�ςɗ�Ԃ��~�߂���Ȃ��^�C�~���O���c��D�����ȊO�̋C�ۏ��댯�\���}�~���s���Feed Forward �^�������Nj�����]�n���������D�y���ЊQ�ł͗ݐωJ�ʂȂǂŊ댯�\���}�~���s���đ�ЊQ�͌J��Ԃ���Ȃ��炻��ɗ�Ԃ��������܂��ɍς�ł���D�C�ۊw�̐��ʂ�����ĎS��������}�����ĖႢ�����D �@ ���A���C���V�����̊փ�����Q��ł́A�J�ʗ��X�X�N'67�N�����璩�[�Ɏዷ�p���{�C���R�ӏ��̕ې���ł̃��W�I�]���f�ϑ���5000m���ł̋C���ƁA�C����(���ˁH)���ϑ����āA���n�n�\���ƕ����Đϐ��U�h�~�U��������s���Ă��邪�A��������炩�ɢFeed Forward �^��������\������ł���D �@ ���̓����ɂ́A��������Ȃ������ꍇ�̐����ьY����������点�Ȃ��l�Ȍx�@�E���@�̔�����K�v���D�k���g���l���������ɎS��(72/11/06)�斱���N�i�Ɠ��}���{�C��(69/12/06)�����̋��̎Ӎ߁E���Ȃ��v�邾�낤�D�V�C�\��100��������Ȃ��Ƃ����ČY���������������܂�Ă͕s�m�����̎c��J���E���s�͊�Ȃ��ďo���Ȃ��Ȃ��Ă��܂��D���������̐���m�x�͕ʂƂ��ėv�͂��C�̖��D | ||
| 2014/02/15 00:14 ���������Z�g�w�Ǔˎ����D | ||
| �~�Ⴊ�������w�ł̉ߑ�������Ԃ��������ō����x�����͔��߂���Ă��Ȃ������Ƃ���A�w�߂����Ē�~���w������āA���}���������Z�g�w��O600m��80km/h�ő��s���̗�Ԃ���퐧�����|�������ǂ�������40km/h�Ő�s��ԂɒǓˁA�C���s�\�̔�Q�ƂȂ�B
�ʏ�Ȃ��퐧����4.0km/h/s�̌����x���A�ᒆ�őϐ�u���[�L�����Ă��ĕ���1.111km/h/s�ƂȂ��Ă������̂ł��邪�A�ō����x����i�}������55km/h�ɂ��Ă����������ꂽ���́B
�ԏ㉉�Z��i�����p�^�[�������Ȃ̂ŁA�ݒ茸���x���~��ɍ��킹�Č����Ă���Ή���\�������B
�����x1.111km/h/s��31.5/1000���z����������A�ᒆ���[�h�̋}���z���~�̓p�^�[�����蔲�����x(10km/h�`15km/h���j�ɗ}���āA��̕��R�n�܂ŕǂ��̂�҂��Đi������K�v���L��B
����̓p�^�[�����Ɍ��炸���ᒆ�^�]�̗�ԑS�ʂɊ|����ׂ������ł���B | ||
�m <ATS-P>/-Sx
�J���֘A�j �n 1974�`1980�@���ώ��^�o�̎����^�p�����{���D�@�@�p�^�[���^�����ˑR�̔���~���s�]�D'87�Ƀg�����X�|���_�^�o�̗p�őŐ�D
1982/01/29�@�V�����w�����ߑ��ʼnw�Ɍ���
1984/10/19�@�R�z�������Ήw�u���g������@�ߑ��x�E����j���̂��_�@��
1986/�� �o�J���@�V�������U82/01�ŁC���^�i���ώ��^�o�j�ƁC���nj^�̂g�^
�@�@(�g�����X�|���_�^)�`�s�r�������D�o�^�̌��^
�@�@�����C���s�ȂǂS�w�ƁC�d�e�U�U�^�d�k�P�U���ɂg�^�`�s�r���D
1987/07/05�@���w���}�`�i���́D�����n��o�^�Q������������
�@�@�g�^�`�s�r�𐳎����`�s�r�|�o�^�Ɩ���
1988/12/01�@���t���V�؏�|��D���J�ƁD�h��܂őS���`�s�r�|�o�^�̗p(���ғ����s��)
1988/12/05�@������w�Ǔˎ��́@��s�s���`�s�r�|�o�^�������\�D
�@�@��������v15����888km�C������C��a���̂o��������
�@�@�����n��q�Ŕ�퐧���t���̂r��������
�@�i��퐧�������n��q�@�\���ȒP�ɂ͕t�����Ȃ��|�a�^��S�p�C�|�o�^�Ɋ���)
�@�S���`�s�r�|�o�^�̗p(12/01���t��)�����ʓI��12/05���̂̌�����ɂȂ�A�ϋɓI��ۂ𔖂߂āA�Г��O�ɕ��y�̐��_��グ���Ȃ��������Ƃ��e���Ǝv���A�؊����̐�`���Ȃ������DJR�������{�ȊO�͍����s�̗p�̂܂܁D
1989/04/13�@�ѓc���k�a�w���ʏՓˎ��́D
�@�@�����n��q�ł̔�퐧���t�����r��������
�@�r�m������̎����͌����ɂ͂��̖k�a�w�Փˎ��̂Ƃ���Ă���炵�����C�J���C
�@�����C�ʎY�C�ݒu�̓����ƁC���̂̃C���p�N�g�C�y�у}�X�R�~��ނł̎���
�@����~�@�\���������Ƃ̒Njy���l����ƁC���̑O�̓�����Ǔˎ��̂��瑖��
�@���Ƃ�������������Ȃ��D�����쎖�̎���JR���L��́u�Q�x�̌x��Ńu���[�L
�@���|���Ȃ��^�]�m�͂��Ȃ��I�����̓d�Ԃł͂Ȃ��I�v�Ɨ͐����C�����n��q
�@�ł̔�퐧���@�\�̕K�v����ے肵�Ă����D���̌����Ɉ�����Ă��C�L���Œ�
�@���n��q�ł̔���~�@�\�̕K�v���Ɍ��y�����}�X�R�~�͌�������Ȃ��������C
�@���Ƃ��Ă�JR���ɓ����Ă���
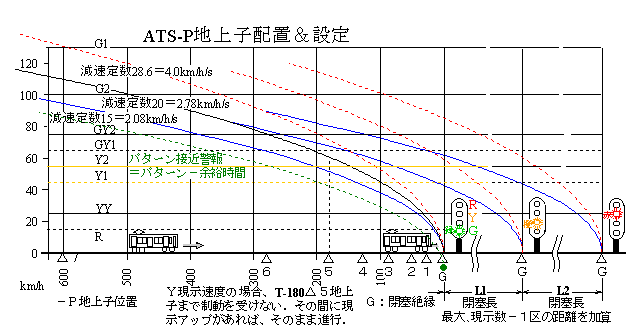
1989/11/ �i�q���ł`�s�r�|�r���g�p�J�n
1990/12�@�|��Ł|�r�s�����D�n�_���x�ƍ��n��q�ʼnߑ��}���D
�@�@�d�v�n�_�ɐݒu����D�펞�łȂ��̂Ŕ����邪�C�����_�C����Ȃljߑ������̂�
�@�@��������n�_�ɑ��ƒn��q��ݒu����D
�@�@97/08���Ëߍx�Еl�Փˎ��͖̂��lj^�]���ő��Ƃ��Ȃ������I
�@�@���p�̖��lj^�]�����߂��K���ɖ��D
1991/02�@���Ł|�r�v�g�p�J�n�D�@�\�́|�r�s�ɓ����D
�@�@�l�o�t�g�p�ȂǓ����\�����قȂ邾��
1991/04�@�ݕ����|�r�e��(���|�o�^�p�J�n�H)�D
�@�@�����́|�r���Ɠ����D�ߔN���Ɓ|�r�s����}����
�@�@01/04/18�x�m�w�`�i���̂ł́C�ߑ��h�~���ƂƂ��ē���D�@�֎m�̂S�d�̃~�X��
�@�@�^���Ȃ����C�~�X�O��ɂ�����J�o�[����̂����S���u������C
�@�@�펞���x�ƍ��@�\�͕K�v
1993/03�@�l���Ł|�r�r����
1994/04�@��B�Ł|�r�j�����D�r�r�C�r�j�C�r�v�C�r�s�͓���@�\
199X�@�i�q���̓��C������ԂɁ|�r�m�f�������r�s���D�r�e�̂r�s������C�؊�����
2001�@JR���C�펞���x�ƍ��@�\�������|�r��ʌ݊��́|�os���ꕔ������:�V���C���ɐݒu
2001/03 ���݁C����28�����1500km�C���łV����300km�~��
�@�@��B���l���͂܂����M�������n��q�̂r�m���H����
2004/02/29 �����g���l��(���{�ꁕ��������)��ATC��p��ATS-P�Ɋ���
2004/xx/xx �R��ݕ����V�h�|�r�܊Ԃ�ATC��p��ATS-P�Ɋ���
2005/3/29 100km/h���s���~�܂�w�ɍō����x����̉ߑ��h�~(�x��)���u�`���t��
�@�@�@�@���ׁI[H17���S�Z195�ʒB] SN�n�ɋ������������A����E������100km/h�ȉ����u
2005/5/27 �Ȑ����x�ƍ��ݒu�`���t���A�e�Ћɂ߂Č��d�Ȏ��Њ����
2006/3/24�@�Z�p����� �A�iH17���S�Z195�ʒB�͎������Áj
�@�@�@�@�댯�̗\���������ւ̉ߑ��h�~���u�ݒu�`������SN�n�ւ��`����
2006/04/dd JR���CATS-PT�S�������v�攭�\�A�ڍd�l����
�y �`�s�b�J���� �z�@�@�@<ATC>
1961s36 �c�c����J���J�ƁC����ATC�H���CAF-FS���T�����n��M��'61�@�@�d������SSB�ϒ��O����H������(�V����&�𗬓d����ԗp)
'64�@�@�c�c�������J�ʁCATC�͓���J������(���c�̔n��|��i��)
'64/10 �V�����J��ATC:�d������SSB�P�g�����C0�C30�C70�C110�C160�C210km/h
'69�@�@���c���J��ATC��AF-AM�����̂T�������ԓ��M����
�@�@�@���É������̒n���S��������O��ATC��
'71�@�@����e��ATC��(���c������)
'72�@�@�������������|�Óc���J�ʁC�����|�ю�����ATC-1C,'76�i��܂�ATC����
'72�@�@(�D���w�ǓˁC���闢�w�Ǔ�)
'73�@�@ATC���v��:�R�褋��l���k�C���݁C�ԉH
'81�@�@��L���R��ATC�����{ATC-1E:���ԉH
'86/10�@�鋞��(�{�ԉH��)ATC�ŊJ�ƁC�����i�H�ݒ�̏����e�ʕs���Œ����ɓ�����
'88/03/13 ���g���l��(�Ìy�C����)ATC-L�J��
�@�@�d��������SSB�łP�����g�Q�M���g�g���������̗p
�@�@������ATC�ݔ���p�����ԓ��M����ATS�D������ATS�ƌĂꂽ
�@�@������ڰ��Ԃł���@�֎Ԃ���Ȃ̂Ŏ����ɉ�s�K����ATC
'00/07 ����e��ATC����(���c������)ATC-1J
'02/12�@�@DS-ATC���k�V���������|���ˊԊJ��
'03/XX�@�@�R��ݕ�����ATC�o�b�N�A�b�v�S�p(ATS-P/-SF�ɏW��)
'03/12/21 ���l���k��D-ATC�؊��D2001�`�R����Ȃǂ̂`�s�b��Ԃ��C
�@�@�o���l�̒�~�ʒu����x�ƍ��p�^�[���������c�|�`�s�b�Ɋ�����
'04/03/13 KS-ATC�@��B�V�����ɐ�s�̗p�A�����H������ATC-NS�Ɠ���
'06/03/18 ���C���V������ATC-NS�ғ��J�n
'06/07/30 �R���D-ATC�؊�
'07/**/** ���k�V���������ȓ��DS-ATC��
[[ �Ǖ� ]]

|
|
mail to�F
| 
| 
| 
| |
|
Last Upload:
�@ATS�X������10-14
��01/10/07�C���S������58-59��01/11/06�����M�C�� Last Update: 05/03/10�@04/08/31,/16 ,6/27,/07 (/02/29,/01/27,03/12/25,org/21) | ||||