
- 腕木に取り付けた2種類のフィルターの1つが腕木の動きで1個の信号電球を覆って現示が変わる
- 腕木の裏面は白色に黒線

|
|
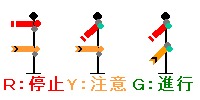
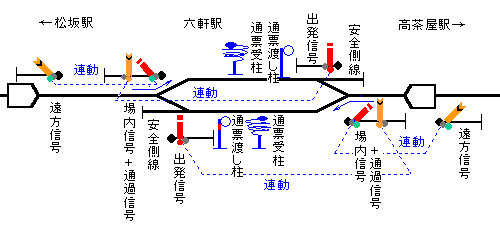
同時進入時の信号現示。
通票受け柱、通票渡し柱は通過列車のみが使用。停車列車で不使用時は倒しておく建前だが建て放しが普通 | 変更手順は、停止優先、双方停止で分岐転換、
| 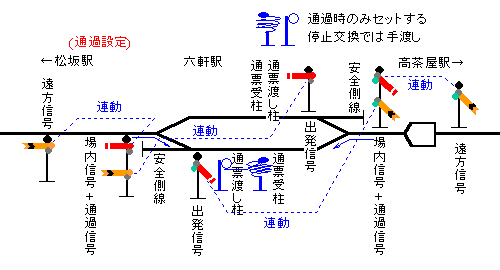
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交換駅六軒へ変更局指令17:53発、快速で全2:31〜2:39。現在はディーゼル化されて快速1:43前後で結んでいる。また付近は1959年紀勢本線全線開通で紀勢本線に組み入れられた(亀山−多気間)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
国際連合開発計画(UNDP)鉄道工学専門家 齋藤雅男
1956年(昭31)10月15日18時22分、参宮線(現在の紀勢本線)六軒駅に進入した鳥羽行き下り快速第243列車(C51+C51形重連牽引、客車9両)が同駅の通過信号機の注意現示を誤認して60km/hの速度で進行、出発信号機の停止現示を認めて非常ブレーキを扱ったものの過走し、安全側線に乗り上げて機関車2両、客車3両が本線側へ脱線転覆した。そこへ対向の上り快速第246列車(C57+C51形重連牽引、客車11両)が走行してきて転覆車両と衝突、死者42人、負傷者92人の大事故となった。
この事故の原因は単なる信号冒進のように思われるが、本来、この列車の行き違いは一つ先の松阪駅の予定であったところ、第243列車の遅延のため急遽、行き違い個所を手前の六軒駅に変更したものであり、六軒駅の通過・出発信号機の現示変更が、列車位置との関係でどの時点で行われたかが問題となった。当時、参宮線は腕木式信号機、通票閉塞方式となっており、六軒駅では閉塞扱いと信号機の扱いは連動せず(分岐器の方向とは一敦するが)、別の扱いとなっていて、そのタイミングが問題となったのである。  参宮線六軒駅の列車衝突事故(1956年10月15日) 翌早朝、亀山駅で下車、車で六軒駅に到着したが、事故現場は破壊ざれた車両の残骸が散乱し、まるで戦中の爆撃を受けたあとのようなありさまであった。死傷者の多くが修学旅行途中の高校生であったことも、この事故の悲惨ざを強調することとなった。 事故調査を進めてゆく過程で、駅員や乗務員からの話によると、運転心得にある運転通告券(運転取り扱いの変更について、事前に停車駅等で乗務員に周知させる書面)が発行されておらず、信号現示の確認のみに頼る扱いになっていたこと、重連牽引の前補機側で非常ブレーキを扱ったため、後の本務機を経由して客車編成につながるブレーキ管の減圧が不能となり、そのため、結果としてブレーキ距離が延びてしまつたことも判明した。 重連牽引のブレーキ問題は戦前から指摘されていたことであり、そのため補機は列車の後部への連結を原則とすることになっていたが、機関車運用の都合などから、戦中の混乱の中でこのような使われ方が常態化していたものである。 (水上機関区のEF12形など2両1組で運用されることの多い電気機関車では、ブレーキ管の応答速度を上げるため、中継弁を設けているものがあった) (2011/09/06追記:補足引用)
戦時体制の名残の無対策重連運転記事によると「重連牽引のブレーキ問題は戦前から指摘されていた」「そのため補機は列車の後部への連結を原則としていた」「水上機関区のEF12形など2両1組で運用される・・・・・・・・機関車では、・・・・・・、中継弁を設けているものがあった」「運転心得にある運転通告券が発行されておらず」と、エラー発生前提の安全策が無視されていて事故に直結しやすい状況だったことが分かる。網谷りょういち氏による「(続)事故の鉄道史」では、北陸本線でも重連機関車に中継弁を設置していたと述べていたが、齋藤氏の記事では、戦前から知られていた欠陥で、補機を後ろに連結することで回避していたものを戦時輸送体制で有耶無耶になり重連運転される様になり、戦後もそのままで事故に至っていることが述べられている。 それなら上越線と北陸線に限らず重連運行が必要な他の急勾配区間でも中継弁を設けた機関車が走っていた可能性が有り、戦時体制のまま重連対策を怠っていた参宮線で減速力不足で防げなかった過走事故で惨事に至ったことになる。 |
 事故当時は同時進入禁止規則や 転換時素設定はなかった模様 |
 List |
 事故一覧 |
 前 |