ATS-Ps 概説 (#72)
ATS-Psとは、JR東日本が変周方式によるATS-Snの機能拡張版として開発して新潟近郊と仙台近郊に設置したもので、従前のATS-Sn/-SFに最高速度からのパターン式速度照査を付加して停止信号冒進を無くしたATS-Sx完全上位コンパチのATSである。平坦地であればほぼ一段制動防御であり若干車間を詰められる。加えてパターン式速度制限4種(分岐、臨時、曲線、勾配)と誘導、入替速度制限を設定している。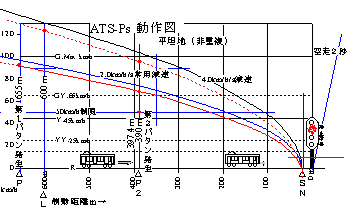
ATS-Ps区間には、従前のATS−Sn/−SN/−Sx受信器搭載車両はそのまま入線でき、特に−Sx系は信号手前390m付近でY現示速度照査を受けるのでSn地上子の非常制動での最大冒進可能距離が短縮されて安全度が上がる。
ATS−Ps搭載車はそのまま従前のATS−Sx区間に(-STの東海を含めて)入線するとコードが衝突する部分があり切替可能で、検出すると自動的にSxモードに切り換えられて運行には差し支えない。
速度照査は信号前や速度制限前(555m)の位置にパターン発生地上子(対)を置いて照査、信号現示ではY現示制限速度を中間段とする最高速度から2段階の速度照査パターンを発生させ、現示アップすると取消地上子(103kHz)でパターン消去する。パターン式の速度制限のため冒進がなく、ATS-Pに較べて安価なこと、及び表示装置としてはパターン制限速度と走行速度が運転者に表示されることが制動限界一杯とかの微妙な運転をしたい場合に優れている。(安全装置がなるべく余計な介入をしないという思想もあり善し悪しとも言えるが、機関車では列車引き出し時に特に欲しい情報で、ATSからいきなり制限を受けるより有り難いだろう)。しかし車種別の速度制限機能がないのは車上時素設定で微調整可能な-Sxより若干厳しい。-Sxでは車上装置の基準時間設定を0.5秒±0.05秒変えて列車・貨物と振り子車に対応しているが、-Ps車上装置の対応は不詳である(第1パターン終端をY現示速度として列車別に55km/h−45km/hを分けている)。
また、ロング地上子でY現示制限を掛ける方式の場合は、地上子が手前の閉塞区間に掛かる場合にその重複分支障するが、Psでは重複パターンを扱え支障しないので、ギリギリまで接近できる。第1パターンはY現示速度以上に適用するもので、勾配補正がないが、規則通りのY現示速度で運転すれば第1パターンには当たらない。重複パターンは駅のような短距離閉塞で地上子が手前区間に設置されパターンが重なる場合に手前の場内信号区間に使われる。

ATS-Ps構造 (Fig.1〜2)
ATS-Psの構造としては、従前のATS-Sxの拡張として位置基準車上演算制限パターン照査を付加するため、まず自由発信周波数が105〜103kHzだったのを73kHzに下げて新たな変周周波数95kHz、90、85、80kHzを設け、ロング地上子(130kHz平坦地約600m)手前にY現示速度制限を行う第1パターン発生地上子(80kHz:平坦地で信号手前655m)と、冒進のない停止位置を規定する第2パターン発生地上子対兼ATS-STのY現示速照対108.5kHz×2を平坦地で390m位置に設置し、信号20m手前に非常制動123kHz直下地上子を設置。
線路条件の修正コマンドとしては2種類。勾配補正地上子をロング地上子の手前の<TBL-3>指定位置に設置(Fig.2)して車上に実効勾配を伝え、 駅などの短閉塞で地上子が1つ手前の閉塞区間に設置される場合に、手前側(たとえば場内信号側)に別のパターンを発生させるためのbパターン(=場内信号)弁別マーカ(95kHzあるいはaパターン勾配補正108.5kHz)が配置される。
車上パターンの消去には-SxでNop(不動作:地上子検査)だった103kHzを割り当てた。(そのため速照や誤出発の不動作状態とコマンドが衝突し、-Snへの増設であることから当面種別地上子設置で対策することとなったが、本来的にはATS-PsのNop周波数:73kHzを用いて区別する筋のものである)
速度制限コマンドとしては、新周波数地上子の組合せ<TBL-2>とその設置間隔<TBL-4>で分岐、臨時、曲線、勾配(code 90kHz+95、90、85、80kHz)について555m先地点の速度制限値を指定し、また消去する。このうち分岐制限は50m走行で自動解除される。分岐制限は場内信号が停止現示の場合には設定されない。だから高加速車では分岐側で過速突入条件が残る。停止位置にも拠るが安全側を考えると停止信号時は低速の分岐条件で設定することも考慮の余地がある。
以上により-Ps搭載車は冒進がなくなり、-Sx搭載車にはY現示制限速照が付加され、-Sn、-Sx搭載車に対しては一般閉塞信号でも直下地上子による非常制動が掛かる様になった。尚、一般閉塞信号の直下地上子については従前の-Sxでも設置するか否かだけの問題で、システム上、技術上の問題ではない。駅の格を下げて場内信号と出発信号を一般閉塞信号として非常制動直下地上子を取り付けなくしたのは政策の問題。たしかに必ず直下地上子があるATS-Pでは全く問題ないがATS-SF車が入線する併設区間では追突防止に少なくとも場内信号相当には123kHz直下地上子を付けるべきだろう。東中野駅、お茶の水駅、日暮里駅の追突事故はどれも場内信号相当直下地上子が非常制動動作なら防げた事故だったのだから。現在分岐のない駅は絶対信号ではなく閉塞信号化されている(東中野と日暮里も)。
|
パスワードは下記スレタイ= 信号・標識・保安設備について語るスレ8 http://www.uploda.net/cgi/uploader3/index.php?dlpas_id=0000002360.zip ●バックアップコピー→p1〜p52ここ● |
| 周波数 kHz | ATS種別 (←左方向へ上位コンパチ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| −Ps | −Sx | −Sn | −S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sx 周 波 数 | 130 | S型警報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 123 | 絶対停止 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 108.5 | マーカM3 /車上速照 | 車上速照 | −
|
| 105 | 信号P消去 | − | 常時発振周波数
| 103 | 常時発振 | 周波数 −
| (84) | − | 制御振り子車(非Ps) | 常時発振周波数 −
|
| (67) | 高減速車判別信号
|
| Ps | 拡 張 部 95 | マーカM2 | Pb(場内)
| −Sx=ST、SW、SK、SS、新SF −Sn=Sn,SN,旧SF −S =S,旧SF (fr)は車上→地上の信号。 他は共振周波数 90 | マーカM1 | 速照先側 85 | Sx抑止
| 80 | P1発生
|
| 73 | 常時発振 | 周波数
| (100.5) | 踏切列車検 | 知103k相当 | ||||||||||||||||||||||||||
非コンパチコマンド部
ATS-PsがATS-Sx上位コンパチといっても、前述の通り不動作時に予期せぬ異常コマンドが生成されたり動作が取り消されるものがあり、また-SF/-ST車上時素速照コマンドが第2パターン発生コマンドと衝突するので、3種の問題を孕んでいる。すなわち作業資料に拠るとこのうち、1,3項は直前2mに地上子種別指定地上子を置くことで回避するとされ、−Ps区間であれば対応が必須、−Sx区間であれば車上装置を−Sn・モードに切り換える必要がある。以下具体的に述べれば、
- 分岐制限として−Sn地上時素速照地上子130/123kHzを用いた場合、及び誤出発防止地上子123kHzを用いた場合に開通側、許容側で103〜105kHzであるから信号パターンを消去する。
対応策は2m前に種別指定地上子として速照の場合に85kHz地上子、誤出発の場合に95kHz地上子を設置する。新設であればNop周波数を73kHzに選べば可。
- -SF/-Sx車上時素速照と-Psの第2パターン発生が108.5kHz×2地上子で一致し、-Ps車上装置に不必要な第2パターンを発生させる。
対応策は-Sx速照として2m前に種別指定地上子85kHz地上子を設置する。
- 分岐速照には1箇所に3〜4対の地上子が設置されていて、その全地上子対の直前に85kHz地上子を設置する。
-Psが当面拠点設置だから、第2パターン発生と分岐過速度速照は重なりやすく、速照とパターン発生を共通配置に割り付けてSx-のY現示速照を担わせたのがエラーなのかもしれない。設計時に拠点Ps式配置が主になることは想定してなかったのだろう。駅でのみ分岐でそこに-Ps設置なら第2パターンにこそ識別地上子を付加すべきだったが、-Ps原則非設置の閉塞信号機への適用を考えれば108.5kHz×2第2パターン発生コマンドで同時に-SFのY現示速照を行うことは有効だから判断は難しい。
- コマンド体系の異なる入替制限などは、2番目の地上子が不作用73kHzの場合、次の30m以内に設置の地上子と干渉して他のコマンドに化ける条件性があるとして厳しい設置位置制限がある。それは地上子の後方側のみを切り換えるから生ずるので、2個共制御して共に不作用にすれば大幅に緩和されるはず。
安全確保に最高冒進速度抑制が必須
変周式(共振周波数式)であるATS-Sxをそのまま拡張して位置基準車上演算速度照査(パターン)方式を安価に実現するというのは、技術的にはコロンブスの卵であっても実用上有用な技術であり、最高速度からでも冒進がなくなることで飛躍的に安全性を高め、また高機能だが高価なATS-Pの値段を引き下げ普及を促進する力となった。だが、ATS-P換装を公約したJR東日本とATS-B区間を中心に換装したJR西日本以外のJRの欠陥ATS−Sxは若干の補足改良に留まっている。これに根本改良を迫り、衝突追突事故被害を抑制するためには、地上設備の増設が基本的に無用で全閉塞について私鉄ATS通達(鉄運S42-11通達)の安全水準を満たせて、もっと安価にできる、ロング地上子でY現示制限照査、20秒後YY現示照査方式の水準を義務付けた方が(区間重複を許せない弱点はあっても)適するのではないだろうか。危険な高速領域防御の無視に頑迷だったJR東海がATS-PT全線導入を発表したことでもあり、私鉄ATS通達仕様の行政指導は復活の時期ではないか。
このATS−Psも地上設備の増設が必要なため、JR西日本での本線系ATS−Pの様に場内信号手前など設置が絶対信号に限られる「拠点方式」設置にされており、非設置の一般閉塞信号には無効である。
| 位置 TBL-2 | 共振周波数[kHz] | 機能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前置 | コマンド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 停 止 パ タ ン a | Ps-1 | 80 | 第1Ptn | 出発・ 閉塞 信号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long | 108.5+ | (130) | 勾配補正 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ps-2 | 108.5 +108.5 | 第2Pt ST速照 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ps-3 | 108.5+ | 80 | 100mPtn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stop | 123 | 即時停止 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLR-a | 103 | a消去 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定 速 制 限 | 入替 制限 | 108.5+ | 95 90 | (鉄電協) (up資料) | 25k=2m 45k=4m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 誘導 | 108.5+ | 85 | 連結off | 15k Max 電源断 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 停止 | 103/123 | 消去 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 停 止 パ タ ン b | Ps-1 | 95+ | 80 | 第1Ptn | 場内等 重複 箇所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long | 95+ | (130) | 勾配補正 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ps-2 | 95+ | 108.5 +108.5 | 第2Pt ST速照 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stop | 95+ | 123 | 即時停止 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLR-b | 95+ | 103 | b消去 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 速 度 制 限 | 分岐 | 90+ | 95 | 自動消去 | パターン 生成= TBL-4 臨時 | 90+ | 90 | 消去 | 2m 間隔 曲線 | 90+ | 85
| 勾配 | 90+ | 80
|
|
非 | Ps 抑 止 ST速照 | 85+ | 108.5 | +108.5 P2誤発生 |
103kHz | マスク ★73kHz適 Sn速照 | 85+ | (123/130) | Sn速照★
| 誤出発 | 95+ | (123) | Sx即停★
|
| Nop | 73kHz | Ps地上子試験用
|
| Ps/Sx | 切替 90+ | 108.5
| 工事区間4m、 | 有効2m間隔 不動作時:
下線=103kHz 上線=73kHz | ★:不動作時周波数を73kHzとすれば 非Ps識別地上子不要。増設の便法
| Sx | Long |
| 130 | S,Sn,Sx | 警報 Sn | 123 | Sn,Sx | 即時停止 ST/Sx | 108.5+ | 108.5
| Sx車上タイマ速照 | Ps-2:第2P発生兼 Nop | 103 | S,Sn,Sx地上子試験
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- ※ 108.5+108.5kHz 間はPs2地点でのSx速度制限
- ※ テキストでは、パターン発生Ps-1使用例は80kHzのみで85kHzは不詳。
- ※ 重複パターン用のbパターンはマーカは表2(3-7)と本文では95kHz、図3-15では90kHzとされるが図3.15、90kHzが誤植の模様。
入替制限でM3:108.5kHzもマーカに使っているが、他は速度制限マーカーM1:90kHzと、重複bパターンを区別するためのマーカM2:95kHzで、勾配補正を伝える。
- 108.5kHz×2個:内法/車上時素=ATS-Sx速照とPs 第2パターン発生が同一コード
Psモードで車上時素速照のあるSx区間に入線しても、Ps地上子がなければSn・モードで動作する。
ATS-SF/-ST速照との区別は、第1パターン発生を条件にして第2パターンを発生させている。この区間内に-SF車上速照が設置されると誤動作となる。
[回避措置]:作業資料に拠れば-SF速照取消地上子85kHzを直前2m前後に置く。それにより108.5/103kHz双方を-Psモードで無効とする。
ATS-Pの休止コマンドに似た「工事中区間」コマンドで強制的に-Sx←/→-Ps切替は可能である。
- 108.5kHz×2個:内法/車上時素=ATS-Sx速照とPs 第2パターン発生が同一コード
ATS-Ps 地上子設置位置・間隔
勾配別-Ps地上子位置 <TBL-3>
| −勾配 パーミル | 設置位置m | 勾配マーカ 間隔 [m] | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ps1 | Ps2 | |||||
| 平坦 ≦5 | 655 | 390 | − | 不設置 | ||
| ≦15 | 775 | 455 | 2 | 1.0〜2.7 | ||
| ≦25 | 970 | 560 | 4 | 3.3〜4.8 | ||
| ≦35 | 1,350 | 765 | 6.5 | 5.7〜7.2 | ||
- 「マーカー地上子+ロング地上子」として勾配設定。
- ロング地上子は130kHz/129.3kHz。
- マーカー地上子は5/1000以上の勾配で設置し、
- パターンa:108.5kHz、パターンb:95kHz
| 区 分 | 設置間隔 [m] | 速度制限地上子#2 | (1秒仮想)km/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準 | 許容範囲 | 分岐 +95 kHz | 臨時 +90 kHz | 曲線 +85 kHz | 勾配 +80 kHz | 間隔 | −0.5m内法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 22.5 | 21.8〜23.3 | 25 | 25 | 40 | 35 | 81.0→80 | 79.2→75
| 6 | 18.5 | 17.9〜19.4 | 35 | 30 | 50 | 45 | 66.6→65 | 64.8→60
| 5 | 15 | 14.4〜15.9 | 40 | 35 | 60 | 55 | 54.0→50 | 52.2→50
| 4 | 12 | 11.5〜13 | 45 | 40 | 70 | 65 | 43.2→40 | 41.4→40
| 3 | 9 | 8.3〜9.8 | 50 | 45 | 80 | 75 | 32.4→30 | 30.6→30
| 2 | 6.5 | 5.7〜7.2 | 55 | 50 | 90 | 85 | 23.4→20 | 21.6→20
| 1 | 4 | 3.3〜4.8 | 60 | 55 | 100 | 95 | 14.4→10 | 12.6→10
| 0 | 2 | 1〜2.7 | 制限解除 | 7.2→−
| | |
| ― | ≧25 | 第1地上子受信取消 |
| 照査速度は制限速度+10kmに設定
| | |||||||||||||||||||||||||
- 直下地上子は信号約20m手前に設置。
- パターンbマーカは、勾配を除き手前約2mに設置。
- 第2パターン発生地上子間隔はATS-SFでの赤信号に対する制限速度に設定できる。
(?現実には?無記載だが最大45+10km/h) - ※ Ps1距離m、勾配(1000分率)は最大値
平坦地での地上子設置位置は概ね、
Ps1=655m、Long=600m、Ps2=390m、Sn=20m、
- パターン消去は、制限区間終端に2m間隔での同一地上子組合せ。
- 分岐制限のみ50m走行で自動解除。∴解除地上子設置無用。
- 注: 右端の地上子内法の制限数値の方が自然だが、何等かの理由で逆順割付となっている?
| 構造 | 型名 | 共振周波数 kHz | 機能 | 接続図 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 停止信号 | 非停止 | ||||||
| 2 値 地 上 子 | 落 下 接 点 | Ps-R1 | 73 | 85 |
パターン2 マーカー1、2 ★'太字:落下側 | 
| |
| Ps-R2 | 90 | ||||||
| Ps-R3 | 95 | ||||||
| Ps-R4 | 73 | 103 | −/取消 | ||||
| Ps-R5 | 80 | 103 | 第1パターン発生/取消 | ||||
| 動 作 接 点 | Ps-N1 | 80 | 73 | 第1パターン発生, | 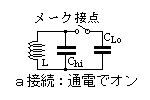
| ||
| Ps-N? | 90 | 73 | M1,臨時 | ||||
| Ps-N? | 95 | M2,分岐 | |||||
| Ps-N2 | 108.5 | 73 | 第2パターン発生 ATS-ST型/Ps取消 | ||||
| Ps-N3 | 108.5 | 103 | |||||
| Ps-N4 | 123 | 103 | ATS-Sn型 | ||||
| Ps-N5 | 130 | 103 | ATS-S型 | ||||
| 固 定 地 上 子 | 固 定 周 波 数 | Ps-01 | 80 | 勾配,第1パターン | 
| ||
| Ps-02 | 85 | 曲線 | |||||
| Ps-03 | 90 | M1,臨時 | |||||
| Ps-04 | 95 | M2,分岐 | |||||
| Ps-05 | 108.5 | M3,ST,第2パターン | |||||
★ テキストに結構分厚い’正誤表’が付くほど間違いやすい事項だが、考え方の基本は、故障したら制限強化側、停止信号になる、電源が落ちたとき停止信号という原則でリレーのON-OFFを決めていく必要がある。
信号電源停電の場合、80kHz、130kHz、108.5kHz、123kHzが有効になり、第1パターン(80kHz),第2パターン(108.5z×2)が発生し、直下が非常停止となって安全側で停止する。
速度制限の場合は、停電で制限が掛かる構成とする。
その原則に従いパターン取消地上子Ps-R4、-R5は制御電源ONで取消、OFFで不動作・無効&第1パターン発生となっている。Ps-Nxも同様である。
|
mail to:
|
 ATS・ATC |

|
 小目次 |
 主目次 | |
| Last update: 2007/04/25 2005/09/17 (05/02/18作成) | |||||