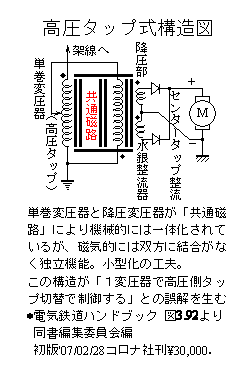 (�}3.92����,���L153�Q��) |
|---|
�@�𗬓d�C�@�֎Ԃ́u�����^�b�v����v�\���́A�����̒P���ψ���̂Q�����^�b�v�œd���������A���i�̍~���ψ�����o�Đ�������Q�g�����X�\��(�}3.91)�����A�ԍڗp�̂��ߏ��^�y�ʉ���}���ċA�����H�����ʂɂ��Ĉ�̉������\���}(�}3.92�F�E���})���Љ��Ă����B
 �@���ʎ��H�̗㎥�����͑��݂ɔ��]������Ɨ��ψ��킪��������͓��e�ʂ����A�P���ψ���Ȃ̂Ŏ������ő�o�͎��łقڃ[���A�ő厞���~���ψ���e�ʂ̂P�^�S�o���ŁA�o�͓d���[���ƁA�ő�o�͎����~���ψ��푤�̍ő厥���ɂȂ�A���݂ɋt�����㎥�Ƃ��Ă��邩�狤�ʎ��H���͍~���ψ��핪�̒f�ʐςōςށB���̂Q�g�����X����̉�����ē��ʍ����P���ψ���Q������芷������������ĂP������芷���Ă���Ƃ̌�����������ēS����������Ȋ������Ɗm�M�����B
�@���ʎ��H�̗㎥�����͑��݂ɔ��]������Ɨ��ψ��킪��������͓��e�ʂ����A�P���ψ���Ȃ̂Ŏ������ő�o�͎��łقڃ[���A�ő厞���~���ψ���e�ʂ̂P�^�S�o���ŁA�o�͓d���[���ƁA�ő�o�͎����~���ψ��푤�̍ő厥���ɂȂ�A���݂ɋt�����㎥�Ƃ��Ă��邩�狤�ʎ��H���͍~���ψ��핪�̒f�ʐςōςށB���̂Q�g�����X����̉�����ē��ʍ����P���ψ���Q������芷������������ĂP������芷���Ă���Ƃ̌�����������ēS����������Ȋ������Ɗm�M�����B�@�܂��A�X�R�b�g�s�����̂Q��ނ̃g�����X���A�����H���ʍ\���ň�̉������^��}��A���ʕ�����Q�{�̒f�ʐςƂȂ��Ă��邱�Ƃ��Љ��Ă���B(P543�}7.136)
�@�R���g�����X�ɂ͌����I�ȂT�r�������A�����H�����݂ɋ��ʉ��őł����������ă[���ɂȂ�ȗ����đ��݂��Ȃ��R�r�����̂��瑽������A�A�����H���ʉ��Ƃ����͓̂d�͗p�ψ���Ƃ��Ă͏펯�I���z�Ȃ̂�������Ȃ��B������̐l���m��Ȃ����������Ȃ̂��B('07/03/11)
�@�G�A�Z�N�V����������ċA�����ɕt���Ă���(P540�}7.127)�B���}��P530�}7.104(�E�}�������})�ł���̋A���ɒ���ɃR���f���T�[��}��������̂̂͂��B�g�����[���ɐݒu����̂����������A�}�������Ă���r���ō������Đ��H�Ƃ̐ڑ����t�ɂȂ����̂��^�����낤�B�uBT�^�d��H�ɂ�����≏�����v�}(p571C2�}7.211)���}7.104�Ɠ����\���ł������S���q�H��n���������ڋ��d���̋A�����������Ƃ��Ă���\�������܂����B('07/03/22)
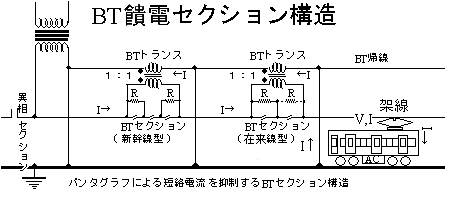
| |
�y(BT�^�d�@�Q��)�z �ϓd�����߂̒��ڋ��d���̋A���R��̋^���B�v�ۓc�����獑�S���q�H��n���҂̌����}�͉��}(Wikipedia�L�����)�A���͏�}�B |

|
�@�u�t�f�q�T�C���X�^�v�Ƃ͕ϊ��~�X���t�j�~�T�C���X�^��GTO�T�C���X�^�̂��Ƃ��낤�B�d�q�G���S���ł͂Ȃ���ʕҏW�҂ɔ�������Ƃ����ɂ͂������e�����A�Z���o���̂Ȃ��Z�p�҂ɂ͂Ȃ��Ȃ����t�����Ȃ��B�܂��A��ނȂ��Z���R�ꂩ�B('07/03/25)
�@�t�d���T�C���X�^�Ƃ́A�t���[�z�C���_�C�I�[�h�ƃT�C���X�^���ꕕ�~�̕����f�q�̌ŗL���i�����낤�B����̓X�y�[�X�ȗ��E��t�ȗ����������K�{�̑f�q�ł͂Ȃ��A��ʓI�f�q���ł͂Ȃ��B����ň�ʖ��������Ă���̂Ȃ��ނȂ�����ʐ��̓_�őf�q���Ƃ��Ă͍������₷���g�������Ȃ����̂��B3.1�͎��M�����̕x�m�d�@�ŗL���i�������̂��낤���H('07/03/25)
|
���ǎґΏہ� �d�C�S���Ɋ֘A�����ƁC�����@�ւ��Z�p�ҥ������ �d�C�S���Z�p���w��ł�����w���E��w�@�� �����s�̂��Ƃ�(����) �@�{�n���h�u�b�N�͓d�C�S���Ɍg���C�e����̐��Ƃɂ��ψ�����\�����C�����ɂ킽����e���ᖡ���āC��w�C�s���@�ցC�S�����ƎҁC���[�J�C�R���T���^���g�Ȃǂ̑����̌����҂�Z�p�ҁC��S�j�\���Ɏ��M�����肢�����B �@�c�c�c�@�Z�p�����Ƃ��āC�S���W�̎�v�Ȋ�Ɗe�ЂɁC�ŐV�̋Z�p�����̏Љ�����肢�����B �@�@�@�ďC��\�@���i�F��
| ||||||||||||||||||||
�@�����ł͓d�@�q�`���b�p�[�̉����ɂ��āu�c�c��d���@�̔����d�����d�Ԑ��d������Ⴍ�}�����K�v�����邽�ߍ�����̉d�͂��}����ꂽ�v�ƂȂ��Ă��邪�A�������́u�c�c��d���@�̔����d�����d�Ԑ��d��+�^�d���~�����ɌŒ肷���K�v���������߁c�c�c�v���낤�B ('07/03/25)
�@ATS-P���p�J�n�����S���ゾ�������A�������cJR��('87/04)�ゾ���������n���h�u�b�N�̋L�ڂł͂ǂ����s���Ă��B'87�N���p�ƂȂ���JR����Ǝ���\�L�ɂȂ��Ă���(P624�}8.6�N�\1987�N,P675C2L-11)���A�]�O�́A���c������Ă���̏��F�葱�����ώG�ɂȂ邽�߁A�������ł����S�̂����ɋ��p�J�n�����F��JR�Ɏ����������Ƃ��ĊJ�����}�����Ƃ���Ă��āA���S�����'86/12���p�Ƃ���Ă��邪�A���̎����^�p���Ԃ͕K�v���낤���A���ɏ��̑S��ATS-P���������t���ł͊J�ƑO�ɂ��Ȃ�̊��Ԏ��^�]���J��Ԃ��Ă��邩��A���S���ソ��'87/03/31�܂łɔF���̂��낤���H�J������͎�����J�n�����Ƃ���'86/12�������A���F�K�肪��݂ł̋��p�J�n��'87�N�Ȃ̂��낤���H���̂�����͎c�O�Ȃ���s���m���B�S�d�����uATS�EATC�v�ł�ATS-P�ډŁu'86�N������g�p�v(P70L2)�u���S�����Ɂc�c�c�J�����ꂽ�v(P50L17)�Ƃ��邪�A���_��(P5L13)�ɂ�'87�N�Ƃ����ăn���h�u�b�N�ƈ�v����B�Z�p�I�ɂ͊W�Ȃ����u���S�J���v���炢�͖��L���ė~�����B ('07/03/26)
�@ATS-P����ōł���a�������镔���́u����JR�ł͂��ꂼ�ꑽ���قȂ�^�C�v��ATS-P���̗p���Ă���v(p676C1L1)�Ƃ����L�q���B�����e��Ƃɒ��������̓I���i��\���Ō������̒ʂ肾���A���S���u(�ۈ����u)�̉���Ƃ��Ă��̓����ǂ��ꍇ�ɂ́A����R�[�h(���d���F���S��)�Ō����ׂ��ŁA�����JR�V�Ђ̋��c����ŕۈ��R�[�h(�M�������d���Ȃ�)�͋��ʂɂ��Ă���A�H���ʂ̓���ȕ����ȊO�͌������ʂł���B[�Q�Ɓ�ATS-P�R�[�h����]
�@�B��AJR�����{�݂̂��̗p�����R�[�h�͎Ԏ�ʂ̋��e�s���J���g�ʂɍ��킹���x�����ɉ��Z���镔�������ł���A�ݒ莞�Ɂu�{���{���v�Ƃ���ƁAJR�����{�Ԃ̐������������Ⴍ�Ȃ邪�A+0km/h�ݒ�ł�JR�����{�Ƃ̍��͂Ȃ��R���p�`�ݒ�ł���B�����{����莖�̑Ή��Ƃ��ā{�����̊g�������߂��̂Ō����̓������ݏ�����ɂ͎x��Ȃ��Ȃ���
�@�u�قȂ�^�C�v�v�Ƃ����̂́A����R�[�h�ɂ�铮������������镔�����A�v���̍l������v�����ɂ�����\���i�ŗl�X�ɈႤ�����ŁA����͖{���I�Ⴂ�ł͂Ȃ��B
�@�Ⴆ�A�J�����̌��X�̍\���̓G���R�[�_(���M�����ݒu��ATS-P����8085CPU�{�[�h�R���s���|�^)�Ŋe�n��q�̔����鐧��R�[�h���쐬���Ă��邪�AJR�����{��ATS-PN�ł͊e�n��q�ɐM���������̐���R�[�h���������A�����ɋ��郊���[����ŗ\�ߏ��������R�[�h��I�����đ��o����\�����̂��Ă���B�ԏォ�猩��R�}���h�Ƃ��Ă͂ǂ�����ς��Ȃ��B���̕ۈ��R�[�h���ʂɐG�ꂸ�Ɂu�����قȂ�^�C�v��ATS-P�v�ƌ����Ė���Ă͌�����g���邾���ō���B
�@�����P�_�AATS-P�ݒu�H��������̂�JR�����{�A�����{�̂Q�Ђ݂̂ŁAJR���C�Ɖݕ���ATS-P���ڎԗ������݂��邾���B���Ђɂ͍̗p����Ă��Ȃ����Ƃ͐G�ꂽ��ǂ����낤�B���C����莖�̂�������ATS-PT�����d�l�����������B
('07/04/08)
�@���s�g�����X�|���_�^ATS-P�n��q�ł́A�ڕW�_�܂ł̋�����t���p�����^�[���ԏ�ɑ��M���铮�삪��{�ł���A�������Ƃ����͖̂����B�Ƃ��낪���p�Ƃ��ĐM���@��650m�قǎ�O�̒n��q���u�p�^�[�������n��q�v�A����ȍ~�ݒu�̒n��q���u����n��q�v�A���̂����ł��M���@���̂���(25�`30���ʒu)���u�����n��q�v�ƌĂԂ��A���̓���Ɂu����v�͂Ȃ��A����R�����ł̔�퐧���ȊO�͋����Ȃǃp�����^�[�̍Đݒ�ł���B���̌ď͓̂S�d���e�L�X�g�uATS�EATC�v��ATS-P���_���̋L�q�����A���e�Ƃ��Ă�ATS-Ps�⋌�ώ���ATS-P�̉���ƍ������Ă���B�����̏ڍד��������ł͍Đݒ蓮��Ƃ������Ȃ������������Ă���B
�@���̕����ɕt���n���h�u�b�N��p676C1L12�`(2)�A����
�u�A�M���@�̊O��(��O)�������ɒn��q���ݒu����Ă���B���̒n��q�̏���Ԃ��ʉ߂���ƁC���p��ɋL�^����Ă���O����R�����M���@�܂ł̋�����̑����ԏ�ɓ`�������B�������O�̐M���@��R�����łȂ��Ƃ��́C���̌����R�����M���@�܂ł̋��������Z����ē`�������v
�Ƃ��čX�V����ł��邱�Ƃ���̓I�ɏq�ׂ邱�ƂŁu�������v��ے肵�Ă���B�����ƃn�b�L�������Ηǂ��̂ɂƎv�����A����čL�܂��Ă��܂����uATS-P����n��q�v�͊��p��Ƃ��Ă��̂܂c���ďՓ˂�����A�V�l�q���R�I�ʂɂł��g����̂��낤���H�u�ȂʁIP�̎�����삾�ƁI�H����x���������ė����I�v�Ƃ������Đ�y���𐁂���w�@�@�@ ('07/04/08)
�@���݂̔��f�Ȃ�AATS-P�R�[�h����ɒ����n��q�̂ݑo�����ʐM�Ƃ�����PN�\���ɏ����Ĉ����ȃV�X�e����g�߂�̂ŁAATS-P�ݔ��̂����Ђ��V�K������Ps��I�Ԃ��Ƃ͂Ȃ��������B �@�������AJR�����{�ȊO��JR������ATS-Sx�i��𑱂��钆�ł̌njR�����̈��S���w�͂��m��I�Ɉ����ׂ����낤�B������TSP�ɂ��Ă����l�ŁA���SATS�ʒB�d�l�ł͒ᑬ�̂����۔������������̂��p�^�[���ƍ������Ŗ��߂����̂��B
�@���`�̋Z�p�I�ϓ_�ł͌��ʂƂ��ė��j�I�ȓk�Ԉ����Ń{�c�Ȃ̂��I�H
('07/04/09)
�ʏ́u�f�W�^��ATC�v�Ƃ��Ĉ��|�I�ɗp�����Ă���\�����A���̓��쌴���ɑ����āu�ԏ�p�^�[�����䎮ATC�v(p686C1L4)�Ƃ��ĉ��߂Ă���̂͑�ϓK�Ȃ��̂��BATS-P�����l�����f�W�^������������D��Ă���̂ł͂Ȃ��A�ʒu��ő��x�����ƍ��p�^�[�������邱�Ƃ��D��Ă��邱�ƂقɎ��������h�����̗̍p�͑Ó��ł���B('07/03/26)
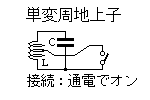 (�P�ώ��n��q) 130kHz/�|�s�� | �� �� �� |
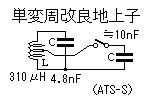 (�}�����Ή��n��q) 130kHz/103kHz |
|---|
�@�ώ��^�n��q��p�������nj^ATS-S�̉���ŁA����123kHz�n��q�̉�����u�c�c�����ɘA�������Z��������悤�ɂȂ��Ă���v(p678C1L1)�Ƃ���A�Z��������U�_���Ȃ��Ȃ���ATS-S���������̒P�ώ�����130kHz���U�n��q�ƁA�����p����ꂽ��^�n��q�̐����Ƃ��Ă͐��������A�嗬�̏��^�n��q�ł̓}��������ɍ��킹�Z���ɑ���R���f���T�[��ڑ����ċ��U���g����103kHz�`105kHz�ɗ��Ƃ��Ď����Q�ώ��Ƃ��āA��^�n��q�����l�ɉ������Ă��邩��A����ɑ���������ł͂Ȃ��B�uLC���U�^�n��q�v�́u�P���n��q�v�Ƃ��āA���̎�M���@�Ƃ��ď]�O�́u�ώ����v���AJR�����{ATS-Sw2�ɍ̗p����FFT�����i�X�y�N�g�����g�U�����A���ߎ��g�����͕���)���Ƃ������Ƃ��낤�B('07/03/27)
�@�V�����ʼnߑ��]�T�̕s������ꏊ�ɐݒu����Ă����n�㎞�f���ߑ��h�~���u���\�������Ԏ����m���u�̍\��������ڂ��Ă���B�Q��ނ̕���������A���[����������R�C���Ԃ̌������ԗւ����߂�u�U�������v�ƁA�����g�̂��ߎՒf����u�Օ������v�Ƃ�����Ƃ��Ă���B�V�������U�����A�Օ����̂ǂ��炩�͋L�ڂ��Ȃ��������A���ɉe�����Ȃ��Ɨ�����Ȃ̂Ř_�����x���o�͒[�ł͂ǂ���ł����Ȃ��B�����ڋ߂��ĂQ�g�ݒu���āA���s�����ٕ̕ʂ��s���B����܂ł��̍\�����͌��t�����Ȃ������B('07/03/27)
�Ԏ����o�� 07/12/22 �����w#16 |
���d���f���Ǝ� �ߑ��h�~���u �@�@<OverRun>  OER�����u�V���w �P�ώ�7�n��q�� �}8.122���� |

|
 �����V�h�w���R�Ԑ��� 15�n��q�ߑ��h�~���u (�n�㎞�f����) �}8.123�ʐ^������ |
 �����a�J�w���P�Ԑ� |
�@���c�}�ߑ��h�~���u�ݒu�}���H
�@���o���̂���ʐ^�ƁA�}�ʁI�Ǝv�����̂��Ap678�}8.123�I�[�w�ɂ�����ߑ��h�쑕�u�ʐ^�������V�h�n���w#3�Ԑ���15�n��q(�P�^)�ߑ��h�~���u�ƁA���c�}�������u�V���w�ȂǂɌ�����7�n��q���ߑ��h�쑕�u����}��:�}8.122�BATS-ST���Ƃ��g�����ߑ��h�쑕�u���}8.124�Ƃ��Čf�ڂ���Ă���B����͓S�d���́uATS�EATC�v�ɓ��R�f�ڂ����ׂ�����}�������i�ʐ^���N���b�N����Ɖ���y�[�W�j�B
�@15�`16�n��q�ߑ��h�~���u�́A�n�㎞�f���Œn��q���~�Ɨ�Ԍ��o���p�ɐ芷���Ďg���Ă���B �@[�����P�^�Q�^�ߑ��h�~���u�̉����p37 ] �@('07/03/27)

|
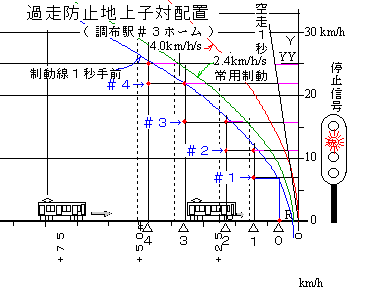
| |
�@�������Ȃ���A�����e�L�X�g�Ɏ�����闪�}�ł͂ǂ����~�t�߂̑��x�Ȑ����A�r�������Ȑ��Ƃ��Ă��̂܂ܓ\�������̂�p���Ă��āA����͂��́u�d�C�S���n���h�u�b�N�v�̋L�ڂł����P����Ă��āA�u�S���ƊE���̐����}�v�ɂȂ��Ă���B(p682�}8.130,�@p684�}8.132,�@p687�}8.136��)
�@�������A�{���̌����Ȑ��͂P�{�̕������z�������̂���{�B�ߑ��x�h��̉�́E�v�Ȃǂւ̃V�[�����X�̓K�p���l����Ό����ɍ������}�̕������w�҂قǗ������y�ɂȂ�B�����͉��߂ė~���������B���Q�l�}�̒i�K�I�����}�̕������m�ȕ\�L�ł���B
('07/03/28)
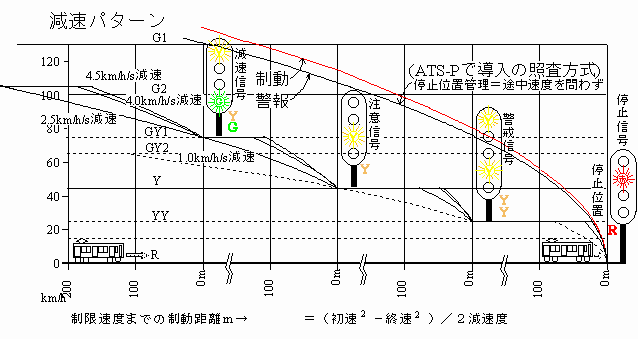 |
�@�u�R�z�V�����p���nj^��ATC-1D�^�v�Ƃ����L�q�ɏے������l�ɁA�V����ATC�j�Ƃ��̖��̂�����ӂ₾�B�R�z�V����ATC�Ƃ�����-1B�^��-1W�^�ł���-1D�^�ł͂Ȃ��B���̉���𗎂Ƃ��Ȃ��̂ł͂Ȃ����낤���B�X�̓�������ɂ͌��͂Ȃ����A�V����ATC���݂̂S�厖�̂Ƃ̊֘A�Ɛ藣�����܂��M���邩�炱�̂悤�ȏȗ��G���[�ɂȂ�A�Z�p�I�Ȑ������܂Ŗ������Ă��܂��B����JNR-ATC����L���u�V�����ɂ����鑽�i�u���[�L�������ATC�̗�v(p682C2�`p683)ATC-1A/ATC-1D���{�����̖ڗ��G���[���낤�B
�@�ΏƎ����Ƃ��ċ��ɓS���d�C�Z�p����A�M���T�_[7]�uATS�EATC�v��[11]�u�V�����M���ݔ��v�ɌX�̕����̋L�q�����邪�A����_�I�ɂ܂Ƃ߂邱�Ƃ����܂������Ȃ������̂�������Ȃ��B���Y8.3�͂̎��M�҂��u�������s��ʋǁv�Ƃ���A����8.1�́A�M���V�X�e����ʂ�A��Ԗh��̈ꕔ��S������Ă��邪�A�V�����̎�����S���������S�W�ł͂Ȃ��A�o�ܐ������O���Ă��܂����̂��낤�B���̏͂͂�͂�V�����M���W�҂̎��M�ɂ��ė~���������B
�@�V����ATC���ǂ̎��Ƃ��Ă�ATC-1A/1B�^�R���p�`�Q���g�����őS���W�������Ƃ���ATC-1D�^�̃|�C���g�Ƃ��̎R�z�o���G�[�V����ATC-1W�^�Ƃ����`�ɐ�������A�i�}���q�ׂĂ��錹�����uATS�EATC�v�Ɓu�V�����M���ݔ��v�������Ă������̂��A�c�O�B
�@�����������́A��z��R�z�Ő��E�ō��c�Ƒ��x�˂炢�Ƃ�������A���邢�͉c�Ə�̓s���Ŏԗ����̍ō����x�̓Ǒւ��s��ꂽ����A�V�X�e���Ƃ��Ă̊���x�ƁA�Ǒ֗�O���x���ĕ\�����ĖႦ��ƃV�X�e���Ƃ��Ă͐�������ĕ�����Ղ��Ȃ����B
�@������q�ׂĂ��d���Ȃ����AATC-1A,-1B����ATC-1D�ւ̉��ǂɍۂ��A110km/h�ȏ�̐������x���{10km/h�`�{20km/h�Ƃ��ꂽ�̂́A�������u�Ƒ��x�v���̈��萫����ŁA������x�����߂ɉ����ł������߂ƍl������B70km/h������#18�ԕ���̉�G���炭�鐧�����x������A�������\�ɂ͊W���Ȃ����A30km/h�����́A�����d�Ԋ�n�`�i�E�����̑Ή���48m�������Y���O����H�O3�M����Ԃ�50m�ɉ������o�܂�����Ō�̖`�i�j�~����35km/h�����ɉ��߂�قǂɂ͌����Ȃ������Ƃ������Ƃ��낤�B
('07/03/22)
�@ATC��`�ɂ��āu�@��v��̌��i�Ȓ�`���咣����������������A�^�A�ȓS���ǂ����g���l��ATS�ɂ��A�ԏ�M����ATS�͔F�߂��Ȃ��Ȃǂ̕ςȃN���[����t����ATC-L�^-1F�Ƃ������B�@�֎ԗ�Ԃɍ̗p����Ă��鎩���u���[�L���L�̍��ߕs�����̂�h���ɂ͔�퐧���������{������A�uATC�̃n�[�h���g����ATS�@�\�v�������Ȃ̂����A�ē��̌�Ќ��ŁuATC�v�ɂ��Ă��܂����B��̓d�ԓ��}�͕���Ȃ�ATC���B������uATC�Ƃ����p��͍L���g���Ă��邪�A���̈Ӗ��͂��Ȃ肠���܂��ł���v(p679C2L8)�Ƃ��Ă���B�Z�p���̊��o�ł͓��R���B���[���b�p��ATP(Automatic Train Protection)�ƌĂ�Ă���Ƃ��A�Ă�ATS�Ɖ]����Automatic Train Supervision��ԊĎ��@�\ATS �ƏЉ���e�̈Ⴄ�a���p��ł��邱�Ƃ��w�E���Ă���B ('07/03/30)
�@1941�N�̎R�z���Ԋ��w�}�s��ԒǓˎS�����@�ɁA�A���R�[�h��ATS�𓌊C���A�R�z�A�������{���ɐݒu����H�������āA�^�p�ԋ߂Ɏԏ��M�@�����q�����őS�����v��������ꂽ����ATS��t�u��āv�ł͂Ȃ��A�u�ݒu�H���v���s��ꂽ(p627).����p669�̉���\8.14�uATS�̎�ށv(�A�����䎮/���p���g���O����H�f��������)�̉�����ɂ����c�c�c�킪���ő����m�푈���C������Ԑ��䑕�u�Ƃ��Čv�悳��C���C�ԓ��M�����p��ATS�Ƃ��Ďԏ㑕�u4���C����юR�z�{����i�`�����Ԓn�㑕�u�������������C�i���R���߂Œ��~������ꂽ�Ƃ����Ƃ��čŏI�I�ɂ�GHQ���߂Őݒu��f�O�������Ƃ��L����Ă��āu��āv�ɗ��܂�Ȃ��������Ƃ������Ă���B ('07/03/30 &4/16)
�@B�^�ԓ��x�u��ATS-B�ł̒�~�M���ԏ�`���@�Ƌ��������ɂ��āA�M���d�����u��T�b�ԎՒf�v����(p670C1L8,L11)�u���̂T�b�ȓ��Ɋm�F���삪�s���Ȃ������ꍇ�ɁC�����I�ɐ�����������悤�ɂ����̂�ATS-B�^�ł���v�Əq�ׂĂ���̂́A�`���@���P�b�ԎՒf�A���̌�̋��������^�C�}�[���T�b�ݒ������������肾�B���ꌴ���Ō�����`�����鋞�����l�s�c�P���^ATS�ł�0.8�b��3�b�Ɓ�(�f)�œ`�����Ă���B�������Ă��Ă����X�������鏈�����璍�ӂ��čZ�����ĖႢ�������́B ('07/04/16)
�@�}8.151�̃|�C���g�Ԑ���`�}�ƒ�`���̂����E���́u�Ɓ��v�̎��́A�|�C���g�Ԑ�#N���̊ԈႢ���B��s�Ƃ̌q����ł́u�Ɓ��v���폜����n�j�B
�@�@# �m��(1/2)�Ecot(��/2)���P�^�Qtan(��/2)
('07/03/30)
�@�ː��̔g�Քg���̌������q�ׂ�͂ŁA�p���^�O���t�W�d�V���[�Ԋu20cm�ƁA���̂P�^�Q��10cm�Ə����ׂ������A���O�̖��Ւlmm�Ɉ���������mm�Ƃ��Ă��܂����B����̍H�w���Ȃ�mm�\�L�œ��ꂵ�ăG���[������h���ł����͂��B���̕ӂ͕s�Ǖi�̎R�ɒǂ��|������o���̂Ȃ������Ҍ^�̕��������ł͂Ȃ��̂����m��Ȃ��B(p473C1L6) ('07/03/30)
���@ EH200�F�i�������o��ŁH�j�����ؑւ̖͗l�@�@�@<EF200>
|
�yEF200�zJR�^�d�@�����X���yM250�n�z http://hobby9.2ch.net/test/read.cgi/rail/1173068730/168n 168 �Fama ��2P6zxky1H. �F2007/04/19(��) 01:15:39 >>166 ���C���o�[�^��������̋@�֎Ԃ́C���z��Ԃ̈ꕔ�������C�p���^�_���͓d���𐧌����Ďg�p���Ă���B �����EH200�̂��Ƃ���Ȃ��ł����H���z��Ԃœ��͓d���l�̐ݒ���蓮�ŕς��Ă܂��B EF200��>>159�̂悤�ȉ����͌������Ƃ����������Ƃ��Ȃ��ł��ˁB |�c��.���O(�����ɏd�݁A�Ƃ̎��Ȃ̂ŋv�X�Ƀg���b�v��) |
�@EH200�Ɏ蓮�̃p���^�_���͓d�������ؑւ�����A������w���Ă���̂ł͂Ȃ����HEF200�ł͏o�͂��グ�Ă��N�������͂͑傫���Ȃ�Ȃ��BEx�D�������o��H(07/04/20)
�@���w���ɉ]�킹��Ƃ������u���K���v�A�d�C���͂�����u�ʎq���v�ƌ�p����\���ŁA�u�������������������x�����v(p469�}6.49)�Ƃ��������O���t���A�ː��̔g���`�d���x���P�Ƃ��Đ��K�����Čf�ڂ���Ă���B�S��������́u���������v�Ƃ����̂��I�d�C�ł̓t�B���^�[�̐܂�_���g�����P�Ƃ��Đ��K�����ĉ�͂��v����ȂǗǂ��g����@���B ('07/03/28)
�@�W�d���E���x���ː��̔g���`�d���x��70%���x�Ƃ͕����Ĕg�����x�����Z���Ă������A���̑��Ɂu�����p���^�O���t�̊��E���U�v�Ɓu�p���^�O���t�̃V���[�̐U���v�Ƃ����Q��ނ̑��x�ŗ����̃s�[�N�����邱�Ƃ��Љ��Ă���B���ꂼ��̗v���͂Ƃ��Ă͓ǂ�ł������A���x�̈�̈قȂ鋤�U���ۂƂ͎v������Ȃ������B(p39�}1.65)
�@�g���`�d���x�̘b�͋O���\���ɂ��o�Ă��āA850km/h�`1,000km/h��������Ȃ��Ƃ��邪�A�����Ɍ��ݎ������̎��C����S��581km/h��̘b���o�Ă���̂͏�Ⴂ�ȋC������(p76C1L8)�B����ɂ��O���̔g���`�d���x�͊W�Ȃ��Ȃ�̂ł͂Ȃ����낤���B���̑����C�̔g���`�d���x�������̕ǂ������͂��߂�B ('07/03/28)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���e�s���J���g�ʐ��� | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| �s���J���g�bd | ���ύt�J���g�bb�|���J���g�b | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (�ȗߎ�)�umax | ����(127�q(�b�{�bd)�^�v)| (�ȗߎ�)�@�bd
| ���v2�^�Qa�g���v2�^�W�g
|
�bd��60mm���ʎ�,70mm������,110mm�U��q��
| �v�F
�O�ԁA�g�F�d�S���A�b��105�F1,067W
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
�@�A���A�Ԏ�ʂ̋��e�s���J���g�K�i�͓��}��70mm�C95mm�C105mm�ł͂Ȃ��A���S����̍������Ő��肵��60mm�C70mm�C110mm(�����ʁA���}�A�U��q)�̔������A���̑���͉������痈��̂��낤�H���̌�������������̂��낤���H'05�N�̓�莖�̎��_�ł͕ς���Ă��Ȃ��l�����H����ł̋��e�s���J���g�̃����N�������������x���ɂ͓`����ĂȂ��̂�������Ȃ��B
IGBT(Insurated Gate Bipola-Transistor)�̃`�b�v�\�����������Ă���(p238�}4.44)�B�`�b�v�\��������PNP�g�����V�X�^�[�Ƃ���𐧌䂷��MOS-FET�̕����\���B�ǂ����a���p��Ȃ���IGCBT(Insurated Gate Controlled Bipola-Transistor)�Ƃł����t���Ă����Ηl�q��������Ղ������B����ȑ�d�͑f�q�̍\���͂Ȃ��Ȃ��L����������Ȃ��������A�f�q���̂�Web�J�^���O�ɂ͌f�ڂ���Ă���A���p����Ă���ƊE�̃n���h�u�b�N�ł��̊ȈՐ}�����B ('07/03/31)
�@������Ԃŕψ���ɓd����������ƁA�����^�C�~���O�̒��������碕������g�U����������邽��BT�^�d�̋A������R���f���T�ی��H�Ƃ��ĕ���ɉߖO�a���A�N�g���ƕ��d�M���b�v��}�����Ă���Ƃ���B�Ȃ�قnj����Ă݂�g�����X�S�S�̖O�a������A�����ׂł̓p�����g���b�N��U�ɂȂ肩�˂Ȃ��B�����̑������̂���͂��ē���ꂽ�m�����낤�B
�@�d�C���ɂƂ��Ẵp�����g���b�N�A���v�͉ϗe�ʃ_�C�I�[�h���t�̒��f��p���Ďg������^�q���ʐM�A���e�i�̃A���v�Ƃ��Ă����Ă͂�����݂ŁA���C���p���p�����g�����͔����و�Ղ��Ǝv���Ă����̂����A���������ŐM���p�����d�����^�p�����g�����ō\�����Ă���(p636L8�u�����O����H�v)�Ƃ����̂̓g���r�A�������B����㓡�搶�������p�����g�������S���̓d�͂ō��������Ă����Ƃ͑�ψӊO�B�d�C�@�֎Ԃ̈ʑ�����Ɏ��C��������g�����͐���o�͂ɉ��������@����̂��̂Ŋ�{����̔��e�ł���A���قNj����͂Ȃ����A���Z�f�q�Ǝv���Ă����p�����g��������kVA�̓d�͗p�Ŏg���Ă����Ƃ́I
�@������IC�`LSI�ɂ�郁�����[���Ȋ�����܂ł̓t�F���C�g�r�[�Y�A���[�`�����������b�L���ґg�������[�A�Ƃ��ăp�����g�����������͂��B ('07/03/28)
�@��R����̊T�v�����p140�}3.35��d���@�ɉ����d���ƒ�R����(b) ������g�݊����i�Q�g�d���@�j���}�̏c�����u���͓d���v���ŕ`���Ă��邪�A����͓d���W�͎����邪��R�����͎����Ȃ��B�d���̏d�ݕt�������čl����Ό��_�͏o�邪�����I�\���ɂ͂Ȃ�Ȃ�����A��R�������������邱�Ƃ������ɂ͏��Ȃ��Ƃ��c�����u���͓d���v�ł���O���t�L����K�v�����邾�낤�B(���}�E�}�K�v) ('07/04/03)
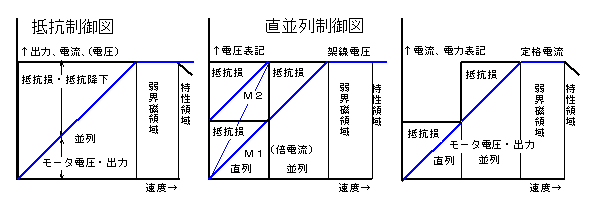
|
- �u�����V�h�w���R�Ԑ���15�n��q�ߑ��h�~���u�v�ʐ^(�}8.123)�ɂ͒n��q��12�����ʂ��Ă��Ȃ��B��ނȂ�O�r��u���ĎB���̂����炱����������J�Ȏʐ^�����߂����B28mm�����L�p�����Y(�f�W�^��18mm)�Ȃ�S�����邪35mm(�f�W�^��24mm)�ł͌f�ڎʐ^�����B��Ȃ�������������Ȃ��B�n��q��������Ă��Z�p����ɂ͉e�����Ȃ��������܂ł�����肾�B
- �������s���ڂ��̌����͂���������ƌ��ł��p���t���b�g�Ȃǂ̖Ԋ|��������ɋ��߂čēx�Ԋ|�����ł���������߂ɑo���̖Ԋ|���s�b�`�������č����g���̉𑜓x�ɗ������̂����m��Ȃ��B���������摜���������ƂɊ��ꂽ�ҏW�҂ƈ���E�l����Ƃ��Ă����Ɖ𑜓x�̗������ŏ����ɗ��߂Ă����̂����A���̂Q���͂��ƍ������B�J�^���O����̃R�s�[����ʼn𑜓x�𗎂Ƃ����Ǝv����̂����}�nEC-02�^�o�b�e���[�o�C�N�ʐ^(p867�\11.40)�B��������ăs���ڂ������Ɏv�����������B����͂ǂ�������ʼn��E�l�̘r�������o���ҏW�ґ��̖��ŎB�e�҂̘r�ł͂Ȃ���������Ȃ��B�G���ȃ\�[�X�������W����Œb�����Ă���Ɣ�����ꂽ�悤�Ɏv���B
('07/04/01)
�@�����d���@�̐������P�̋@�\�Ƃ��Ắu��Ɂv�Ɓu�⏞�����v�����邪�A���̓���͔����ɈقȂ�A�u��Ɂv���u���V�ɂ��Z�������d�@�q�R�C���̋N�d�͂��A�t�����㎥�őł������ĒZ���d���[����ڎw���A��ɂƎ�ɂ̊Ԃɒu����钼�������ɂł���̂ɑ��A�u�⏞�����v�́A�d�@�q�d������鎥�E�ɂ�蒆���_������Đ�������������̂�d�@�q�d���Ƃ͋t�����̗㎥�őł����������ŁA�d�@�q�d���ɂ��l�X�̉e����ʂ��u�d�@�q����p�v�ƌĂԁB������n���h�u�b�Np227C2L1�ł́u�d�@�q����p��}���邽�߂̕�ɃR�C���ƕ�ɓS�S�v�ƍ������Ă���B���y�[�W�}4.16�؊J�ʐ^�ł͕⏞������������}4.17�Œ�q�ʐ^�ł͕�ɂ��ǂ������Ă��邩��A������Łu�⏞�����v�̐����̂���Ŕ���āu��Ɂv�Ƃ��Ă��܂�����������G���[�̉\���������B
('09/03/31)
<Last>
2007/03/26�@23:30�L
|
mail to:
|
| ||||||
| Last Update��2009/03/31�@�@ (07/04/10�C/03/31, /26) | |||||||



