 BBS |
mail to:
| ||||
 旧 |
 新 |
 Geo日記 |
 前 |
 主目次 | |
| ||||||||||||
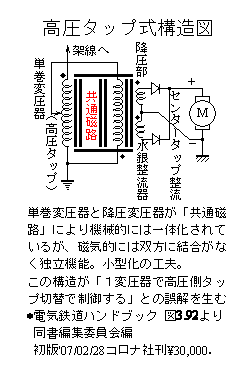 磁路一部共有一体型
磁路一部共有一体型
|
初期の交流電気機関車で用いられた「高圧タップ式制御」の構造が「一次側を切り換える」という誤った解説で席巻されて、単巻変圧器+降圧変圧器の2変圧器構成とする正しい解説をほとんど見掛けないことを日記#151で指摘したが、その誤解の原因が理解できる構造図を発見した。
高度の専門書(自然科学書、工学書等)の出版を続けるコロナ社が「電気鉄道ハンドブック」を編集委員会編著で'07/02/28初版刊行、内容は鉄道専攻学生とプロ用だ。(参照→内容メモ:鉄道工学ハンドブック)
同書図3.91(右下略図)には単巻変圧器による電圧調整部と、その後段の降圧変圧器を経ての整流器が記述されて、日記#151で既出の「制御方式入門2」P110回路図10.11高圧タップ切替式回路図、中図は上図を分かり易くするために上図表示に合わせた基本回路形を示しているが中図と下図は同じものである。初段は単巻変圧器で小型化されているとはいえ2変圧器構造ではスペースも重量も最大2倍近く(単巻構造の分減少)に大きくなるので、双方のトランスの磁路の帰線部を共通にして形状的には一体化し、その分小型軽量化を図ったものが図3.92(右上略図)の構成である。励磁方向を相互に逆にすると共用部鉄心には差分の磁束しか通らないので、最大で片側分の磁束を通せれば済むから更にその分は軽量化できる積極的な工夫である(単巻変圧器に必要な容量の算出→日記#158)。但し降圧変圧器巻線を1次2次両巻線を開放にすると過電圧を生ずる危険があり無負荷状態にしないために制御回路の工夫が必要だ。
「共通磁路を持つトランス」としてみるとスコットT結線トランスが一部磁路を共通にして一体構造で作られているものがあることも同書で述べていてトリビアであったが、考えてみれば3相トランスが独立の単相トランス3個ではなく、「5脚型」で一体化され、更に帰線磁路無用なことから「3脚型3相トランス」となっているから、電力機器設計での鉄心共通部というのはむしろ常識的な発想なのかも知れない。
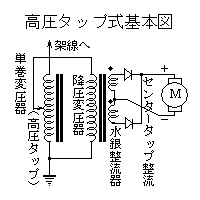
基本結線図1 
基本結線図2(標準的表記) |
|
●読者対象● 電気鉄道に関連する企業,研究機関の技術者・研究者 電気鉄道技術を学んでいる大学生・大学院生 ●刊行のことば●(抜粋) 本ハンドブックは電気鉄道に携わる,各分野の専門家により委員会を構成し,長期にわたり内容を吟味して,大学,行政機関,鉄道事業者,メーカ,コンサルタントなどの第一線の研究者や技術者,約百ニ十名に執筆をお願いした。 ……… 技術資料として,鉄道関係の主要な企業各社に,最新の技術動向の紹介をお願いした。 監修代表 持永芳文
|
| [Page Top↑] |
 表 |
 旧 |
 新 |