|
|
|
|

BBS
|
mail to:
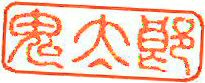 adrs adrs
|

旧
|

新
|

Geo日記
|

前
|

主目次
|
|
間違い探しでソコソコ売れると揶揄される「鉄道DATA FILE」誌 #148号、「国鉄・JRの車両−試作型交流・交直流電気機関車、& ED44型」のページ(148-7〜-12)で記事の流れとして同誌には珍しく大きなスクープが有る。
もちろん好い加減さで有名なデータファイル誌のこと、フランスからの交流機関車輸入を通産省が認めなかったという記述(P8C3−L5〜−L1)と、輸入両数削減通告でフランス側から断った(P11C2L1〜L5)という記述が並立しているし、技術解説は執筆者の変な作文が加わってどうしようもない部分も多いが、従前知られていたのは「フランスの交流機関車輸出拒否で仕方なく国産開発した」としか伝えられてなかったものを、国産を目指して開発中の重電メーカー側が通産省に国産を強力に働きかけていて、交流整流子モータ試作機が回ったことで、輸入台数を当初の10台輸入引き合いから1〜3台輸入へと大幅に引き下げて交渉を頓挫させた事実と、「ヨーロッパ交流電化視察中の国鉄派遣団に電動機開発成功を知らせ取りやめにした」ことを書いている。これはデータファイル誌には極めて珍しいスクープだ。
戦前の碓氷峠用電気機関車ED41型のサンプル輸入・デッドコピーED42型問題があるから、断られたのか断ったのかは微妙だが、形の上では断られたにしても国産化優先のために輸入台数を激減させてフランス側から断らせたようなものだ。
内容が矛盾したまま並記してどちらが正しいか分からないのはサスガ、データファイル誌!ではある。
折角のスクープではあるが、相変わらずの間違い探し本であり、執筆者が自身の根拠の乏しい推測をあたかも事実であるかのように解説している箇所が多数有り、技術的・専門的な知識がないと真偽を判断できないから、一般アマチュアに誤謬が拡がっていくのは困ったものだ。疑問点も順不同で指摘して置こう。その後の号の「鉄道用語事典」では、直流・交流電化について執筆者の余分な作文が削り取られてほぼまともな解説になっている。これまでのエラーの流れを見るとデータファイル誌は技術解説の執筆者と、その原稿のチェック体制に大きな問題が有るのだろう。
以下×がTDF誌記事の誤り。
- 直流供給電圧値選択理由の間違い(#148-P7C3L1〜4:148号7頁3段落1〜4行、−Lは逆カウントの意。以下同)
- × 直流では、放電事故などが起こりやすく危険なため送電電圧を低く抑える……
- ○ 直流は容易に変圧できないので、モータの動作電圧を電車線に直接送る必要があり、また直流機は整流子構造で更に低い動作電圧になり、これが電車線電圧を規定している。日本で直流1500V、西欧で直流3000Vが最大電圧となっている。
- 交流供給電圧値選択理由の不適(#148-P9C2L3〜12)
-
× フランスでは25000Vが採用されていたが、狭軌を採用する国鉄では特にトンネル断面積が小さく、架線と車体の間に十分な絶縁距離を取れないことから電圧を(20000Vに)抑えたと×いわれている。
× この当時は、昭和26(1951)年に京浜東北線桜木町駅構内で発生した車両火災事故の原因が×架線の短絡だったことから、絶縁対策が急ピッチで進められていた時期であったことも影響していたと×考えられる。
- ○ 交流電化実用化試験の架線電圧は、当時の一般配電用である第3次変電所と直流変電所への標準的な送電電圧である20000V(送電端22000V)がそのまま使われた。その成功で在来線交流架線電圧が決定した。
常用設備の規格品を採用すれば諸設備は新たな供用試験は無用で予備品などがそのまま流用できるので実務的に妥当な選択である。
その後、この在来線交流電化技術を引き継いで建設された東海道新幹線では、高電圧ほど送電効率が良い代わり、絶縁離隔確保の問題を生ずるので「国際標準」という理由付けでフランスと同じ25000Vを採用して若干昇圧したが、当時25000V電化はまだごく少数で、実際に欧州全土に採用されていた訳ではなかった。
当時、新幹線−在来線直通運転は全く想定していなかったので独自の選択が許容された。新幹線は当初のBT饋電方式から、現在は実質倍電圧供給のAT饋電方式に改善されて更に大電力長距離給電を可能にしている。
(See→AT饋電/BT饋電)
○ 桜木町事件の原因は架線の折損・垂れ下がりにより木造車体に地絡して発火、過電流遮断が働かず、車内にはドアコックが無く、貫通扉もなく、3段窓で脱出不能のうえ、車外のドアコックの位置が表示もなく関係者に周知徹底されて居なかったため救助の機会を失い死者106名の大惨事となったが、その対応策は車両の不燃化、車内にDコック設置と明示、貫通路設置、窓の開閉量増、変化率ΔI遮断法採用などであり、これが交流電化の供給電圧選択に影響する理屈はない。この項は作文。
- 交流電化のメリットには、
×民間の電力会社から電力供給を受けることが可能な点である。………(P8C1L3〜5)
○ 直流でもほとんどが電力会社からの供給であり、半分近くを自家発電するJR東日本だけが異例。根拠不明のデタラメ節だ!
交流電化のメリットとして、高い電圧を使えて変電所設置間隔を大きく取れる理由は、車上で走行用の電圧に降圧できるから生ずるメリットである。ひと言で言えば直流変電所を車載にしたのが「商用周波数交流電化」方式だ。(P7C3L5〜P8C1L2)
- 吸い寄せられるから赤色???
× 交流では電圧が大きいうえ、一定のサイクルで極性が変化するために周辺に生ずる磁気も強弱を繰り返し、うかつに近づくと吸い寄せられる危険性があるため、感電防止の警戒色としての意味合いも込めたものだった。(P12C1L13):下線部意味不明の作文!「吸い寄せ」は特別高圧の一般的危険性。
- 細かいが、整流子モーターの構造の呼び方は「2N極M溝」で極数2N(極対数N)、整流子片数=溝数M、ブラシ数2Nという構造になるが、P11C4L28の記述は「………整流子は14極から16極におよび、ブラシの数は50個を超える。」となっていて意味不明である。例外的な特殊構造の解説を落としているか、資料の解釈をどこかで間違えたか、間違った資料で執筆している。
4極48溝重ね巻構造図
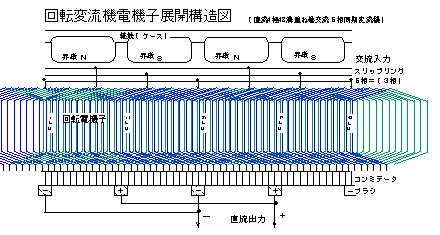
下側導体:緑色、上側導体:青色
上側スリップリング構造を削除すると電動機
|
資料もなく正答を推定しても仕方ないが、溝数&セグメント数50、極数14〜16でないと構成できない。次のページ(P12C2L4〜7)には14極〜16極とあり、こちらが正しそうだ。ED44型の解説記事中での脈絡を欠くミスは不注意に過ぎる。7〜8極対で電機子が半端な50溝とすると重ね巻ではなく波巻きの可能性が強い。因みに100KW出力程度の直流直巻整流子モータはほとんど4極で、電機子が48溝前後の重ね巻き(375V)が標準的だ。波巻き接続にすると極対数倍の倍電圧定格(750V等)になる。
- P12写真CAPTIONの「現在の主流になっている三相交流電動機とは異なるものの、直流に整流せず交流のままモーターに送る直接式の先進性は評価されてよい」とは意味不明だ。後述の様に小電力ならAC-AC直接変換も実現可能だが、大電力の機関車は交直両用だから直接変換方式を採用する意味がなく、交流区間でインバータ+コンバータで三相交流モータを駆動するVVVF方式について「直流に整流せず」と誤解して、その誤解を前提に解説している疑いが濃厚だ。同一筐体にインバータとコンバータが収納されて中間の直流部が表から見えないことでの誤解ではなかろうか?これは(#49-049シリコン整流器)の記述から一貫している誤解だろう。
僅か6ページでこれだけの大きな作文、エラー箇所があるところが「データ・ファイル」誌のデータ・ファイル誌たる所以だろう(w。だが、エラー箇所を子細に見ると執筆者が独自の解説を加えた部分がほとんど外している。執筆者自身が物理的な理解をできないまま、感性に任せての出任せ解説をしていることに問題があるようだ。
2007/02/27 23:55
TDF補足訂正
交流車のVVVF制御のAC−DC−AC(VVVF)変換
× 現在では交流電動機を使用するようになったため、交流電源は直流に整流されず、コンバータで電圧や周波数を変換して主電動機へ送られる方式へと変わっている(#49-049シリコン整流器)
○ 直流を介してトランス側交流と交流モータ側交流(VVVF)が接続されているが、コンバータ+インバータが同一筐体内のブラックボックスで直流が表に現れないため「直流に整流されず」と勘違いしたものだろう。電力は力行時AC→DC→AC(VVVF)、回生制動時AC←DC←AC(VVVF)と送られる。光ゲート制御素子の普及で交流−交流VVVF変換は不可能ではないがまだ電気機関車での実用はないはずだ。商用交流から直接のVVVFは明電舎開発の「マトリクスコンバータ」があるが、まだ出力が小さいし、交直両用VVVF車は直流区間との共通動作が必要で直接交流方式にする意味がない。変換素子には単なる整流器では使えず、制御電極の付いた「ゲート素子」を用いて、回生制動時は逆接続で動作させたり逆並列接続の逆側が動作したりする。
(手元の資料「制御方式2」では731系、E501系、EH500、新幹線300系、500系、700系、E1〜E4まで総てコンバータ+3相インバータ構造で中間では直流を介している。同書p118図10.27に300系主回路ツナギ概要図があり一旦直流化している。
逆の肯定情報として「『電車の進化』大研究」広岡友紀著08/09/21中央書院刊に新幹線300系が「VVVFではなく正しくは(静止型)サイクロコンバータ制御」だという敢えての記述があり、上述の私の理解が間違って居たかも知れない!と再調査した。元の資料の信用性もさることながら、同書記述の具体性正確性と、出版社が古くからの定評有る鉄道技術テキストの出版社だからである。明電舎では無理な出力容量でも日立製作所なら新幹線電車用として実現していたのかも知れない、と一瞬思ったからだ。
しかし結局は、『VVVFではなく正しくは』という広岡氏の方の間違い。AC−異周波AC直接変換方式では最大周波数の点で原周波数の1/3程度が実用上の上限とされて電源周波数60Hzに対しては20Hzが同期周波数であり低すぎて高速回転の新幹線用は実現困難だ。JR東の持永芳文氏(JR総研電気システム技師長工博)も一旦直流化して変換と述べていて、300系実回路図を捜したところ鉄道車両Tipsに掲載されていて、そこでは一旦直流化している。
サイクロコンバータというのは元々は周波数変換の回転機で、機械的構造としては巻き線型回転子式3相誘導電動機で、巻き線には回転磁界周波数と回転子回転周波数の差の周波数を発生してスリップリングから取り出す構造なのだが、半導体化が進んで周波数変換器一般を指す様に意味が拡張されて変わっている。その変換過程に直流を介すかどうかは関係ない様だ。だから「マトリクスコンバータ」であればAC→異周波AC直だけれど、結局はAC−DCコンバータ+VVVF3相インバータの構成をも一部でサイクロコンバータと呼ぶ様になったことを勘違いしてVVVF(/+CVVF)動作を否定してしまったのだろう。(08/09/28&/10/05追記)
尚「逆導通サイリスタ」という名称がこの資料に出てくるが、それはサイリスタと補助ダイオードを同一基盤上に構成・同梱した複合部品であり、独自の半導体素子ではないから「新方式」と取れる解説は妥当ではない)
See→VVVFインバータ制御参照
-
「周波数で形式を分けた理由」
国鉄の交直両用車は50Hz用と60Hz用、50/60Hz両用で形式を分けて、401/421、451/471、483/481/485(両用)、581/583(両用)などとなっている。この様に周波数で形式を分けた理由についてTDF誌は
交流機器冷却部の周波数依存性が主原因で、
×「トランスはどっちでも働く」(#45−5左端)
×「トランス自体は10Hzの違いぐらいどーってことない!」(#58−5)
と重ねて記しているが、後半のトランスについては間違い。
○ トランスの最大出力容量、最大電圧はほぼ周波数比例だから、50Hz用のトランスを60Hzで使うことは可能だが、60Hz専用に設計されたトランスを50Hzで使う場合は最大電圧が周波数比例で減少するので、過電圧となって使えない。鉄心の磁気飽和を避ける最大磁束密度(珪素鋼板で1Wb/m2余)で規定され最大出力電圧が周波数比例になるからだ。だから50/60Hz両用トランスというのは低い周波数の50Hz用で設計し、電圧降下率などで60Hz動作も配慮する。
50Hzで設計された車両が60Hz区間を走れない理由として考えられるのは、トランス本体ではなく、冷却部のモータの周波数依存性とか、ATSの耐ノイズ特性の違い、あるいは単なる未検定など周辺部に原因がある。その対策をしたものが50/60Hz両用車、485、583系である。
長崎市電が、廃止された東京都電の直流変電所設備を買い取って使ったのは、東京が50Hz、長崎が60Hzだからできたことである。60Hz専用→50Hzへの逆方向では750V60Hz定格→625V50Hz使用であれば可能だが、同電圧ではトランス励磁が飽和領域になって過電流を生じるので、できない。
-
国鉄型ATCの概略解説はhttp://www.geocities.co.jp/Technopolis-Mars/8897/FIG/atsatc.htm#ATC、
周波数割付など詳細部はhttp://www.geocities.co.jp/Technopolis-Mars/8897/FIG/320c/atc1d.htm参照。
解説ページに照らしてTDFの解説は
- 1)01、02、03信号は東海道新幹線開業当初からあり、後の改良で加えられたのではない。
- 2) ATC改良は、全国共通方式ATC-1Dとして先ず東北・上越新幹線で実施、次いで東海道(型名不明)、山陽(ATC-1W)を準じる形で設備改良した。
- 改良内容は、副搬送波と副信号波を増やして、上位コンパチの信号波2周波組合せ方式として、220km/h以上の高速度信号を制定し、02E信号を新設した。
- 2周波方式は新大阪210km/h信号誤現示事故に散々にやられての改良
- 02E信号は、品川信号事故(停電時に70km/h信号誤現示)の苦い経験の反映。
- 02 は冒進や停電で線路に信号電流がない状態。
- 02E はノイズを信号と間違えない様に、02状態を伝える信号電流。これが2周波化改良で追加された。
- 03 は過走非常停止の添線軌道回路ループコイルに流す絶対停止信号。
- 01 は、30km/h仮制限時、次閉塞手前約150mに置いた2個の変周地上子(P点)から発する停止信号で、常用制動で停止し、他の信号現示を受けて解除。
30km/hは次閉塞に列車がいるなど、ATCからいえば停止(在来線ATCはもろ停止)だが、確認扱いにより長い閉塞区間のP点先まで低速での進入を許容して列車間隔を詰めるもの。
- 2周波式改良時に改められたのは、
210km/h→220km/hと、160km/h→170km/h、110km/h→120km/hは正しい。基準になる車両の減速度を増やせたということだ。
- これに対し副本線待避の#18分岐通過制限70km/hは曲線の横G基準だから、この基準(約0.05G)が変わらない限り変わらない。
しかし東海道新幹線の運行責任者だった齋藤雅男氏が繰り返し「東海道新幹線に限り分岐制限70km/h→80km/hに変えた。」(RJ'05/06号等)と書いていて、齋藤氏の新幹線システム全体像と古い情報の正確さと横G算出値からは#18分岐制限80km/h説も捨てがたい。氏も現場を離れている時期の情報には時に間違いがある(→疑問項参照)ので、ATC二周波化改良時は現役引退済みだったことから間違いの可能性もある。この#18分岐制限80km/h問題はTDF記述の問題ではない。
- 国鉄では、車内信号がATCの条件だが、それより古い営団のWS-ATCは地上信号。
- 青函ATC-LとはハードとしてはATCシステムを使ったATS。自動ブレーキ車を使う以上自動緩解は使用を避けたいが、「車上信号式はATSには認めない」という規則で、予告信号を設けてハンドル位置を規定しATC-Lとした。(省令での規定の仕方が本末転倒だ。当初JRが命名した「ATS」が本筋だ。)
- ATSは点伝達で、ATCは軌道回路から連続して伝達という区分けも間違い。
連続伝達のATS-Bとか旧阪急ATSはATCではないし、地点情報はATCだって地上子から受ける。
-
#
134号巻末鉄道用語事典、デジタルATC項は比較的良くまとまっているが、キーとなる速度照査方式の決定的な違いである「位置基準限界速度車上算出方式」=いわゆるパターン方式の採用が優秀さの根源であることと、これはATS-Pでの成功が基礎であることを述べておらず逆にD(S)-ATCとは独立のものとして説明していることが基本的な弱点である。当該ページ日記#136参照
-
- (#15-P7C3):「電圧制御のみを行い弱め界磁制御は行わない」
「クモハ711に電気機器を総て搭載したため,床下はギッチリと埋まってしまい,発電ブレーキ用の抵抗器を搭載することができず,国鉄新性能電車としては異例の,発電制動を装備しない形式となった。」
とあるが、MT54の弱め界磁制御不使用&500V←375V定格と、発電制動不使用は、無接点化&抵抗制御不使用方針として一体のものである。
- (#15-P9C1)高速走行特性がトップクラス×
標準的特急車183系,485系より悪い。
共に、ディーゼルカーの安価電動化路線。
詳細は「MT54A/711系の走行特性比較」参照
-
【「寝台特急日本海北陸トンネル火災事故」解説は落とせない!】
(#113-P27)トンネル内列車火災で30人死亡、714人負傷の大惨事となった急行きたぐに事故の3年前、急行きたぐにの前身である寝台特急日本海北陸トンネル列車火災に際し、乗務員は火災時のトンネル内停車が危険と判断し、運転規則に逆らってトンネル外まで走行、地元消防と協力して消火し出火車両のみ焼損の物損事故に留めた。乗務員の適切な判断によるトンネル火災事故対応で当時の報道でも殊勲の行動と賞賛された。
ところが国鉄はこれを規則改定せず「運転規則違反」として処分してしまい、出火した急行きたぐにに危険なトンネル内停車を強要して大惨事を招いた。惨事後の「予見可能性はなかった=国鉄に刑事責任なし」という結論を作るための大規模なアリバイ実験だけでなく、トンネル内停車による惨事を予見して適切な措置を採った寝台特急日本海事故についても論じるべきだろう。このとき国鉄が妥当な規則改定をしていたら30名死亡の大惨事は防げていたのだから。
因みに、急行きたぐにとは、寝台特急日本海がダイヤ改正で別の特急に吸収されてなくなり、それと同じスジ(ダイヤ)で運行されるようになった夜行急行だった。2件の北陸トンネル火災は同じスジで発生している!
→日記#114参照
-
シールド工法の解説もなく、いきなり特殊な泥水加圧シールド工法解説とか、基準となるべき「リング」の解説もなしに、その構成要素たるセグメントだけに触れるとか、いかにもTDF的解説。斯界の権威には全く相談しないで書いている。#128号「鉄道用語事典」
→日記#130参照
-
標記2ページの記事に補足訂正が6件見つかったので、改めて別ページとして記述します。
(#158号P23-24)→日記#151参照
全電気式制動はメカ部摩耗防止 <TDF_9>
#
159号巻末、鉄道用語辞典「電気指令式ブレーキ」解説中の「全電気式ブレーキ」の解説として、停止まで回生制動が有効であるかの説明があったが、これは誤り。回生失効以降静止までの制動トルクを逆回転磁界で与えているからその部分は電力消費であり、ブレーキメカ系の摩耗を極限まで抑えてメンテを減らすのが利点。省エネは回生制動項に入るべき解説だ。(07/03/20追記)
-
#
158号
交流機関車開発時には車載用水銀整流器開発
<TDF_11>
#
165号の試作型交流電気機関車解説記事中に、水銀整流器そのものが開発中と取れる記述があるが、間違い。詳しくはこちら「鉄道DATA FILE補正memo」参照
×→× TDFミス表示明確化:2011/08/25
2007/04/27+ /03/02 23:55






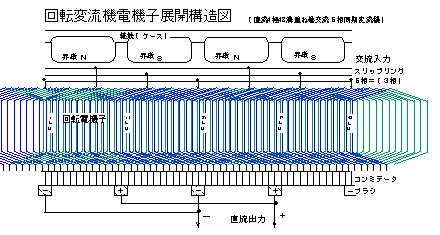
 鉄道DATA FILE誌補足→
(目次へ) ./tdf_err.htm <TDF>
鉄道DATA FILE誌補足→
(目次へ) ./tdf_err.htm <TDF>
