[191]
|
|
|

BBS
|
mail to:
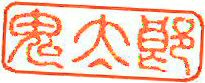 adrs adrs
|

旧
|

新
|

Geo日記
|

前
|

主目次
|
|
神戸電鉄過速度停止事件Q&A
日記前ページ#190は、実は右囲み上側のmailを頂き、その返信を基に書き上げたものだ。追って箇条書きの質問とmail公開のお許しも頂いたので、追補の補足として更に述べる。超特急の作業を必死に終えて眠ったら、変な時間に目が覚めてしまい以降眠れそうもないので既に送った返信mailの内容をネタに日記190を書いた。
神戸電鉄のATSの数とその速度設定について
frm.189:
2008/05/24 (土) 17:30 AT
『問題は何か?非常停止は速照設置の成果では?』の論文を拝見し、………大変参考になりました。ありがとうございます。
さて、その中の、『3段階速照とすれば、制限55km/hに対してカーブ入口から手前方向に65km/h、75km/h、85km/h等と3組が設置されていたのではないだろうか。』とのご推測については、神戸電鉄(http://www.shintetsu.co.jp/) の発表「制限速度超過によるATS作動に伴う急停止について」などによれば、3段階速照ではなく、75km/hと80km/hの2組のみの設置ということでした。
ということで、今回は75km/h地点にたまたま80 km/hで進入したためにATSが動作したものの、もし75km/hのスピードでの進入だったとすれば、フリーパスで55 km/hの制限速度のカーブに突っ込むことになるのか、もしそうだとすれば脱線、転覆の恐れがあるのではないかと再質問したところ、その場合には何らチェックにかかることなくそのまま75 km/hでカーブに進入するが、そもそも55km/hの制限速度は乗り心地等に配慮して設定した速度に過ぎず、75km/hの速度のままで進入した場合であっても脱線、転覆等の危険はない旨の、堂々と断定する驚くべき回答が来たのでした。
勿論、それはないだろうと強く反論をしておりますが、併せて、近畿運輸局に対しても、このようなことを認めているのか、このようなことで安全は守られるのか、どのように電鉄会社を指導しているのかなどと質問をしているところです。
実は、本件に関する最初の報道の直後、カーブの制限速度は、75 km/hは誤りで、55 km/hであると、現地確認の結果、某新聞社に投書したのは当方です。
又、55km/h制限のカーブに75 km/hで進入する可能性があることについても、危険な設定ではないかとの投書も改めてしているところです。
確かに、制限速度の1割程度はオーバーしても安全に問題はないとは直感的にも思うものの、20 km/h超過は3割6分ほどのオーバーとなるため、これはいくら何でもまずいと思うのですが、如何でしょうか。
|
[190] 神戸電鉄過速度停止事件追補
2008/05/26 01:55
(Re.は日記190:神戸電鉄過速度停止事件追補の元文)
|
神戸電鉄のATSの数とその速度設定について
RE:
2008/05/27 (火) 11:27 AT
早速、ご丁寧な回答を頂きまして、ありがとうございます。
実は、ご回答では当方の能力を超える技術論が展開されているため、概念的には分るものの、残念ながら厳密には理解しがたいというのが正直なところです。
その方面に詳しい方も世の中には大勢おられるものとは思いますが、当方と同様に、そうでない人も更に多数おられるものと思います。マスメディアもその中に含まれると思います。
そこで、専門的な技術論の他に、それを分り易く解説する説明もつけ加えて頂ければ幸いです。新聞の記事で言えば、難解な内容と考えられる場合などの、本文の後に「解説」と銘打たれているものなどです。
尚、本件を日記にて公開希望とのこと、匿名とのことですので、公開して頂いて結構です。
その中で、次の疑問を解消する解説や意見も盛り込んで頂ければ、更に分り易くなるのではないでしょうか。
1.本件のATSの速度設定では、半径200メートルのカーブの制限速度55km/hに対し、仮に20km/hも上回った75km/hで進入したとしてもATSでは異常とは判断されず、フリーパスとなるが、クルマの場合、制限速度を20km/hも上回った速度違反をしでかしては大変なことになるのに、鉄道の場合には本当に大丈夫なのか。
本当にそうであるのであれば、電鉄側はその理由を懇切丁寧に説明する義務があるのではないか。
つまり、今回も所謂「誤発表」が問題になったように、鉄道側の発表においても、制限速度を大幅に上回るATSの速度制限設定の現状と、仮にそれでも安全であるとするならば、そのことと、その根拠とを十分説明する必要があると思うが、どうか。
それを改めないことには、今後も同様の「誤発表」問題が再現するのではないか。
2.それでも脱線、転覆の心配はないということであれば、勿論、実際の脱線限界速度は更に高速度であるということになるものの、福知山線の脱線限界速度に関しては、事故直後のJR発表が『現場の転覆限界速度105km/h(103系)』よりも遥かに高い速度になっていたように、神戸電鉄が判断するところの「脱線限界速度」にも怪しいものがあると考えるのが自然であるが、その点の心配はないのか。
つまり、神戸電鉄は、福知山線脱線事故を教訓として、本件カーブの「脱線限界速度」の見直しをしたのかどうか。
3.福知山線の当時の制限速度70 km/hに対し、転覆限界速度105km/hは1.5倍になる。単純にこれを制限速度55 km/hの本件に当てはめれば、1.5倍の転覆限界速度は82.5 km/hになり、神戸電鉄が絶対安全と主張する75km/hとの差は僅かになるが、それでも大丈夫と本当に断言できるものなのかどうか。
4.『3段階速照とすれば、制限55km/hに対してカーブ入口から手前方向に65km/h、75km/h、85km/h等と3組が設置されていたのではないだろうか。』とのご推測もあったところなるも、神戸電鉄では3段階速照ではなく、75km/hと80km/hの2組のみの設置ということなので、安全のためにはもう1段の低速度設定のATSを設置すべきだと常識的にも考えるのであるが、どうか。
5.今回のATSによる非常停止により、大勢の人が転倒したとのことであるが、半径200メートルの制限速度55 km/hカーブを20km/hも上回った75km/hで進入した場合には、少なくともATSによる非常停止よりも強いショックが生じると想像するのであるが、その点についてはどうか。
6.一般的には、車両なども高速走行を前提として設計されているJRよりも、全線を通しても最高速度が80 km/hのローカル鉄道である神戸電鉄の方が、比較的高速域の速度違反には弱いと直感的に考えるのであるが、その心配はないのか。
7.国土交通省の行政指導でも、簡易型ATSの速度設定は、そもそも、急ブレーキをかけて当該カーブ突入直前で制限速度まで減速する形の速度カーブを描いて停止するように指導されているのではないのか。
この点からも、『55km/hの制限速度は乗り心地等に配慮して設定した速度に過ぎず、75km/hの速度のままで進入した場合であっても脱線、転覆等の危険はない』旨の神戸電鉄の考え方とは真っ向から矛盾すると思うが、どうか。
8.この関係で、今回のご回答の中の、次の『突然の非常制動自体にかなりのリスクがあり、若干の速度超過は許容した方が安全で、現に転覆しませんでしたから。』の意味が不明。今回は、75 km/h制限のATSに80 km/hで突入したので、急ブレーキがかかって列車は停止したのであるが、たまたま75 km/hで通過したとすれば、そのままのスピードでカーブに突入してしまうのである。
|
2種類ある設定基準
ATS-Sxなど点速照型過速度防止速照の設定についての考え方が2通りあり、JR系ST速照は制限速度を強制的に守らせる発想で、速照を数段に分けて最終的に制限+10km/h程度に設定するものが多く見られるのに対し、神戸電鉄の設定は、曲線速照国交省通達05/05/17に基づき、転覆限界速度×0.9を速照値として転覆だけは避けようという必要最低限の設定基準になっている。同通達添付参考資料によれば、簡易には400R未満の曲線では速度差20km/h以上で速照義務付け、400R以上で速度差30km/h以上に設置とあって、尼崎事故前のJR東海基準の40km/h差より厳しくされており、神戸電鉄の現場は200Rで55km/h制限に80km/hで進入するに際して制限+20km/hの75km/h照査をするというのはまさに通達添付参考資料通りの設定であるから「転覆防止」機能について問題はなかった。動作境界の着目点が「乗り心地保障」なのか「転覆防止保証」なのかの違いである。
両方式を比較すれば、多段階照査で乗り心地を保障する方が過速度対策としては丁寧なのは言うまでもないが、実際に速照に当たった場合の非常制動の衝撃には激しいものがあり前ページで触れた様なリスクがあるので、安全面の保障のみに限れば国交省通達の通りで良い。現に非常制動による乗客の転倒が第一報で伝えられていて、これを放置して多段階照査にしても安全面は変わらない。しかし、低速側速照でも当たれば報告義務を生じ、時には懲罰的日勤教育に晒される訳で、運転が慎重になる。
極端な設置例では土佐くろしお鉄道宿毛駅突入事故前の分岐器速照は分岐器手前約10m付近に25km/h照査として設置されており、これに当たっても空走時間内に分岐器に突入していて物理的過速度防御には全く役立たなかったから人為エラーや障害があれば終わりで現に事故に至ったが、運転士懲罰のネズミ取りには使えて、規則遵守を強制する設定となっているが、安全装置として人為エラーをカバーすることはない。それでは精神論強化の運転士虐めだけで、安全装置の意味はなく、後に事故防止に有効な設定に直しているが、こうしたJR国鉄型の役立たない酷い速照は他にも残されてはいないだろうか。
宿毛線は元々は鉄建公団の設計を運輸省が認可して設置したものを第3セクターのくろしお鉄道が受け取っただけであるから「まだ残ってないか?」と危惧するのである。
事故後に有効な過走防止速照の必要性を言われたくろしお鉄道は「指導があればすぐに設置した」と取材に答えていて、速照地上子を3対6基増やし、計5対で過走防止装置を構成している。
両方式での水平方向Gの値の試算は、後述の5.項に行っており、緩和曲線により2秒余を掛けて徐々に強まる200Rを75km/h通過の横Gよりも、突発荷重である非常制動の衝撃の方が強烈であることを予想させる。
これが最初のmailの主要疑問と2度目のmailの1項に対する回答になる。
2本目のMailの質問項については日記#190で概ねは述べているが、改めて箇条書き毎に触れると
- 1.前述通りOK!妥当な設定
- 2.福知山線事故の2ヶ月後に国交省指導基準で設置。「福知山線脱線事故を教訓として、本件カーブの「転覆脱線限界速度」に基づき設定した」
- 3.強い横風など別の条件が約0.19倍の余裕分(∵1−0.92)を超えて加われば転覆。
鉄道は常々そういうリスクを抱えて運行している。北伊豆地震で当時掘削中の丹那トンネルに2.5mもの断層ズレを生じたが、これが列車走行中に起これば大惨事である。240km/hでの断層面への衝突など地獄絵ではあるが今日も新幹線は運行中。
- 4.考え方次第。点速照式を採用する限り、安全面ではあまり変わらない。通達で強制できるのは最低限の安全保障。ATS-Pなど車上演算式照査を採用したもっと高機能のATS/ATCでないと厳密規制の効果が薄い。
当サイト日記189で55km/h制限に対する照査速度を85km/h、75km/h、65km/hという推測をしたことで混乱を生じた嫌いはあるが、それはJR型の制限速度基準=乗り心地限界速度遵守型での設定であり、国交省通達で義務付けた転覆懸念速度を直接に基準にした「安全限界速度」によるものではない。しかも直前区間に80km/h制限があることを知らなかったから85km/h照査を残している。神戸電鉄がそこに80km/h照査も置いていることは妥当で丁寧な措置と言って良い。かって運転は機関士の職人芸に任される部分があり、直線の速度制限は時に無視されやすいのだから。(2ちゃんねるに「体験した最高速度」のスレッドが立って暫く賑わっていたからさほど珍しくない日常的違反であろう)
- 5.試算:非常制動減速度はATS-Sxの算出基準として、電車で減速定数K=20/0.7と規定されている。この値は最低保障値で停止寸前には1.5倍〜1.75倍程度になる。
K=20/0.7=3.968km/h/s=1.1023m/s2=0.1125G(突発)。
水平遠心力=V2/R=(75/3.6)2/200
=2.170m/s2=0.221G 。
カントを105mm(最大制限値)、軌間を1067mmとしてカント面に対する実効横Gは重力と相殺して
実効横G=sqrt(12+0.2212)
×sin{atn(0.221/1)−asin(105/1067)}
=1.02413×sin{12.46゚−5.65゚}
=0.1215G
(1/400律カント逓減方式で42m以上2秒余分の緩和曲線があり、徐々に横G増。但し新幹線のカント逓減律は直線ではなく正弦法など過渡的Gを考慮)
以上の試算から、衝撃の絶対値比較では非常制動と遠心力とがほぼ同じオーダーであるが、突発という点で非常制動のショックがかなり大きいことが分かる。分岐器0.05Gと曲線0.08Gとで限界Gが違うのは分岐器が突発Gだから厳しくしているのだろう。
- 6.具体的根拠は?通勤車両は同一区分と理解。特に低重心で作られた特急用ふりこ車とは違う。
- 7.行政指導は「当該カーブ突入直前で『制限速度』まで減速する」のではなく『安全限界速度』まで減速。この神戸電鉄のケースでは75km/hでこれは国交省の指導内容そのもの。
- 8.以上解説の通り
予想外の鉄道事故続きで、不安、危惧の気持ちが生ずるのは理解できるが、尼崎事故を機に発した転覆防止の曲線速照通達については以上の試算の通り(200Rでは)適切なものである。
一般人に理解できるよう工夫した広報の要求は前ページにも触れたとおり同感である。
点速照だから速照を通過後加速されるとアウトで、現に京王井の頭線吉祥寺駅事故で車止めに接触しスカートを破損しているから、加速も防御するとなるともう1段の速照が欲しくなるが、果たして急曲線直前120mから加速するだろうかと考えれば、まだ若干のゆとりも見込んであり義務付けまですることはないというのが現段階ではないか?新幹線の終端過走防止装置の設定は停止後再加速も想定して設定している様である。さすがShinkansen!
なお、尼崎事故直前の土佐くろしお鉄道宿毛事故を承けての過走防止速照通達(H17国鉄技第195号)には対応に抜けがあり、翌年の技術基準改定で無効となり事実上撤回されている。
5.項説明図

|
遠心力と重力(青)の合力(黒)は、カント面に対しては「カント面横G」(緑)と「カント面垂直G」(緑)に分解して考えられ、横Gが小さくなって、その分高速通過を可能にする。
前出、5.項での値としては、重力=1G、遠心力=0.221G、だから
合力=1.02413G、合力の方向は12.46゚=ATN(0.221/1) となる。
カント=105mm、軌間1,067mmのカント面の方向は5.65゚=ASIN(105/1,067) で、
先の合力をカント面方向に換算すると、
合力1.02413G×sin(12.46゚−5.65゚)=0.1215G
|
ATS-Pの分岐器速照でも、列車長さはATS-Pに取り込まれてない様だから、15連で加速すると加速度次第で最後尾はかなりの過速度となり危なくなる。列車長の情報を持っている編成は多いから、それをATS-Pに取り込む小改造をしたP車上装置を新製車から導入した方が良いと思うのだが、無閉塞運転中の15km/h照査導入(直下地上子検出で解除)と併せ改良を検討して貰いたい。JR西日本の許容不足カントコードの採用を決めたJR東日本は、そのための車上装置改良に併せて導入すればソフトの機能追加でほとんど資金を要しないはず。執拗なまでの故障地上子排除運行継続策からみて車上装置にも予備のDigital入力端子くらいはあるのではないだろうか?
ATS-Sx系は総て点速照だから、照査点を過ぎての誤操作には対応していないから、事故条件は僅かには残るが、それは錯誤を含む意図的操作に依るもので、単純なブレーキ操作遅れでは事故にはならない。
[[[追補]の補足]の補足]
JR社内で言えば、公称の速度制限を安全限界と見なして厳守を求めていて、それを前提に速度照査を設定したから結果として「乗り心地限界速度」遵守の設定となる。一方監督庁としては転覆防止ギリギリの物理特性で設置を義務付けないと通達の妥当性を争われる余地が出てくるから解析的に規制する。そこに微妙な違いがあるのだろう。JRが制限速度厳守を運転士に徹底する意図があって物理限界速度ではなく、規定速度で管理するというのならそれは一つの識見である。しかし、懲罰のためだけで安全装置としては働いていない前出宿毛駅25km/h速照型の設置は断固反対。安全装置がオペレータを助けず敵対する設定は抵抗行動を誘発する事故の素になるから絶対に避ける必要がある。
かっての私鉄ATS通達仕様は極めて原理的で高速部に速度照査を課し、冒進直前照査20km/h以下に規制することで大事故を押さえ込んでいるのに対し。JR東海ST時素式過走防止装置は高速部は放置し危険度の高くない低速部のみの規制だから、私鉄ATS通達仕様である小田急、京王等が進んで取り入れて機能不足を埋めている。危険な高速域放置ではATS-ST過走防止装置は欠陥であり'06/03技術基準改定を承けて直ちにATS-PT導入を表明する背景となっている。国鉄JR系規制は運輸省規制に比べて感覚的・観念的規制で、JR化時の不合理な私鉄ATS通達廃止など逆に運輸省を引きずり回したのだ。
かぶりついて乗務員を監視し、手袋を取ったの、手放しで立ち上がったの、携帯を使ったの、少年ジャンプに目をやったのと下らないことを匿名密告して対抗防衛措置として前面展望を遮断されるような愚を止めて、速照の設定でも算出・分析して有害なネズミ取り速照でも捜してやり玉にあげてはどうだろう。算出用基礎数値としては車上速照タイマーはSx系や京王線で0.5秒標準、列車で0.55秒、九州の振り子式特急車で0.45秒、小田急が1秒であり、2基の速照地上子の内法で動作、地上子検出幅は最近の小型で0.5m、電気鉄板焼き器(ホットプレート)の様な大型で0.65m、計測のための長さの基準はレールがほとんど25mで、その間の枕木は東京近郊なら等配で40本〜41本(場所毎確認)、車体長、列車長、ホーム長から、精度は落ちるが直線部電柱ピッチ約50mと、概算基準には事欠かない。枕木がほぼ停まって見える1/2000シャッターで撮影出来れば低速時なら枕木本数から試算可能で、それが過速度を防御できるか、ネズミ取り処罰用かを判定して晒してはどうだろう。安全には却って有害なネズミ取り速照の撤去・改造は必要なのだから。See→ATS-SW速照値計算例
速度照査の設定法が一般鉄道ファンの話題になるというのは、珍しい。それは設定方法についての情報が最近まで一般公開されていなかったことも原因だ。土佐くろしお鉄道宿毛事故05/03/02で速照設定の不適・不足が問題になってようやく話題となったが、これも直後の尼崎事故での「ATS-P換装で防げた」という誤報に影響されて多くのアクセスがATS-P関係に取られてしまい、時素式速照関連のページのアクセスはさほど増えなかった。連続関数ではない点速照の不連続不等式計算がなかなか理解しがたく面倒なのだろうか。
鉄道業の社員教育テキストである鉄道電気技術協会編「信号概論7.ATS・ATC」でも時素式速照個々の設定計算法が記されて、数組で過速度防止装置を構成することは掲載されているが(p30〜32)、具体的にどう構成するのかと、設置基準は全く掲載されていない。昨年2月末07/02/28に刊行された「電気鉄道ハンドブック」(電気学会同書編集委員会編コロナ社刊)でようやく設置例が載った程度である(p679,678)。当サイトでも具体的設定法が分からず、右上リンクの様に観測可能点を捜して実測し、あり得る様々な仮定をして試算、作図を行いその想定動作を推定していた。それはATS-Pの詳細動作設定についても公開資料がないため同様に詰めて行った。(記事での試算は総て制限速度基準で行っており、転倒限界からの試算はない。See試算例→最初の[Sx速照地上子位置試算図]'02/09/18)
参考資料リンク
2008/05/28 20:00








