[348]
 揝摴夝愅偛偭偙 |
mail to:
| ||||
 媽 |
 怴 |
 Geo擔婰 |
 慜 |
 庡栚師 | |
[348] |
| |||||||||||
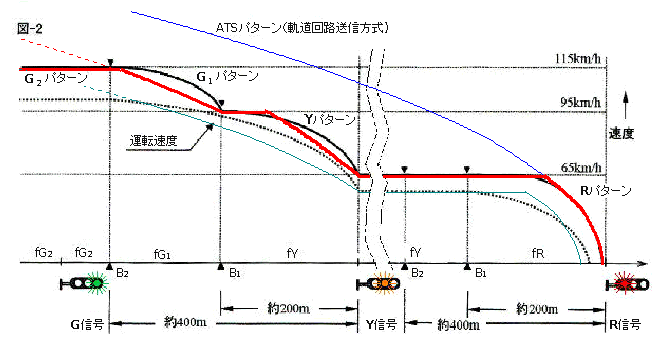 丂惣揝俙俿俽偺栿偺敾傜側偄夝愢偵擸傑偝傟偰偄偨偲偙傠傊丄峔憿椶帡偲偝傟傞惣晲揝摴俙俿俽偺夝愢婰帠傪嵹偣偨揝摴僺僋僩儕傾儖帍2013擭12寧憹姧崋傪敪尒丅偦偺夝愢側傜摦嶌偑椙偔棟夝偱偒傞偺偱攦偭偰偒偰丄帺暘側傝偵從偒捈偟偨偺偑塃偺儕儞僋儁乕僕偱偡丅
丂惣揝俙俿俽偺栿偺敾傜側偄夝愢偵擸傑偝傟偰偄偨偲偙傠傊丄峔憿椶帡偲偝傟傞惣晲揝摴俙俿俽偺夝愢婰帠傪嵹偣偨揝摴僺僋僩儕傾儖帍2013擭12寧憹姧崋傪敪尒丅偦偺夝愢側傜摦嶌偑椙偔棟夝偱偒傞偺偱攦偭偰偒偰丄帺暘側傝偵從偒捈偟偨偺偑塃偺儕儞僋儁乕僕偱偡丅
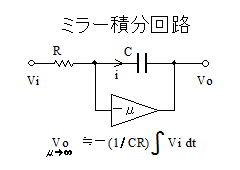 僆儁傾儞僾憹暆搙兪仺亣 擖椡倁i仺弌椡倁o 學悢丗亅侾乛俠俼  |
|
1953/10/17 崅懍楍幵揝摴媄尋偺敪昞婰帠:崙揝杮幮偐傜偼嫮偄斸敾丄塣桝徣尋媶曗彆嬥懳徾偵 1954/09丂丂揹幵曽幃埬傑偲傑傞丅柤慜偼揝摴乽媄尋乿偩偑幚幙乽帋尡強乿偺惂栺桳傝 1954/10丂彫揷媫偑揝摴媄尋偵崅懍揹幵奐敪愝寁梫惪 1955乣56丂 塣桝徣偺崅懍幵奐敪尋媶曗彆嬥丄揝摴媄尋強堳傪挿偲偟彫揷媫偐傜怽惪 1956/11丂丂丂搶奀摴慄慡慄揹壔姰椆 1957/06丂彫揷媫3000儘儅儞僗僇乕姰惉乮惢憿幮擻椡偱寉崌嬥仺峾惢乯 1957/09丂彫揷媫3000崅懍搙帋尡乮搶奀摴慄偱揝摴媄尋乯 1957/丂丂丂儌僴90宯帋嶌(101宯)姰惉乮怴惈擻崙揹僾儘僩僞僀僾乯 1959/丂丂丂儌僴20丄91(151宯丄153宯丗偙偩傑宆丄搶奀宆)姰惉 1959/04丂搶奀摴怴姴慄寶愝擣壜寛掕 1960/12丂丂103宯帋嶌曇惉 1964/10/01 搶奀摴怴姴慄奐嬈 丂丂See仺乵彫揷媫俽俤幵偐傜惗傑傟偨怴姴慄乶 丂丂丂彫揷媫3000宍俽俤偺捛壇丂嶰栘拤捈丂揝摴僼傽儞丂1992/7 |
丂婡娭幵偑廳偐偭偨帪戙偺婎弨偱揰専 |
丂丂丂擔杮宱嵪怴暦 2013擭10寧4擔2柺憤崌柺
俰俼杒奀摴慻怐偵昦憙 |
 丂偟偐偟尰嵼偱偼婡娭幵傪娷傔偰傎偲傫偳偑俀幉戜幵偲側傝丄崙揝宆偺揹婥婡娭幵俤俥俇侽宆埲崀偼塐昘摶墇偊偺怣墇慄尅堷婡娭幵俤俥俇俀宆乽俁幉戜幵亊俀乿偑桞堦椺奜偺俁幉婡偱偡偑丄墶愳亅寉堜戲娫偺攑慄偲嫟偵攑幵嵪傒偱丄嵟屻偵巆傞壿暔擖懼梡俢俤侾侽宆乽俁幉戜幵亄俀幉戜幵乿傕嵟戝幉嫍偑抁偔側偭偰僗儔僢僋偺婯掕傪彮偝偔夵傔偰偄傑偡丅尰梡婡偱俁幉埲忋偼俢俤侾侽偺懠偵偼丄揝摴徣宆峔憿偱偁傝僀償僃儞僩憱峴梡偲偟偰曐懚偝傟偰偄傞忲婥婡娭幵偲丄俤俥俆俉丄敿棳慄宆俤俥俆俆埲奜偵偼柍偔側傝傑偟偨丅
丂偟偐偟尰嵼偱偼婡娭幵傪娷傔偰傎偲傫偳偑俀幉戜幵偲側傝丄崙揝宆偺揹婥婡娭幵俤俥俇侽宆埲崀偼塐昘摶墇偊偺怣墇慄尅堷婡娭幵俤俥俇俀宆乽俁幉戜幵亊俀乿偑桞堦椺奜偺俁幉婡偱偡偑丄墶愳亅寉堜戲娫偺攑慄偲嫟偵攑幵嵪傒偱丄嵟屻偵巆傞壿暔擖懼梡俢俤侾侽宆乽俁幉戜幵亄俀幉戜幵乿傕嵟戝幉嫍偑抁偔側偭偰僗儔僢僋偺婯掕傪彮偝偔夵傔偰偄傑偡丅尰梡婡偱俁幉埲忋偼俢俤侾侽偺懠偵偼丄揝摴徣宆峔憿偱偁傝僀償僃儞僩憱峴梡偲偟偰曐懚偝傟偰偄傞忲婥婡娭幵偲丄俤俥俆俉丄敿棳慄宆俤俥俆俆埲奜偵偼柍偔側傝傑偟偨丅
|
| [Page Top仾] |
 媽 |
 怴 |
 Geo嶨択 |
 慜 |