[416]
 鉄道解析ごっこ |
mailto: | ||||
 旧 |
 新 |
 Geo日記 |
 Geo雑談 |
 前 |
 主目次 |
[416] |
| ||||||||||||
岐阜羽島駅780m過走事故・・・・・・。冬も迫ってきた昭和42年12月9日のことである。この日は日曜日であった。 自宅の鉄道電話が鳴りひびいた。相手は運転司令長である。「報告します。ただいま名古屋発新大阪行『こだま201号』列車が岐阜羽島で停止位置で止まらず、通過する事故が発生。 長良川橋梁を過ぎ、760m先の地点で停止中。死傷者なし」 「それでは至急、運転士は前から後ろの運転室に移り、列車を羽島駅に戻すこと。 決してバック運転をしてはならない。 客扱いを終わった後、直ちに発車してくれ。発車後、再度自宅に電話してくれ」 「了解」 10分後、電話がきた。 「客扱いを終了し、8分の遅れで出発しました」 「乗客は騒いでいるか。米原・京都・新大阪ともよく連絡しておいてくれ。 13時にこの件で協議をするから、関係者に集まるよう連絡を頼む」 ということで指示を与えた。 ・・・・・・・・中略・・・・ 13時、車両課、保線課、列車課、旅客課の一同が会議室に集まった。 実情報告を列車課長が始めた。 運転士からの報告によれば、当日は「名古屋出発時より吹雪となり、列車の前方はこの”伊吹おろし”のため確認が良くできない。 運転室の車内信号はノッチを入れると210信号を現示する。列車の速度は110km/h程度であった。 全くATCによる信号現示は狂ってしまって 危険この上ない。 ブレーキをかけると、今度は氷雪のため車輪とレールの粘着力が低く、滑走する。 この滑走と空転を繰り返し、運転を続けた。 吹雪はいよいよ激しく、ノッチを入れたり、ブレーキをかけたり、注意を重ね全力を尽くして運転したが、せっかくの車内信号が当てにならず、岐阜羽島駅の70信号もこのために減速せず、120km/hで副本線に突入した。 B点(30km/hで(確認ボタン)スイッチを押すとマニュアルブレーキとなる(停止コマンド))を80km/hで過ぎ、最後の要(ママ:砦?)である絶対停止区間長さ50m(これを03という)も過ぎ、本線に出てしまった。 そして、ようやく長良川橋梁を越えて停止した」 ・・・・・・・・中略・・・・ 速度計軸、制動力1/2→0→後部車両へ。 & 分岐の進行定位・・・・・・ ・・・・・・・・中略・・・・実現した。 私(斎藤雅男氏)は直ちに本社に出掛けて関係幹部にこのことを説明した。 ところが ?(以下1行欠落か?:(本社関係幹部)「報告不要」) (斎藤)「重大事故一歩手前だったのに、報告不要とは何事ですか」 (本社関係幹部)「君、列車遅れが10分以内では報告の要なし、ということになってるよ」 (斎藤)「それは百も承知です。 しかし事故の内容から、一歩誤れば今頃は長良川に落下し、大事故になっていますよ」 と言い捨てて外に出た。 この件は、その後も一切の報告も記録もない。 「新幹線安全神話はこうして作られた」斉藤雅男著日刊工業新聞社2006/09/25刊p204L3
|
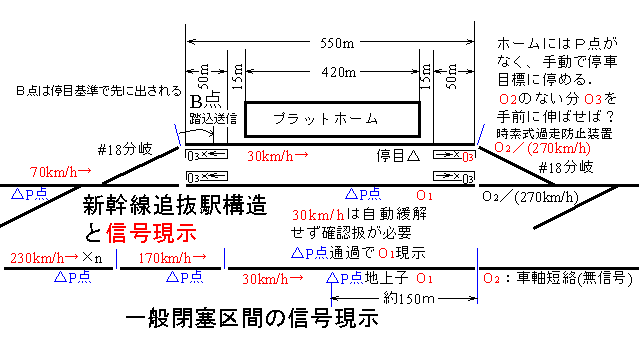 【 新幹線追い抜き中間駅構造図 】 「停目」を基準に「過走距離」と「B点位置」から状況推定 岐阜羽島駅は豪雪難所、関ヶ原関連のトラブルに備えて上下に通過線と島式ホーム2面4線、計6線を備えている。 上図上半分の2面2線より島式ホーム分駅が大きい。 |
| [Page Top↑] |
 旧 |
 新 |
 前 |