[218]
 BBS |
mail to:
| ||||
 旧 |
 新 |
 Geo日記 |
 前 |
 主目次 | |
[218] |
| |||||||||||
|
http://www.nikkei.co.jp/news/main /20090703AT2G0100103072009.html 長周期地震動、東京で揺れ2〜3m
|
長周期地震での振動増倍全国地図が作られたということで、その条件を読み込んでみたが、その条件は30階(約100m)のビルで、周期3秒の揺れに対する増倍率というだけで、振動吸収機構によるQの抑制や、共振モードが1/4波長なのか、3/4、5/4、7/4波長・・・・なのか、建物全体を1/4周期とするさらなる長周期振動応答などへの言及がなく、かなりもの足らない記事だった。また振幅が大きくても超高層ビルでの長周期であれば横Gは大きいとは限らず、振幅だけを云うのは妥当ではない。構体の最大応力と強度の関係とか、少なくともGに触れなければあまり意味はない。ブランコの振幅が3mあってもどうって事ない場合と同様だ。100m高ビルについての耐震危険度警鐘と採れば良いのだろうか?
記事にはない加速度だけでも算出しておこう。
位置Xの時間tに対する変化率が速度V、速度Vの時間tに対する変化率が加速度α、すなわち位置Xの2階微分が加速度αだから
X=A・sin{(2π/T)t}
V=dX/dt=A(2π/T)・cos{(2π/T)t}
α=dV/dt=d2X/dt2=−A(2π/T)2・sin{(2π/T)t}
=−3・(2π/3)2・sin{(2π/3)t}
αmax=(4π2/3)=13.2 [m/s2]=1.34 G
この振動加速度は約1,320gal=1.34Gの加速度であり、震度5強上限付近の250galの5倍余、震度7下限の概ね400gal以上の揺れにはなるから、記事後半の状況解説に合致するが、途中の解説はどこへ行ってしまったのか?発表内容の整理が悪いのか、記者が要点を理解できなかったのか、どちらだろう。一々数3と高校物理を思い出して試算する必要のある新聞記事というのは、あまり褒められたものではない。
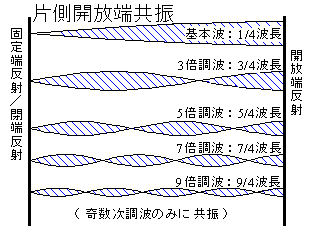 主たる振動モードは何次? 地盤:基礎側が固定端、最上階が 開放端の片端固定進行波型共振 |
| [Page Top↑] |
 旧 |
 新 |
 前 |