[188]
 BBS |
mail to:
| ||||
 旧 |
 新 |
 Geo日記 |
 前 |
 主目次 | |
[188] |
| |||||||||||
| ||||||||||||||||||
金沢工業大学永瀬和彦教授が、「福知山線事故報告書の問題点」副題&ページヘッダー「意図的な調査と調査委員会主旨にもとる判断とを含むレポート」と最大限の否定的評価をぶつけたWeb Pageを4/21付けで公開している。「はじめに」章は批判のトーンが穏やかで首肯できる項目もあるのだが、本文各章の結論部は「はじめに章」に対して木に竹を接いだかの様にかなり手厳しいし、論点が微妙に違うのだ。JR西日本社長が事故調を「ひよっこ」と見くびって不服従を匂わせた発言をして('07/8/4事故説明会)大顰蹙を買ったが、その論拠が、どうもこの永瀬教授の見解にありそうだと感じて、以下URLの原文を読み込んでみた。
情報ソースが公開のWeb上であるから、相手がたとえ大学教授であっても論議参加の資格要件としてはSELF-SERTで厚かましくも適格とさせていただく(w。当方出自は電子回路設計&解析屋であったが浅く広くあちこち使い回されて次第に何が専門なのか訳が分からなくなっている(苦w。
事故調報告の事実認定を辿ると、運転士の意識レベル低下が疑われる事象が並んでいるが、理由部ではそれに十分には触れてないことを指摘している。しかし事故調に鑑定依頼した兵庫県警から解剖結果に異常の無かったことは知らされている(報告書2.5.2.2解剖結果p40、2.5.5健康状態記録などp45)から、内容は変わらず、最終的には報告書に運転士体調不良の可能性を言及して対策を提示できるかどうかの話に留まってしまう。運転士の緩慢な動作に「異常がないはずがない」とは言い切れないではないか。運転士がこの事故で亡くなっているので痕跡の残らない一時的変調は追試できないのだ。
意識レベルに疑問の付く経過を列挙すれば、(1).下り回送時の低速進行、(2).同宝塚駅場内での確認扱い不操作でATS非常制動、(3).×停止時の非常制動(これは誤出発防止装置の到着前動作であり正常)、(4).宝塚中線折り返しで暫く運転席から降りてこず、(5).ホームで行き違う車掌の問いかけに無反応、(6).伊丹駅70m過走時の操作遅れ、(7).転覆時の緩慢操作、((4〜5).は当方の補足)が連続して起こっていて、何らかの身体的異常が発生していた疑いがあることを指摘している。
事故調報告はこれを転覆前の120km/h運転時に過速に気付いて制動していることなどを挙げて、正常な運転を追求してたと判断した訳だが、解剖では判らない一時的な意識の中断が無かったかどうかは痕跡が亡く確認しようがないということだ。類例を挙げれば、かって某都議会議員がデパートの売り場から商品を持ち出して万引きとして検挙され辞任したが、その原因はてんかんの症状で一時的に意識が飛んで持ち出したものと診断されたことがある。それは生存していたから脳波などで客観的に確かめられた訳で、亡くなってしまったら判らない。
事故を調査して予防対策を求められる事故調のスタンスとしては「何らかの原因で過速度突入をしたときの安全対策」を求めるのが主になるだろう。簡易にできる検診など今後の対策があるか事故調として検討・提起して欲しいと思うのは無理がないが、物証や具体性が弱い意識中断説は「ありうる」、「かもしれない」に留まる。個別の変調は負荷試験で発見するのだろうが、ピカチューやゲームでの脳過負荷時の痙攣症状(=てんかん)は知られているから、簡易にその負荷検査ができるかどうか、検討の余地はありそうだが、テトリスのハイゲーム1時間直後の脳波チェックみたいな試験は実現性と客観性があるのだろうか?いずれにしろ診断法と治療法の開発が必要で、具体的言及は困難だ。事故調報告はタイミング的に非常に良く一致する「過走報告集中説」のみを述べているが、不当ではないだろう。
また、安全装置からみた対策は「過速度防止」で現在の対応と全く変わらない。実務的には重大事故防止に人為的要素を残すか、安全装置が担うかという比較選択になり、従前鉄道で軽視されてきた装置による安全確保を強調するのは妥当だと思う。
事故調報告書の原因追求記述が網羅的でないのは事故調査検討会による日比谷線中目黒駅脱線衝突事故報告から共通している。一般論で言えば、各種要因を挙げて具体的に調査・検討を加えて寄与率・可能性を示して絞っていく方が妥当で説得力がある。その点で最初から一本に絞った調査と報告書は疑念を残し易く、避けた方が良いのは確かで、一般論としては同感だ。
しかしながら、専門的に明瞭な原因が見える場合にはそれは実質的に表現形式の問題になり重要でなくなる。中目黒事故00/03/08では、事故直後の早い内から「左曲線出口緩和曲線カント低減部(右)の約7m位置から脱線が始まり、7m走って脱輪」という現場状況は判っており、事故調査検討会は全国の鉄道事業者に対し緊急措置として03/16付けで「200R以下の曲線出口緩和曲線への脱線防止レール設置」を勧告していて、平行して行った実車試験で30%近い極端な輪重比狂いの車両とその浮き上がり現象を発見・映像記録して更に「輪重調整」を勧告し、事故調報告書としては、「等価脱線係数比」による脱線防止レール設置基準式と、輪重比10%以内という2つの基準を具体的に示しているが、一方、文面上の原因は「多要因の競合」と称して明らかにしなかった。工学的原因は指摘したが、文学的法学的原因は特定できずということだ。現場労働者に対する生け贄的刑事処罰を回避する事故調の知恵ということだろう。それと同時に事故調としては、他に原因は有り得ないという自信の表れでもあるが、その辺はたとえ同じ結論に落ち着くにしてももう一回りの検討と言及はあった方が良いだろう。
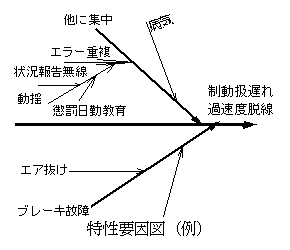 この中目黒事故での緩和曲線カント低減部の脱線と車両の走行特性不良の見逃しというのは東海道線鶴見事故63/11/09のワラ1型脱線原因からそのまま繋がる。対外的には「競合脱線」で要因を特定できないとしたが、どれだけの貨車を改造、あるいは廃棄処分にして、条件次第で800Rにまで脱線防止レールを敷設したかの諸対策を考えれば、このときの脱線防止レール設置基準を国鉄内に留めず、全鉄道事業者に一般適用される基準として布告していたら中目黒事故の犠牲は無用だった。たとえ輪重調整がされず乗り上がっても200R以下に設置を義務付けられた脱線防止レールに阻まれて元に復帰していた。
この中目黒事故での緩和曲線カント低減部の脱線と車両の走行特性不良の見逃しというのは東海道線鶴見事故63/11/09のワラ1型脱線原因からそのまま繋がる。対外的には「競合脱線」で要因を特定できないとしたが、どれだけの貨車を改造、あるいは廃棄処分にして、条件次第で800Rにまで脱線防止レールを敷設したかの諸対策を考えれば、このときの脱線防止レール設置基準を国鉄内に留めず、全鉄道事業者に一般適用される基準として布告していたら中目黒事故の犠牲は無用だった。たとえ輪重調整がされず乗り上がっても200R以下に設置を義務付けられた脱線防止レールに阻まれて元に復帰していた。
中目黒事故は技術的には最初から原因・主要因がかなりハッキリしていたケースの様だから、網羅的に調べても結論が大きく変わることはなかったろうし、委員たちがその必要を感じなかったのだろうが、原理公理発見の学術論文では着目点一点突破型で良いが、事故調査報告書としては結論が変わらなくとも、それ以外の項目(「特性要因図」のいわゆるサカナの骨)をも丁寧に潰す記述をすべきだった。
航空事故調査委員会や、海難審判庁との比較で鉄道事故調査委員会の弱体な陣容が指摘され、その強化が説かれているのは同意。
現鉄道事故調査委員会は、当事者による事故調査という問題点を取り去って第3者調査にしたことが基本的進歩であり、その立場を活かして過去の大事故の記録を洗い直して隠れた真相を明らかにすることも必要だ。そうすれば隠れていた教訓が現れる可能性があり、書面審査が基本でも良いから予算と人材を投じて貰いたい。
たとえば参宮線事故では、人為エラーは機関士か駅信号係かで刑事裁判が争われて機関士の場内信号誤認で片付けられたが、確認困難な直前転換の可能性は否定できず、事故後の国鉄の対応を見れば「駅への同時進入禁止」や重連で非常制動が良く伝わらない欠陥対策で既に一部勾配区間で実施していた「中継弁設置」や「非常制動扱い合図制定」が全社で行われ、地上側にも手落ちがあったことは明瞭である。
鉄道信号は交通信号とは違い通常は停止→中間現示→進行と変化するもので、一旦進行を確認してから停止に変わることは何らかの事故以外は無いから大変見落としやすく、通常の操作としては「直前転換」として回避するタテマエだが操作が遅れた可能性は否定できない。この辺りが高裁で執行猶予に減刑された原因と考えられているがそれでも疑わしきは罰せずの刑事裁判の原則からは外れる。
前出の鶴見事故でも同様で、ワラ1型の軽荷重時の不安定を見逃したのは、営業運転開始前の走行試験を省略したことによるとか、最初の脱線箇所が緩和曲線カント低減部で、脱線防止レールを必要箇所に設置したという専門家には良く知られ、一般には全く伝わっていないことは公式にまとめた方が良いだろう。See→鶴見事故
現状の事故調査委員会の弱点は、国交省傘下の組織として、監督行政の可否に言及できないことである。土佐くろしお鉄道宿毛事故でのATS設置基準が信号ATSも過走防止ATSもどちらも最高速度に対応していなかったことは、運輸省認可のATS設置基準の問題で運輸相自身の監督責任はあるのだが、事故報告書に一言もないのはその弱点の反映である。監督と事故調査の分離は必要である。
しかし、尼崎事故調査委員会が「意図的な調査と調査委員会主旨にもとる判断」、「今回の事故に対すると同じように意図的又は法の主旨に沿わない調査が行われ、その結果に基づいて戒告、勧告及び業務停止などの行政処分が行われる事態」という、永瀬教授の尼崎事故調に対する敵対的評価は断固不同意だ。後述のように、永瀬教授の指摘する「誤数値」のソースはJR西日本の算出に拠るもので、それを前提に各種設定数値を実査したものがベースであるなど、永瀬教授の主張にも結構な歪曲が見られるからである。
一般的な解説では慎重かつ正確な解説をする永瀬教授だが、この鉄道を切る#26ではかなり不用意なミスを重ねている。乗務員経験者ならすぐ判る筈の誤出発防止地上子を出発信号の直下地上子と取り違え、また今縮刷版を当たれば判る東中野駅追突事故でのブレーキ扱いの事実を、尼崎事故で懸念した運転士体調不良説の補強としてノーブレーキ追突としたのか?従前の「慎重」な氏としては珍しい誤認だ。(注:氏が東中野事故調査に直接関わり、ノーブレーキ衝突はJRとしての結論だと尼崎事故意見聴取会での主張。新聞報道が誤報)
回送電車の宝塚駅到着での2度目の非常制動について繰り返し「直下地上子」に拠るものとしているが、停止目標より若干手前の非常停止位置からしてこれは6両編成用の「誤出発防止地上子」によるものである。(補足:永瀬氏が「直下ATS」と書いているのは「誤出発防止地上子」を指しているのかもしれないが、「直下」とは信号直下の意だから不適切。せめて「即時停止地上子」としないと通らない)
当初の報道では確かに「宝塚駅ホームでの過走による非常制動」だったが、それでは必ず停目を超えて、手前に停まることはない。実際は最初の非常停止の位置で誤出発防止タイマーが起動してしまい、再発車で移動中、停目到達前に誤出発地上子が有効になったものである。これは最終報告書に明記されている(pL)し、その位置関係については中間報告書にも記載され、さらに誤出発地上子動作の注記もあり、2度目の非常停止位置からして6両編成用誤出発防止地上子が働いたであろうことは明白だった。
それを「直下地上子」とするのは当初の報道による情報のままであり、永瀬教授が中間以降の事故調報告をきちんと読むか、非常停止時の地上子と車上子と停目の位置関係を自ら検討していたら「直下地上子」とするのは考えられないのだが………、機能の区別のため地上子の塗色は異なるがその物理特性として、共振周波数は即時停止の123kHzで同じものである。それを停止現示で有効にするのが直下地上子、領域進入からの時素経過で有効にするのが誤出発防止地上子である。
東中野衝突事故では、衝突7m手前からブレーキ痕があり、運転士による非常制動痕と解されている(88/12/07毎日等)。それは衝突後停止位置、先行車停止位置、Y現示速度など他の条件と突き合わせて整合性のある数値で、ブレーキ無操作での衝突ではないから、今回永瀬教授が例として援用できる事故ではない。遅延防止にATS警報受信時一旦停止規則を無視せよと言う「千葉支社通達」通り、Y現示制限55km/hを守って保ち位置で制動なしに確認扱いして52km/hでそのまま東中野駅に突入して、直前で気付いて非常制動を掛けたと思える諸データであった。これとは別内容の事故調査報告書がJR東日本など何処かに存在するのだろうか?(See→永瀬氏は東中野事故調査を直接担当と述べている)
「誤認」とまで言えるかどうかは別として、現在のVVVF制御車では常識化している滑走再粘着制御(航空機の着陸後減速や自動車で言えばアンチスキッド制御)は、鉄道では開発が遅れ、しかも当初は制動距離短縮よりフラット防止に主眼が置かれて滑走を検出すると遅速に関係なく前後両側を緩解する仕様で実質は整備工数を減らすためのフラット防止装置なので103系試作車と201系試作車には装備されながらそれらの量産車では取り外されて、0系新幹線でも最長800mにも及ぶ過走事故を繰り返していて、鉄道総研が北海道特急用の4軸独立微分制御型の滑走防止装置を開発実用化するまでは在来線の量産車には採用されていないはずのもの。すなわち、時期的に207系には再粘着制御(滑走防止装置)は採用されていないはず。それで高減速度の運転をすれば雨天など悪条件下で滑走して停車位置を行き過ぎるなど安定した運転ができないから、社内規定としても2.5km/h/sとしていた。それでは運転曲線を算出するのに、高減速度を設定できないではないか。そんな無茶な設定を前提に事故調攻撃をしてはいけない。
福知山線のダイヤは、「一旦遅れると取り返せないギリギリのダイヤ」という乗務員たちの話があり、事故調として調査の結果、JR西日本のダイヤ設定方針として「余裕時間ゼロ」を採用したことが基本にあり(報告書p140〜1)、同社のコンピュータに残された運転曲線の計算経過を点検すると、算出に際しての設定値が非常にデタラメで、7連列車の全長140mを運転曲線ソフトには10mと設定して算出していたり、先行列車通過後の出発可能時間を実際より短かく設定したり、客扱い時間が実態に合わずかなり足らなかったり、線路勾配の正負を4箇所で間違えていたり、採時地点が駅によりマチマチだったり、乗務員に不徹底だったり、使用していない高加速スイッチを投入と設定して算出していたり、一部でブレーキノッチを1段低いB5で教育していたり、などのミスが見つかって、想定の時間的余裕がゼロや駅間で負になる列車があって、ARC/CTC記録から尼崎駅で定常的に遅れていたことを明らかにした。
これに対し永瀬教授は、遅れは東海道線列車に接続するための尼崎駅の機外停止で生じており、その時間余裕に無関係の遅延分を除いて処理すれば余裕はあり、それまでは隠れ余裕で取り返して埋めているから差し支えなくダイヤに無理はなかった。ARC/CTCの記録は分解能と誤差に問題がある。事故調の補足した運転曲線算定は「私鉄A社方式」を唱いながらその設定値を変えており、電源電圧1500Vを私鉄A社設定1350Vまで下げ、加速度をJR設定の2.5km/h/sまで下げて、JRの「鋸歯状運転」での算出を知らずに、私鉄A社の「定速度運転」での算出と同列に評価した上で、JRの設定速度が最高速度で余裕ゼロだと非難している。
計算違いと思われる区間も有るし、この誤った設定は無理が有ったと結論づけるための意図的なものだ。というのがおおよその論旨である。
「東海道接続機外停車主因」、「鋸歯状運転」とか「1500V→1350V」とか「2.9km/h/s→2.5km/h設定」と並べられるとかなり説得力ある指摘だが、釈然としないのは、論旨のどこかに実態とのズレが有るからだ。
(補足:公述書3項参照):「先行列車の東海道線接続のための機外停車の場合を除いて集計すれば遅れはない」という直接の裏付け資料は見つからない。機外停車分を除けばその分不足時間は減るが、全部解消するかどうかの実証データはない。永瀬教授は公述書で「基準運転時間」では不足があっても、「基本運転時間」ではまだゆとりありと主張している。
そもそも「回復運転」というのは(調整余裕時間を設定してなくても)運転士がその技量で隠れ余裕時間を絞り出して行うもの。多くの列車が尼崎手前時点で遅延ゼロに戻していたとしても「一旦遅れたら回復不能」という乗務員の評価は消せないではないか。それは永瀬教授の言う「隠れ余裕」が小さすぎることを示すもので、熟練の運転士が運転秘術を尽くしてようやく定時刻維持で、外乱が有ればその分遅れるというのは「問題ない」のではなく「余裕がない」と言うべきである。教授はこの点(なぜ遅延回復しがたいという評価か)に触れていない。
それ以上に、事故調報告の記載構成としては、JR西日本の基準運転時間と運行時間を基に各項目を確認していく中で不足項とその不足時間を指摘している訳で、「計算が違う」としたら元となるJR西日本自体の計算が違うのである。それで事故調を責めてもお門違いと言うものだ。それこそ元々のJR西日本の算出のどこに問題があったかを指摘するのが筋である。
しかも「一旦遅れたら回復困難」という事実は変わりなく、細かな設定パラメターの相違や計算値の違いを言い立ててもそれは木を見て森を見ずの誤りと言うほか無い。すなわち永瀬教授の主張は実質的には福知山線運転士の技量は未熟者ばかりだと言っているに等しい。いや公述書では言っている。仮にその場合でもその「未熟者」に合わせた余裕時間は取らなければならない。運転実績で「ゆとりがない」と言ってるのに、机上計算で「ゆとりはある」となったら、机上計算に実態と違う無理が入っているということだろう。基本的にここの判断が間違っている。事故調報告の評価の方がまともだろう。
ソフトの現物を確かめられる立場にないから主張を聞くだけというのはあるが、最高速度に達したら惰行運転に切換え、一定程度速度低下する毎に再度最高速度まで加速を繰り返す「鋸歯状運転」をそのまま運転曲線ソフトに取り入れるのと、私鉄A社方式の平均一定速度で最高速度から2〜3km/h低い値で算出するのは、ほとんど同じであり、前者のJR西日本方式が無理をしている訳ではないという永瀬教授の指摘は、前提がその通りであれば、その通りだ。鉄道について知悉した人たちでないとの指摘の具体例にあたる。
(永瀬レポートに解説している)鋸歯状運転というのは、目標速度まで加速しては惰行運転に入り、速度低下すると再加速して目標速度に戻す、在来線では標準的な運転方法である。仮に速度低下5km/hで再加速を繰り返した場合、私鉄で採用の等速度運転近似では最高速度より2km/h〜3km/h低い速度として計算するのと変わらないから、「最高速度での算出に変えた」といってもJR西日本がことさら無理な計算をした訳ではないという指摘である。
しかし、その前は2〜3km/hの余裕を設定していたから、作成基準を厳しくして基準時間短縮を図ったことは疑いない。
国鉄JRの減速度設定は、運転実態に合わせて101系103系時代に2.4km/h/s、その流れを汲んでの2.5km/h/sの筈だ。(JR社内規定(p148L1)は減速2km/h/s、停止制動2.5km/h/s)。近年再粘着制御付きの15両編成が100km/h超から減速を開始し80km/hでホームに突入して停目に停まる(常磐、総武・横須賀、東海道、湘南新宿など)かなりダイナミックでスリリングな運転を見せているがそれは均せば3km/h/sに達していない(2.963km/h/s=80^2/(20*15)/7.2)。雨天等悪条件では高減速度は保障されないから、実務的には幅を持たせて2.5km/h/sなどで算出してきた訳である。問題のJR西日本207系には再粘着制御(≒アンチスキッド制御)はまだ無かったはずだから2.5km/h/sは大変妥当な値だろう。(引用数値、標準値と誤認に付き1行削除)私鉄の運転曲線算出の減速度設定が3km/h/s以上の会社が多いとしても、再粘着制御も無しでの高減速度設定には無理があり、その性能次第で設定値を決めるだろうし、客扱い停止時間の設定、制御器応答時間設定や余裕時間配置で変わるものだから、滑走再粘着制御のない207系の減速特性に合わせて社内規定通りの2.5km/h/sとするのは妥当なのだ。そこを含めて論じないで「2.5km/h/sはA社方式ではない意図的な算出数値」というのは全く当たらないどころか逆に「意図的な誤導主張」になるのではないか?定速運転か鋸歯状運転かといった計算上の仮定の組み合わせをもって国鉄JR方式とか私鉄A社方式とか呼んでいるのであり、具体的な設定パラメター(この場合、設定減速度)を以て方式呼称が決められる訳ではないだろう。だから、それを以て直ちに「意図的歪曲」とは言えない。
事故調報告には前述のような弱点もあるが、どこもそれほど大きく外れている訳ではなく、常設の鉄道事故調査委員会の陣容強化の必要を強調するあまり、現職を引き合いに出して叩く内容はかなり行き過ぎだと思うが………。特に指摘内容とその評価・現事故調委員排除に繋がる主張が噛み合うのかどうかかなり疑問を感じてしまう。
航空事故調査委員会は国家資格を持った委員が就任しているが鉄道事故調査委員はそうではなく、「鉄道に深い造詣を持つ者が調査を担わないと今回と同じような問題が起きかねない」(末節、おわりに)とこき下ろしているのはどう見てもやりすぎ。
永瀬教授は、事故原因についての言及は非常に慎重で、マスコミに対しても具体的結論はまず言わないが、JR西日本を厳しく批判した事故調に対してだけは事実を歪曲してまで明確な否定的結論を出すというのでは、評価基準がまるで違うダブルスタンダードで、それこそ特別の意図が無いかどうか疑問に感じてしまう。それでは単なるJR西日本擁護代弁人ではないか。世論に厳しく叩かれたJR西日本社長の「事故調はひよっこ」発言('07/08/04事故説明会)のソースであることを十分疑わせる無理な主張である。
研究畑・教育畑では特定法則に着目して、他の要因を誤差として補正や切り捨て処理して結論を導くので、たとえば高校物理実験で斜面落下など精度の上げられない計測法で落下の法則を導く実験ではそれこそ「思い込み」と紙一重の誤差だらけの実験結果から「法則性」を宣言する訳だが、これが現場に行けば、考え得る様々な要因を並べてそれぞれの寄与率を検討して一つ一つ項目を潰していく。シビヤーな金絡みだから経済的合理性には厳しい反面、極端な話有効だと判断されると理由は重視されずに取り敢えず実行してみることさえある。こういう現場感覚と、研究・学際感覚の相違は現れて批判対象にはなり、新卒社員もその違いに気付くまで暫くは強烈な批判に晒されることはあるが「意図的歪曲」とまでは到底言えない。
早い話が、運転士の身体的異常突発も疑われる状況があるのに、これにほとんど触れず、懲罰的日勤教育に繋がる無線のやりとりに気を取られて制動操作時期を逸したことを原因としてJR西日本非難に集約させたのは不当という、懲罰的日勤教育有用論側のもう公けには言えない恨みつらみ不満を外部から代弁したものではないだろうか。
常に予算のない学校への教材・研究費確保のためにスポンサー相手に割り切って幇間芸を演じることも必要な現状があり否定しないが、せめて悪い副作用が出ないように配慮して貰いたい。既にJR西日本首脳の「事故調ひよっこ論」のソースとして疑われるし、JR西日本は最後までその非を認めず最終報告書直前の意見聴取会でさえ副社長自らが「懲罰的日勤教育有用論」を強調、激しい指弾を浴びてから、最終報告書を承けて「安全基本計画」を発表して「あり得ることは起こること」「人為エラー発生を前提の対策」という労災防止では古くから追求されている妥当な方針を初めて打ち出したのだが、従前の無反省な主張からその本気が疑われている訳で、それを口先だけで風除けを策する方向に勢い付けるヨイショを学識経験深い方がなさるのだけは勘弁して欲しいのだ。(まさか内向けのヨイショを立場を忘れて外向けにひよっこ論を喋る御仁が首脳とは思わなかった!不運な事態とか(w)。JR西日本もスクラップになる廃車部品が専門教材になるのなら変な反対給付を求めず欲しいところに寄付・譲渡すれば良いではないか。校舎の外は公道という都心の学校がガラクタを貰っても迷惑というのもあるが、八王子など郊外の山上に移転したキャンパスなら空き地は十分だ。
|
2.14.5.1 運転曲線作成システム |
永瀬教授の意見聴取会「公述書」3項に対する事故調としての反論が章立てせずに、本文中に埋められていた。(右枠内参照)
「(運転曲線)作成システムについては、加減速が実際と異なると見られるところがあることなどから、それにより算出された「計算時間」は、必ずしも実際に要する時間と一致しない。」というのが永瀬公述に対する事故調の見解だった。
現場では実績優先でないと転がらないから、後から「運転曲線作成システム」を導入して短い所要時間が算出されても、実態との繋ぎで補正値を加算したり補正係数を掛けたりして「理論計算」には含まれなかった誤差要因のどんぶり勘定的補正をして辻褄を合わせるもので、この場合のJR西日本「運転基準時間」もそういう経過があって単純算出値に優先して制定したものだろう。たとえば主幹制御器を操作しても起動や電制は1秒近く遅れるが算出システムには設定されてないといった細かな抜けがあるのだろう。正確な算出システムが構築されるのが望ましいが、まだ実態に合わない開発途上システムを補正しながら使っていたということだろうか。
事故調がその辺を非常に穏やかに指摘して永瀬公述の検討不足部を庇っているのに、今頃、改めて尼崎事故調非難を提起して「専門家不在の現行の鉄道事故調査機関に海難審判庁と同じような権能を将来的に持たせることになるならば、問題である。なぜなら、今回の事故に対すると同じように意図的又は法の主旨に沿わない調査が行われ、その結果に基づいて戒告、勧告及び業務停止などの行政処分が行われる………」というのは言い過ぎではないだろうか?客観事実から離れた会社寄りの無理な攻撃的主張をされる永瀬氏こそ逆に事故調委員としては如何なものだろう。
| 基 準 運 転 時 間 | 「計算時間」(試算値) | A社方式 基準運 転時間 (試算値) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基 本 | 本 件 基 準 運転表 | 本 件 運転士 メ モ | 乗車率 50% | 制 限 速 度 −2km/h | 減速度 毎 秒 2.0km/h | A社の 計算方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宝塚駅(2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3′15″ | 3′11″ | 3′07″ | 3′09″ | 3′08″ | 3′13″ | 3′15″ | 3′17″ | 3′20″ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 中山寺駅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3′10″ | 3′08″ | 3′09″ | 3′09″ | 3′05″ | 3′11″ | 3′12″ | 3′13″ | 3′15″ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 川西池田駅(3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2′20″ | 2′21″ | 2′19″ | 2′21″ | 2′18″ | 2′22″ | 2′21″ | 2′24″ | 2′25″ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 北伊丹駅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1′30″ | 1′31″ | 1′33″ | 1′41″ | 1′33″ | 1′34″ | 1′37″ | 1′35″ | 1′35″ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 伊 丹 駅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2′20″ | 2′12″ | 2′23″ | 2′18″ | 2′08″ | 2′12″ | 2′12″ | 2′16″ | 2′20″ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 塚 口 駅(3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3′00″ | 2′44″ | 3′04″ | 3′08″ | 2′44″ | 2′48″ | 2′47″ | 2′49″ | 2′50″ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 尼 崎 駅(6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_
|
| 計 | 15′35″ | 15′07″ | 15′35″ | 15′46″ | 14′56″
| 15′20″ | 15′24″ | 15′34″ | 15′45″
|
※なお、提出運転曲線の「計算時間」の計は14′45″である。 | 赤字は永瀬公述書3項が根拠にすべきだと指摘する単純算出値。 | ||||||||||||||||||||||||||
加算や係数による補正は、厳密な理論を追っても意味の薄い現場では当面の辻褄合わせに結構使われる。それで仕事が転がれば良いのだから。
昔、某社の小型直流モータのテキスト的設計資料には、直流機の教科書通りの設計式が記載されているのだが、その中で何故か2極3溝モータの式にだけ解説無しに0.95という係数が掛かっている。理由を尋ねると「ワカラン。合わない分の補正だ」というのである。市販テキストを残し某X社にヘッドハンティングされた前任CAPの時代の設計資料で、某重電Y社設計幹部からスカウトされたばかりの新CAPも「細かいヤシはまだようワカラン」というのに製品はとっくに量産されていて全く差し支えないのだ。この手の現物合わせは現場には転がっていて、さほど厳密を要しない部分を繋いでいるが、問題の運転曲線算出システムは改良を経ているというのに誤差が若干多目ではある。算出に必要な情報が十分得られないのは肝心の現場からはあまり頼りにされていなかったのだろうか。(注:定数0.955は理論解明済み)
謎の係数0.95の原因追求をやると、教科書で扱われる大型機は、電機子各コイルの発生電圧が台形状なのに対し、2極モータでは正弦波に近いことに気付いた。その3溝モータでは3相交流発電だから、発電波形に歪みがあると各巻き線の3N次高調波は同相で加算されて環状結線(Δ結線)に短絡されてほぼ正弦波化される訳で、コンミテータ(整流子)により6分の1回転=60度回転毎に接続が切り替えられるはず。その発生電圧は最大値Vmに対して±cos30度の範囲で変動するはず。その平均値はcos函数の0〜30度の平均を求めれば良いはず。
平均値(3溝)=∫030゚cosθ dθ/30゚
=[sinθ]030゚/(π/6)
= 6/π*[1/2−0]=3/π≒0.955
平均値(3溝)=∫30゚−30゚cosθ dθ/60゚
=[sinθ]30゚−30/(π/3)
= 3/π*[1/2−−1/2]=3/π≒0.955
これが謎の係数0.95の正体であった。目の子での係数補正で走って正しかったことが証明できた訳である。
5溝、7溝は1.0に非常に近い値、9溝以上は1.0。
微妙な差を理論的に解明できるまでは量産するなとはならないだろう。理論値と現実値が違うのは理論値側に未考慮の要素があって違いが出るので、現実の計測値が間違ってるのではない。
永瀬公述はここがあべこべなのだ。
| [Page Top↑] |
 旧 |
 新 |
 前 |