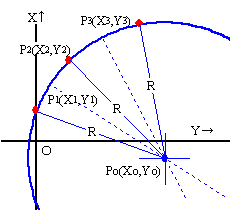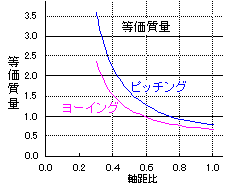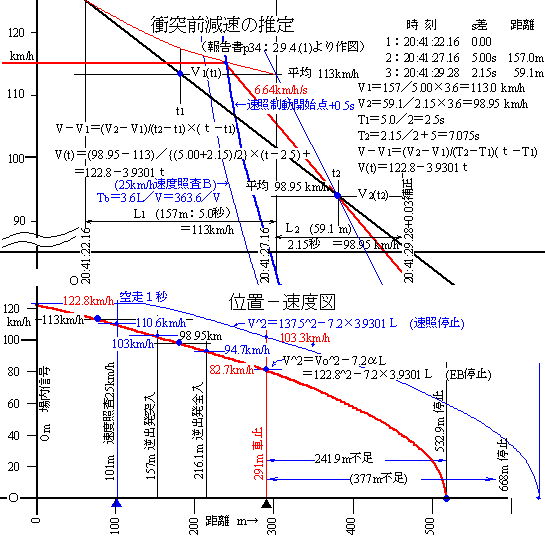|
|
|
|

BBS
|
mail to:
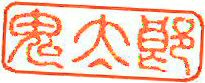 adrs adrs
|

旧
|

新
|

Geo日記
|

前
|

主目次
|
|
[167].8月度記事upの整理
夏休み前後は日記部を1ヶ月も放置してしまいましたが、その間に興味に駆られて記した部分を整理します。
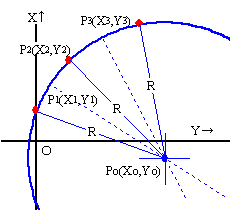
3点を通る円の半径と中心座標を求む
先ずは地図や航空写真から曲線半径をなるべく正確に求める方法としてGoogle Earthの分解能1/100秒の経緯度表示機能を利用して、曲線上の3点の経緯座標を読み取り、地球半径からX−Y相対座標に変換、3点を通る円の半径として算出すれば誤差±5%程度の精度で計測可能でした。ほぼ実用水準です。
See→【Google Earth で曲線半径計測】
→[経緯度相対座標変換]
→[曲線半径計測例]
鹿児島線宗像海老津追突事故(02/02/22)の解析に際し、現場の状況が良く分からず、地図から正矢法で曲線半径を求めたものの比較対象地図で得た数値の誤差が大き過ぎて採用不能だったものです。誤差の原因が地図側にあるのか計測法にあるのかは突き止められませんでした。
【正矢と弦から半径を求む】
在来線曲線簡易管理法は10m弦での正矢法です。正矢から曲線半径を求める方法を整理しておきました。曲線標識裏面の「V=nn」というのが正矢です。

300R標識
総武線両国駅上り出発信号付近
等価質量(軸距比)
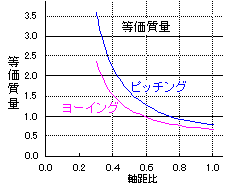
|
軸距と車体長の関係は?(等価質量)
東海道線鶴見事故で、最初の脱線原因とされたワラ1型貨車は事故後の対策として云われた「2段リンク式改造」はワラ1型にとっては元々の懸架構造であり対象外のはずです。重要な事故要因である「軽荷重時の走行不安定」は軸距を伸ばす改造であることが伏せられたままになっています。最近亡くなった故久保田博氏がワラ1型の走行不安定を見逃した原因についてその著書「日本の鉄道車両史」(2001年刊)で事前の性能試験を「ワム60000類似車」として省略していたことを明かし「性能テストは実施すべきであったことが教訓として残された」と述べているので、軸距比がどの程度効くのかを解析してみました。ワラ1型の原寸法は判らず、当時多数存在したワム70000型も紙一重の微妙な数値であり、現在軸距比の長いワム80000だけが生き残っており、基本的には不安定な2軸車両は避けよと言うことですね。
See→[2軸車操向等価質量試算]
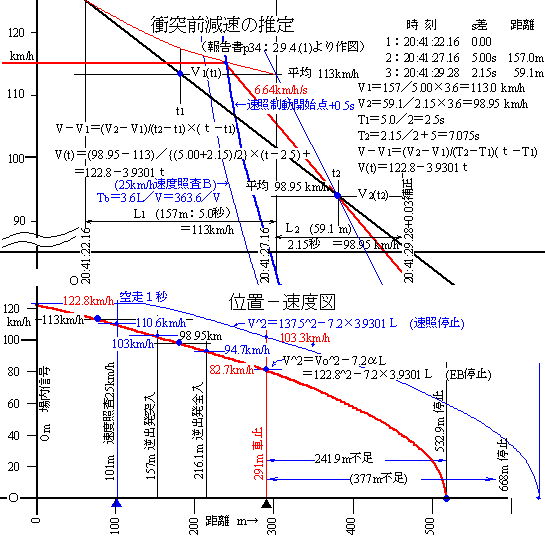
宿毛事故:補足
宿毛事故最終報告書で、閉塞区間の状態記録に車止め衝突寸前の時刻が残され、その記録と閉塞区間長、継電器の動作遅れ時間、速照地上子設置位置から突入時の運転曲線の有り得る範囲が算出される。事故調報告では「EBが動作した可能性は有る」「25km/h分岐速照動作」となっていました。
そこで、残されたデータを整理すると、分岐速照による非常制動で記録通りに走行するには6.64km/h/sの減速度が必要で、それは滑走が起こるため実現できない可能性が高いことが判りました。
EB動作とすると一様の減速度が約4.0km/h/sで、その時の場内信号突入速度が約125km/hだったことになります。
報告書は聖ヶ丘トンネル最高地点通過後、突入時のノッチは低い位置であったことを強調していますが、どこでEBが動作したかは正確には判らず、トンネル内最高標高地点で下り勾配に変わりノッチを下げたとするとトンネル出口手前で最初のEB確認要求ブザーが鳴り、これを確認ボタン操作でクリアしてその61秒後は宿毛駅場内信号直前付近で次のEB確認要求ブザーが鳴って、5秒放置で非常制動に見舞われたとすると、丁度宿毛駅場内信号付近で非常制動になり時間軸でみるとそれ以降4.0km/h/s弱でほぼ一様の減速線:距離軸でみれば放物線でと言うことになります。
減速度が4.0km/h/s「弱」というのが事実の鍵なら、場内信号に突入した途端にEBによる4.0km/h/sの非常制動に見舞われたことになります。制動力の強いE233系の最大限速度が5.0km/h/sとされており、パウダー噴射など特別の機構を持たないディーゼル特急車両が晴天とはいえ6.64km/h/s減速を実現する可能性は先ずなく、最も有り得る可能性は場内信号付近でのEB動作による非常制動でしょう。
See→125km/h余からEB制動か?宿毛事故
See→EBの穴が直撃:補足
宿毛事故:欠陥通達(H17国鉄第195号)が改訂される!
最高速度100km/h以下の路線や、ATS-SN路線、合流点、交差点での防御を義務付けなかった欠陥通達「H17国鉄第195号通達」が実質廃止され、技術基準改定として事故発生の危険性(可能性)のある線区に設置が義務付けられました。文面は抽象的で判断を各鉄道事業者に任せた形の「国交省アリバイ構成通達」ではありますが、事故発生の結果責任だから実際問題として大手はこの通達を無視できなくなりました。
See→欠陥通達実質改訂さる
(この8月も見掛けよりは記事を書いていました(苦w。図やグラフというのは頭の中にはパッと閃いて簡単そうでも実際は表計算のグラフ機能を使ってもかなりの作業量になります。花子用によく使う汎用部品は準備してるんですが、解析、確認と併せて数日掛かったりでつい横着になりがち。BASICでグラフの方程式を描いてその画面をファイルとして取り込む様な真似をしなくて済むようになったのがWindows系アプリの功績です。一回り余の昔は取説用技術資料用画像の描画方程式を座標変換でトラブりながら必死に作ってました(w)。高速繰り返し型アナコン(=要するにCRTオシロスコープで観測する型。ペン・レコーダなんて普及前でしたから)の時間軸変換とかめったやたらに座標変換作業が多かったのを憶えてます。
2007/08/30 22:55
|
|

旧
|

新
|