[166].
 BBS |
mail to:
| ||||
 旧 |
 新 |
 Geo日記 |
 前 |
 主目次 | |
[166]. |
| |||||||||||
宿毛事故の最終報告書が出され、概ね予想通りの内容だったが、想定外が、当初報道の窪川出発時の遅れがなかったとする報告と、衝突前のEBによる非常制動の可能性を指摘して諸データを提示している(報告書 p34下段2.9.4.(1))ので、先ずはEB動作の試算を行ってみたい。
閉塞の記録単位が1/100秒、取得データが2.12秒〜5.00秒なので、かなり正確に状況を推定できるだろう。当初は最悪1〜2秒の誤差を予想していたが、設置機器の進歩は予想以上に早かった様だ。
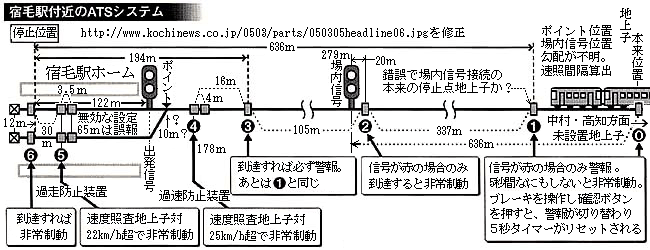 See→[宿毛事故解析] |
| ※上図の設置位置636mは2000系専用(空走1秒、非常減速度4.6km/h/s)試算で、ATS-S標準の設定では737m(空走時間2秒、制動定数:20/0.7=3.968km/h/s減速度)となる。 |

|
|
→4).式を時間で積分してtを消去し距離xの函数とする 原式V(t)=V0−αt [km/h=3.6m/s] ……4)'だから x=∫V(t)/3.6 dt+X0 =(1/3.6){V0・t−(α/2)・t2}+X0 =(t/3.6){V0−(α/2)・t}+X0 ………5). αt=V0−V(t) t={V0−V(t)}/α ………6). これを5).に代入 x={V0−V(t)}/3.6α・[V0−(α/2)・{V0−V(t)}/α]+X0 ={V02−V(t)2}/7.2α+X0 ………7). ∴V(t)=sqrt[V02−7.2α(x−X0)] ……8). (但し7.2α=K:制動定数) 先の試算値、V0=122.8km/h、α=3.9301km/h/s、X0=0mを当てはめると、 V=sqrt{122.82−(7.2・3.9301)x} ………8)' 但しxは場内信号からの進入距離 試算:車止め位置291m(=157+122+12m) の突入速度は V=sqrt{122.82−(7.2*3.9301)・291}=82.73km/h 試算:V=0 時の走行距離は、 V02/7.2α=122.82/(7.2×3.9301)=532.9m ………実制動距離で241.9m分車止めに食い込んだ! |
トンネル内あたりから意識朦朧でEBをリセットしつつ緩やかに加速し、場内信号手前でEBによる非常制動が働き、実減速度3.9301km/h/s、場内信号突入速度122.8km/hで車止めまでに停止しきれず82.7km/hで車止めに突入したというデータを提示している訳である。
一般的に低速側で減速度が増えるので突入速度は更に下がる。運転士以外は救命された被害からみても90km/h前後での激突となる信号計算の最低減速度4.0km/h/s弱よりはEB制動が実際に近い可能性がある。
(→See.報告書写真9:フラット写真参照。以下07/07/27↓宿毛事故調報告書)
http://araic.assistmicro.co.jp/araic/railway/report/RA07-4-1.pdf URL変更↓
http://www.mlit.go.jp/jtsb/railway/rep-acci/RA2007-4-1.pdf

この報告書に拠れば、最終のEBリセットが聖ヶ丘トンネル出口手前での何等かの運転操作、或いはEB確認ボタン操作で、それから61秒の無操作を経て警報が出されるが、この地点ではもうブレーキを扱っても車止めに激突する位置の可能性があった。聖ヶ丘トンネル最高標高地点4,641mから下り8/1000勾配となりノッチを1〜2に戻すことでリセットされ、ここから61秒後にEB警報となり2秒後にリセットして平均120km/hとすればここが約2,541mのトンネル出口直前で、次の61秒+5秒+空走1秒を平均123km/hで走ると251m位置で、ここは前出略図に見るとおり場内信号を28m過ぎた前後の位置になるから減速度5.08km/h/sでも絶対に停まれず前述のように70km/h超で車止めに激突する。
まさに「EBの穴」と言うべき配置となっている。これを回避するには、減速定数K=20/0.7=減速度20/0.7/7.2=3.968km/h/s(ATS-S算出基準)=4.0km/h/s(事故調報告算出基準)、空走時間2秒+5秒の条件で737m位置でEB警報しないと意味がない。(=終点に対する警報地上子がここに必要。)。もっともトンネル内で1回はEB警報をリセットしており、再度リセットされたら意味はない。こういう個々の条件を想定をできないEBは単なる気休めに過ぎない。速照より数秒早かった分は若干有効で乗客を救命したが………厳密に言えば25km/h速度照査で非常制動となった場合の車止め突入速度約103.3km/hをEBの働きで82.7km/hに抑えて死傷者を減らしたが事故は防げなかったし、正常運転での警報を繰り返すオオカミ少年型安全装置では無意識の習慣的リセットで意味がなくなる。必要充分な特性値(=停止信号では停止位置からの距離)を選んで管理すれば最低1地上子で済む過走防止装置が、モグラ叩きのATS-Sxでは9組18基の地上子が必要でしかも最低減速度列車の制動特性に規定されて使いがたい代物になってしまうのは当然なのだ。安全確保には停止限界位置に対応した速度照査、速度制限は必須である。
宿毛事故を承けて05/03/29に過走防止装置設置通達(平成17年国鉄第195号)が出されたが、大変な欠陥通達で、対象が100km/h以上路線の行き止まり駅のみで、100km/h未満や合流点は放置のうえATS-Snには強制停止を義務付けなかった。→[参照記事]
それが、報告書の事故後の対応項を見ると、直後の福知山線尼崎事故対応を承けて、翌年06/03/24発表文書でその欠陥の総てを埋める技術基準の改定が公布され、曲線、分岐、線路終端、その他重大事故懸念箇所の速度制限を義務付けたことで通達の欠陥は埋められることとなった。
http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha06/08/080324_.html
公布日 平成18年3月24日(金)
施行日 平成18年7月 1日(土)
改正の概要
(1)速度制限装置の設置
曲線、分岐器、線路終端、その他重大な事故を起こすおそれのある箇所への速度を制限するための装置の設置を義務化及び………(以下略)
この技術基準改定は、JR東海がY現示速度以下の過走を防御することをもって「ATS-P並の安全性」としていたATS-ST過走防止装置の高速側無防備を直撃することとなって、1点あたり最低18基もの地上子を設置するよりも、従前全面否定だった最低1基で実現可能なATS-PTへの換装を決定させるものとなった様だ。JR九州がATS-Xの運用実験を引き受けているという風の便りは聞くが、サンライズ湯布院とかの直通を想定するとき、安価になったATS-Pを袖にして現示アップ更新方式が違うだけで互換性のない他方式を採用するだろうか?(軌道回路用アンテナ周辺と伝送周波数以外は処理ロジックの問題だからP/X共用車上装置開発不可能ではないが)というのが疑問。ほぼ同一価格でP/X両用車上装置を開発する方針なのだろうか?あるいは'86年運用開始のP系はパテントで耐え難く酷くぼられているのだろうか?
リスクをほぼ同じに揃える観点からは、尼崎事故を承けた曲線速度照査を徹底すれば、他の個所の速度制限と過走防止が当然設置基準に入ってくるからその点では技術基準に妥当な改訂が行われた。これによりまだ不足する安全確保項目は停止信号時の冒進速度制限=私鉄ATS通達仕様復活となった。
(細かに見ると、Sx速照の設置が防止じゃなく処罰トラップに見えるようなものがあって、その設定の考え方の整理が必要な項もあるが……少なくとも宿毛の過走防止装置は妥当なものに補強修正された。)
 旧 |
 新 |