[280]
 BBS |
mail to:
| ||||
 旧 |
 新 |
 Geo日記 |
 前 |
 主目次 | |
[280] |
| |||||||||||
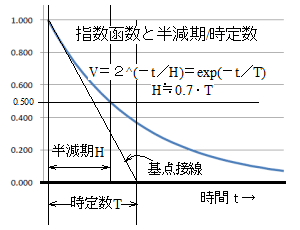 (どの時点から見ても同じ関係になる。↓以下参照)
指数函数 V(t)=A・exp(−t/T) の
任意の点t1での接線方程式を求めて、t軸との交点t2を求める。 | 座標と勾配で接線方程式が決まり、その Y=0 の点t2を求めればいい。 点P(V0,t0)を通り、勾配αの直線を現す方程式は v−V0=α(t−t0) であるから、t1での函数の勾配と座標を求めれば接線方程式を求められる。 勾配 d/dt(V(t))=−(A/T)exp(−t/T)、 ∴d/dt(V(t1))=−(A/T)exp(−t1/T) Y座標 V(t1)=A・exp(−t1/T) ∴接線方程式:y−Y座標=勾配・(t−t1) すなわち y=−(A/T)exp(−t1/T)(t−t1)+A・exp(−t1/T)=0 (t2−t1)=T となって、t1から時定数T経過した点t2がt1での指数函数の接線とt軸の交点になる。 |
|
既知の概念として記事中に意識せず使ってきたdB(デシベル)の解説がないことに気付きまして、自前で説明を試みます。工高電子など工学系専門科目でしか扱っていない様で、騒音・振動訴訟報道などで一般には内容を理解されないまま使われています。 デシベル[dB]とは (解説) <4>
主に振動的な物理量を現す際に、人間の体感特性が概ね対数的であることから、基準の値を定めて、そのエネルギー比の値を対数で現すに際して常用対数である10底の対数値で現して[ベル(B)]とし、さらにそれを10倍した[デシベル(dB)]が扱いやすい値として広く使われている。すなわち基本定義式は
[db]という表記は1950年代頃まで電気通信で使われたが、人名由来の単位は大文字表記とする国際的規約が浸透して[dB]表記に統一された。 勧奨・誘導と処罰で強制は違う! <4.2>国が「標準」を定めて推奨するのは良いが、刑事罰を以て強制するのは間違いだ。 一時、インチ規格のネジの入手に苦労した時代があったが、日米経済摩擦で強請られて飛行機B747などインチ規格製品がフリーパスで輸入されるようになり、実態としてメートル強制が消滅した。加速度単位を[m/s2]に「統一」させた筈が、阪神淡路大震災報道から一挙に[gal:ガル=cm/s2]が復活してしまった。 鉄道で、機関車のけん引力が[トン]だったものを[kN:キロ・ニュートン]に切替させたが、実作業を考えれば「総重量1000トンの列車を25/1000勾配から引上げる勾配抵抗は25トン(=1000×25/1000)∴牽引力は30トンほしい。」と言えた方が「245kN:キロ・ニュートン」より直截。加速度Gとか、音速マッハも消せなかったし、真珠取引規格単位の匁(もんめ)は当初から例外として許容した。 同様に、停止制動距離が時速の2乗に比例することから、比例定数として制動定数を定義して、「制動距離=時速^2/制動定数」と単純な形にして、それを基に列車種別ごとに制動定数をさだめ、その最高速度を制定していたものを、単位系を変えて管理規則・定義式までややこしくする改悪が行われた。 しかし理論解析など国際単位SI(MKSA有理単位系)の方が便利な場合は処罰なしで普及した。 また、物理学嫌いを大量に生んで高校物理教科を暗記物に貶める愚行に大いに寄与した不可解な単位:cgs.esu/cgs.emuなど現在ではほぼ消滅してしまった。 本来は事実認識力&法則性抽出力涵養の学問であり決して暗記物などではないのが本来の物理学! 名義貸しなのだろうが「朝永振一郎監修」を表示する我が高校物理教科書(電気科&機械科1年、化学科2年、普通高校3年)は、電気関係の多くをcgs.esu/cgs.emuで記述していて、その部分は授業から割愛し、工業専門科目に任せて、「電気理論」電気科1〜2年、「電気一般」機械科、化学科3年でMKSA有理単位系(後の国際単位SI)で学んだから私自身はcgs.esu/cgs.emuの被害を受けずに済んだ。 その後私は「教科書だけは難しい」と揶揄され、関東の高校理科教師の半分近くを送り出したという伝説の理工系大学に進学したが4年間cgs.esu/cgs.emuは全く出て来なかった。 物理を選択する高校生は、かっては80%台だったものが今や20%を切っているとか。産業立国を支えた基礎教育の一端が崩壊しつつある。 文部省には長らく高校物理学の適切な指導監修能力が不足して居る様である。 類例では明治政府の太陰暦禁止・太陽暦強制の力技がある。太陽暦の適切性、欧米を目指す近代化政策の一端ではあったが、内湾漁師のように潮汐=潮の干満で月間の作業を配置する人達は困ってしまい、取締り処罰回避に太陰暦の載る占い本を使うようになった。半農半漁の母方本家には常備されていた。 これは現在でも年末年始の本屋に平積みで並べられているし、最近はコンビニにまで置かれている。太陰暦禁止が根深い占いブームを招いた様だ。 商取引など諸権利に直接関わるもの以外は、処罰を以て使用を強制してはイケないだろう。遣りすぎ! 欧米が未だにヤード・ポンド法のままと云うのに、日本はメートル・グラムを刑事罰で強制して、曲尺・鯨尺では実際に処罰された例もあるのだ! タレント文筆家であった故永六輔氏が和裁に必須の曲尺・鯨尺をメートル法による処罰付き禁止に怒り、縁日を回っては曲尺・鯨尺の物差し(直定規)を大道販売して歩き「俺を捕まえろっ」と叫んでいたが、さすがに有名人に過ぎて「芸能活動」と解釈して検挙しなかった。 そういう恣意的解釈も無茶であるが、永氏にメートル法処罰規定の違憲性を最高裁まで争われては堪らないと判断したのだろうか? (2026/01/03追記4.2節) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [Page Top↑] |
 旧 |
 新 |
 Geo雑談 |
 前 |