[477]
mailto: | |||||||
 媽 |
 怴 |
 Geo擔婰 |
 Geo嶨択 |
 撪専嶕 |
 慜 |
 庡栚師 | |
[477] |
| |||||||||||||||
愥偱僽儗乕僉棙偐偢捛撍両杒嫗抧壓揝
丂丂丂丂丂丂撉攧怴暦 2023/12/15 20:06 |
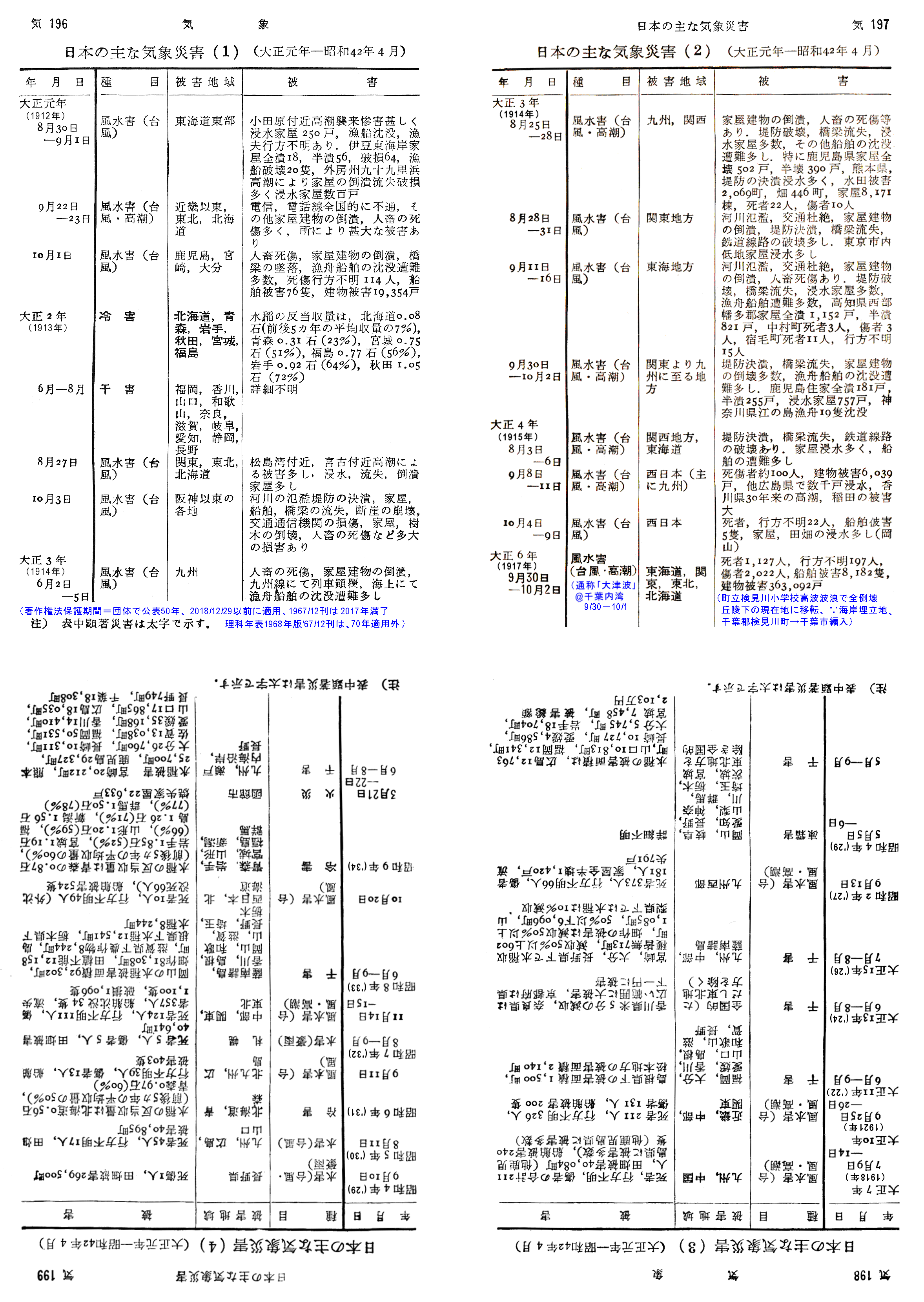
A3斉偺椉柺報嶞偱4儁乕僕亊2丄仾Click Here両 |
戝惓6擭偺戝捗攇両丂戝惓6擭乮1917擭乯9寧30擔偼丄搶擔杮偑嫄戝戜晽偵廝傢傟偰丄搶嫗榩娸偵傕懡戝側旐奞傪弌偟丄愮梩孲専尒愳挰偺奀娸偵棫抧偟偨挰棫専尒愳彫妛峑偑崅挭丒攇楺偲嫮晽偱慡夡偟丄尰嵼抧偺媢椝壓2挌栚偵塣摦応晅偒偱嵞寶偝傟傞偙偲偵側偭偨乽戝惓6擭偺戝捗攇乿敪惗偺擔偱偁傞丅撪棨懁敤挰偵挰棫敤彫妛峑愓傕巆偭偰偄傞偑丄偙偺摉帪偺彫妛峑偵乽塣摦応乿偼柍偐偭偨條偩丅丂巹偺曣偼偙偺戝惓6擭9寧30擔偵敿擾敿嫏偱曢傜偟偰偄偨専尒愳挰奀娸増偄偺帺戭偱惗傑傟偨偑丄壠拞偑寖偟偄崅挭旐奞偺屻曅晅偗偵庤傪偲傜傟偰弌惗撏偑1儢寧傎偳抶傟偰丄曥採帥偱偁傞忩搚廆慞彑帥偺屼廫栭朄梫擔10寧18擔乮忩搚廆杮棃偺媀幃偱偼懢堿楋11寧5擔乣15擔朄梫傜偟偄乯傪弌惗撏忋偺抋惗擔偲偟偰挰栶応偵撏偗弌偨偺偩偲偐丅帺戭弌嶻偺帪戙丄偺偳偐偩偭偨偺偐丠両偙偺巹揑僄僺僜乕僪偱乽戝惓6擭偺戝捗攇乿偼朰傟側偄丅9寧30擔偼曣偺柦擔偱傕偁偭偰丄杮摉偼枮92嵨偺抋惗擔偵朣偔側偭偰偄傞丅 |
壒柤偼乽B乿偐乽H乿偐丠両丂棟壢擭昞偵偼暔棟愡偺乽壒乿偺復偱A=440.0Hz偱偺乽暯嬒棩壒奒廃攇悢乿偑帵偝傟偰偄傞偑丄偦偺廃攇悢昞偱梡偄傞壒柤乮A乣G丄僀乣僩乯偑丄彫拞妛峑偱梡偄傞塸暷幃偱偼側偔丄僪僀僣幃偺乽H丗乮僴乕乯乿偑梡偄傜傟偰偄偰戝曄傑偛偮偐偣傞丅丂嶲峫彂傪擿偔尷傝丄彫拞妛峑偺嫵壢彂偼塸暷擔幃偺壒柤傪愢柧偟偰偍傝丄僪僀僣幃乽H乿偺婰嵹偑柍偄偙偲偑懡偔偰丄偦偺応崌丄棟夝晄擻丗崙揝怴掃尒婡娭嬫屼梡払墶昹弔晽嵗岦偗偺摿庩壒奒偐丠偲側傞丅 丂僪僀僣幃壒柤偲丄僽儔僗僶儞僪乮嬥娗妝婍俛乮儀乕乯娗乯偱偼乽B:乮儀乕乯乿偼丄塸暷幃偺B壒傛傝敿壒掅偄B侒偱丄B壒偼乽H乿偱昞偡偐傜丄娫堘偄偱偼側偄偺偩偑丄擔杮偺彫拞妛峑偺壒妝嫵堢傪庴偗偨憌偵偼傎偲傫偳捠偠側偄丄擔杮偺棟壢擭昞偵偼晄揔愗側昞婰偱偁傞丅 丂壒奒偺婎弨廃攇悢偑1938擭5寧崌堄偺崙嵺婯栺偱A亖440Hz偲掕傔傜傟偰偄傞偑丄擔杮偱偼弶偺僋儔僔僢僋愱梡儂乕儖丗僒儞僩儕乕儂乕儖偺僺傾僲挷棩偑A=442Hz偱峴傢傟偰僋儔僔僢僋奅偵岲昡傪摼偨偙偲偱丄屻懕偺壒妝儂乕儖偺僺傾僲挷棩偑A=442Hz偑庡棳偵側傝丄偦傟偵傛傝尞斦幃揹巕妝婍偵傕僺僢僠挷惍乮廃攇悢挷惍乯婡擻偑晬偝傟偰丄440/442Hz椉曽偺挷棩偵懳墳偱偒傞傛偆偵偟偨丅 丂棟壢擭昞奩摉復偺乽ゥゥ祩﹤祵粛輭箠y娭學偱偼庡偲偟偰倎1亖442Hz偑梡偄傜傟偰偄傞乿偲偟偰偄傞偺偼丄壒妝偼僋儔僔僢僋偺傒偲偄偆嫮偄巚偄傪攚宨偵彂偐傟偰偄傞傛偆偩丅 偟偐偟壒掱偺昗弨壒嵆偼堦娧偟偰A:440Hz偑巗斕偝傟偰偄偰丄A:442Hz偼尒妡偗側偄丅壒妝夛偺崅壒壔嫞憟夞旔偺怽偟崌傢偣偱丄戝愄偼僼儔儞僗偑A=435Hz傪朄棩偱掕傔丄偦傟偼愴慜偺擔杮偵傕嵦梡偝傟偰偄偨偑丄1939擭5寧偺儘儞僪儞偱偺崙嵺夛媍偱倎1丗440Hz偺懳悢棪嵦梡傪怽偟崌傢偣偰尰嵼偵摓傞丅 嬤擭丄擔杮偺僋儔僔僢僋奅偱晛媦偺A=442Hz偼僒儞僩儕乕儂乕儖乮偺僺傾僲乯偵嵦梡偝傟偰偐傜屻懕偺壒妝儂乕儖乮偺僺傾僲乯偵懡偔奼偑偭偨偑堦愗偺崌堄偼側偄偺偩丅 丂婰帠偼棟壢擭昞偺奺暘栰幏昅扴摉幰偵擟偝傟傞偨傔丄懠暘栰偐傜偺廋惓偑弌棃側偄偺偱丄幏昅幰偑朣偔側偭偰丄偦偺傑傑挿婜偵乽H乿昞婰偵側偭偰偄傞偦偆偩偑丄1968擭斉棟壢擭昞41嶜偱偼暷塸擔幃偺乽B乿壒偲昞婰偝傟偰偄傞丅 偦傟埲崀偺埥傞斉傪嫬偵B仺僪僀僣昞婰丗H偵曄偊傜傟偨傑傑偵側偭偰偄傞偺偩傠偆丅 場傒偵丄棟壢擭昞慡姫偼崙棫揤暥戜堦斒岞奐帪偵傾僀儞僔儏僞僀儞搩乮懢梲岝暘岝憰抲乯撪偵揥帵偝傟偰偄偨丅愴帪拞WW2偺嶰擭暘偩偗敪峴拞巭偲側偭偰偄傞丅 |
| [Page Top仾] |
 媽 |
 怴 |
 慜 |